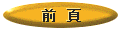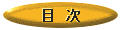気分はインディー・ジョーンズ!
アメリカ国内を旅行しながら、ちょっと日本とは違う体験をすることがある。かつてプロダクション業務の関連でラーフリンという小さな町へ出張した時のことだ。この町はネバダ州南端に位置し、コロラド河岸へ巨大なカジノが数軒並ぶ以外は何もない。ラスベガスのカジノでディーラーをやっていたラーフリンという男が、将来を見越し、もともと何もない砂漠にせっせと貯めた金でカジノを建てるところから始まった。
ラーフリンの夜景
映画“バグジー”を見ればわかるとおり、ラスベガスも最初は(ウォーレン・ビューティーとかなりルックスが違う)実在の人物である主人公が砂漠のど真ん中へ建てたカジノ1軒しかない。今のフラミンゴ・ヒルトンである。そのラスベガスはわずか数十年で驚異的な発展を遂げ、続けとばかりにリノとレークタホが誕生した。いわばこの路線の新顔であるラーフリンは、そこへさらに続く。
そして規模がどうあれ、これらの町へは必ずメジャーのカジノが進出しており、中に入れば何処も同じだ。ただし、表は違う。いくらカジノの建物が立派でコロラド川へはノスタルジックな遊覧船が浮かんでいようと、囲りは本当に何もない砂漠なので、よけいギャップが激しい。対岸の飛行場も、管制塔はおろか飛行場らしき建物など皆無である。
そもそもラーフリンへ行くことになって、まず電話で飛行機を予約したわけだが、予約手続きの途中、荷物の量を聞かれたあたりで不吉な予感を覚え、体重を聞かれるに至って頭は混乱した。当日、出発地であるLAX(ロサンゼルス国際空港)へ着くと目指すターミナルが見つからず、ようやく南側のカーゴ専用棟に混ざってポツンと建ったターミナルを発見し、十数人乗れるか乗れないプロペラ機を見た瞬間、私は電話で聞かれた質問の意味を理解する。係員が乗客の荷物や体重と相談しながら席を割り当て、いざ出発だ。
狭いシートで何時間か揺られた後、機長自らの機内アナウンスはラーフリン上空へ差しかかったことを告げる。アプローチの態勢に入り、窓から下を眺めれば、コロラド川と平行した未舗装の短い道路しかない。それが滑走路だとわかって間もなく、飛行機を降りた私はすぐ横の船着場へ降りてゆく。そこからホテルの建ち並ぶ対岸を、無料のフェリーボートが定期的に行き来しているのである。
その日はともかく仕事を済ませ、翌日、飛行機の出発時間まで少し余裕があったので、私は初めてフェリー乗り場近くのカジノを覗いてみた。ブラックジャックがいい感じでノリだした頃、カジノの場内アナウンスは誰かを呼びだしており、それが自分の名前と似ているような気がした私は、まさかと思いつつ耳を澄ます。間違いない。どう考えても飛び込みのカジノから呼び出される理由がわからないまま、とりあえず指定されたフロントデスクへ向かう。
「横井ですが?」
「オー、ミスター・ヨコイ、申し訳ありませんが、あなたのお帰りの飛行機は欠航になりました。ですから、私共のほうで今夜のお部屋をご用意させていただきたいのですが」
「えっ! なんでまた?」
「パイロットが風邪で、とても飛べる状態じゃなくなったんです」
「そう言われても困る。私は明日、L・A(ロサンゼルス)で大事な会議があるから、どうしても今日中に帰らなくてはならないんだ。なんとかして下さい」
「たった1便の1人しかいないパイロットが寝こんでしまった以上、なんとかしたくても無理ですわ」
「それじゃ、会議に出られなくて被った損害は、お宅がカバーしてくれるのか?」
「・・・・・・」
「最悪の場合、自分で運転してでも帰るから、レンタカーを用意してもらう。だが、その前に何か手はあるだろう? 考えてみてくれ、30分後に戻ってくる」どうせ、すぐ答が出ないと判断した私は、いったん引き下がって時間をつぶす。飛行機会社のオフィスがない以上、ホテルで業務を代行しており、乗客への緊急連絡は数軒のカジノが場内アナウンスをすれば事足りるわけだ。そう思うと改めて小さな町の規模が実感できる。フロントデスク嬢の話しぶりでは、風邪で寝込んだパイロットもここがベースか、あるいは地元と密着した人間らしい。
そんなことを考えながら30分が過ぎ、あまり期待はできそうもなく、これからの長いドライブを思うと憂欝な頭でフロントデスクへ戻ると、
「オー、ミスター・ヨコイ、お待ちしてました」
「どうなった?」
「今夜、ラスベガスに行く郵便飛行機があります。そこへ便乗させてもらえれば、ラスベガスからL・A行の便がぎりぎり間に合うはずです。小さな飛行機で郵便物のスペースしか空いていないかもしれませんが、どうしてもとおっしゃるのでしたら頼んでみます」
「ぜひ、頼む!」
「乗り心地は保証できませんよ」
「そんなもの、どうだっていいさ!!」郵便屋(パイロット)が承諾してくれて、その夜、私は機上の人
正確に表現するなら郵便物の一部となった。4席分の2席を残し、残るスペースは大きな郵便袋が占めている。こちらへもたれかかった郵便袋は私の席がスペアであることを主張し、なんとなくヒッチハイクでトラックの荷台に乗っている雰囲気だ。じっさい、料金を取られるわけでもなく、ヒッチハイクで乗った荷台という点は事実であった。しかし、隣で陽気に話す若い郵便屋(パイロット)といい、久しぶりで乗ったプロペラ機の感触といい、なんともはや現実離れをした世界なのである。プロペラ機でもコマーシャル用のほとんどが、来る時同様、いわゆるジェット・プロップと呼ばれるタイプだ。それと比べてこの郵便飛行機は昔ながらのレシプロ・エンジンなので、スピードが劣るばかりでなく飛べる高度はかなり低い。まさしくトラックの荷台の世界であるいっぽう、低空飛行ゆえ地上を見下ろすと闇の中でぼんやり浮かぶ砂漠の夜景が目と鼻の先まで迫り、心をぞくぞくさせる。
まして、ラスベガス上空へ差しかかり、突如としてまばゆいネオンの渦が舞い始めた時の感動たるや、低空からのアプローチでしか味わえないド迫力の臨場感だ。ジェット機やジェット・プロップ機で接近するラスベガスの夜景も素晴らしい。しかし、レシプロ機の低空で接近する感触を3Dの世界だと仮定すれば、高高度での接近は2Dの世界にすぎないのである。ラーフリンの小さな飛行場を飛び立って以来、なぜか頭の中がインディー・ジョーンズの気分で染まってゆく。
もっとも、ラスベガスへ着くとコマーシャル用の空港に移動しなくてはならず、のんびり構えている余裕などない。ラスベガスの夜景が見えた頃、郵便屋(パイロット)へ管制塔と無線連絡を取り、到着した時点でタクシーを待機させるよう手配を頼む。急がないとL・A行の最終便を逃がす。時間との競争は体内のアドレナリンを促し、頭の中がますますインディー・ジョーンズに・・・・・・
かつてはハワード・ヒューズ個人の持ち物であった業務用のプライベート空港へ着陸するや、郵便屋(パイロット)に一礼した私はひと気のないターミナルを駆け抜け、筋書どおり玄関先で待機中のタクシーへ飛び込む。わずか数分のドライブが、やけに長い。そして、チェックインの後、急ぎ足でゲートへ着いた時は、ほとんどの客がすでに搭乗手続きを終えている。
立っている客もまばらとなった機内で囲りの視線を浴びながら、ようやく自分の席を見つけて落ち着き、「ああ、文明社会へ戻ってきたんだ!」という実感を抱く心の片隅では、ありきたりのボーイング機が初めて太平洋航路を飛んだパンナムの水上旅客機へオーバーラップしたものの、パンナム機に乗ったインディー・ジョーンズと自分自身の姿は重なりそうで重ならなかった・・・・・・たまたま、同じような帽子をかぶっていたのだが!?
横 井 康 和