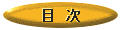初めてのビッグディール
初めてのビッグディール
20年来の親友マイク・アーウィンと幼い頃からの夢だった映画製作に乗り出して3ケ月目、それは1990年の春だった。ウィルシャー通りの武道の道場で、いつものように稽古をしていると、UCLA(カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校)の後輩である若手脚本家エド・ソロモンが彼のヒット処女作「ビル&テッズ・エクセレント・アドベンチャー」の続編を、前作でボケ役が好評だったキアヌ・リーブスという東洋系の俳優で作る企画が進んでいる、と得意そうに言ってきた。
こいつはまだ21才のくせ、初めてのスタジオ作品をヒットさせた上、大監督シドニー・ポラックの次作を80万ドルで書く契約を結んだばかりの強者(つわもの)である。人の成功は自分の励みと思いつつ、何気なく、
「ところでお前、今まで書いた作品中、とくに気に入ってるものでスタジオ(大手の映画製作配給会社)から蹴られた企画はないの?」と聞いてみた。何が僕にその質問をさせたかは未だにわからないが、その瞬間が僕のプロデューサー人生を変えた。
翌日、ソロモンから「マム&ダッド・セーブ・ザ・ワールド」(邦題:「スペース・エイド」)という1冊の脚本が届いた。同封の手紙には、
「マックス、この企画はすべての大手スタジオから蹴られたけど、その理由はSFの主人公が父ちゃん、母ちゃんでは無理ということなんだよ。でもこれは僕の最高傑作、ぜひ映画化してくれ!」とあった。読み始めるや2時間がアッという間に過ぎ去り、まるで本当の映画を見たような興奮を覚えながら頁を閉じた。今まで多くの脚本を読んできたが、あの2時間ほど印象に残るケースは数少なかったと思う。そして、この映画を作り、僕が感じたのと同じ感動や笑いを人々と分かちたい衝動にかられると同時、ハリウッド中で蹴られたという企画製作へ挑戦してみたくなった。
 さっそくソロモンとその弁護士から非常に安く向こう1年間の権利(オプション)を買い、電話で中堅の配給会社や製作会社に当たってみるが反応はない。そこで、粗筋や希望俳優リストを加え、製作予算や撮影スケジュールなどをコンピュータでパッケージ作成中、とある情報が目に止まった。
さっそくソロモンとその弁護士から非常に安く向こう1年間の権利(オプション)を買い、電話で中堅の配給会社や製作会社に当たってみるが反応はない。そこで、粗筋や希望俳優リストを加え、製作予算や撮影スケジュールなどをコンピュータでパッケージ作成中、とある情報が目に止まった。
それはアメリカ最大のケーブルTV局であるHBO(ホーム・ボックス・オフィス)がウォール街で6、000万ドルの映画投資基金を調達し、ワーナーブラザーズ・スタジオと組んで大型映画業界へ進出するため、現在、風変わりな企画を募集中という業界紙の掲載記事であった。「これだ!」と直感した僕は相棒のアーウィンに相談した。結果、僕同様この脚本にぞっこんの彼が素晴らしいゲリラ作戦を考案し、われわれ2人は彼の計画通りサンセット通りに面したエリート男性の社交場「ジョナサン・クラブ」へと向かった。
武道を愛するアーウィンは、そこで週2回の早朝稽古のインストラクターを務めていた。利用する客のほとんどが一流企業、それも保険や金融関係の重役クラスで、1日の仕事の前に武道で汗を流し、サウナに入ってからアルマーニのスーツをビシッと着込んで企業戦線に出かける猛者たち・・・・・・日本風に、そのクラブ内で大きな事業がまとまるケースがけっこう多いらしいという噂を頼りに、ウォール街とコネのある人間からHBOへ橋渡しをしてもらおうというのが僕たちの計画だった。ゲストとして一緒に稽古を終え、ニューヨークを基盤とする大手証券会社の西海岸責任者だというミスター・ジオダノに狙いを定めた僕たちは、文字どおり裸一貫でサウナに入って行った。
誰も相手にしてくれない企画への僕たちの情熱と、サウナで言い寄った度胸が気に入られ、また氏の故郷のボストンで僕が大学院時代を過ごした偶然もあって意気投合し、「案ずるより生むがやすし」の諺(ことわざ)どおり、話はトントン拍子に進んだ。ミスター・ジオダノが、映画化の際は彼の証券会社へ手数料を支払う約束で、直接HBOの製作責任者に例の脚本を届けてくれることになり、ハリウッドが人脈ビジネスと言われる理由を肌で感じさせられた。
それから3週間後のある日、ガレージを改装した電話が2台あるだけの僕たちの事務所へニューヨークから電話がかかり、それに出たアーウィンが真っ赤な顔で、
「おい、HBOだ!」と、その声でもう1台の受話器をとった僕の耳にハッキリとした声が、
「そちらは『マム&ダッド・セーブ・ザ・ワールド』を所有しているプロダクションですね?」と尋ねた。アーウィンが少し震える声で「イエス・・・」と答えると同時に、「この企画を是非やりたのです・・・」という言葉が確かに聞こえたような気はしたが、あとの会話は未だにボーっとしている。
その後、ニューヨークからやって来たHBOのお偉方とのビバリーヒルズ・ホテルでの会食の席上、このオファーの株主達は実績のあるプロデューサーとの契約を条件としているので、現在、ワーナーブラザーズ側は、マイケル・ダグラス、マイケル・フィリップス、ジョエル・シルバー(「ダイ・ハード」)、アーロン・ルソー(「トレーディング・プレース」)と契約し、彼らに製作してもらうつもりだと勧告される。
また、この企画が気に入っているので、我々に売却してくれないかと言われた時、僕の耳の錯覚なのか、ポロ・ラウンジのピアノが「ホェア・イズ・ユア・ドリーム?」と歌っているように聞こえた。結局、「われわれが製作できないなら、この話はあきらめて下さい」とカッコよく立ち去ったものの、何か後ろ髪を引かれる思いが残った。
それから2日後、初めての契約だからだと無理して雇った一流弁護士のキース・フリアーより連絡が入り、
「おいおい、あまり最初から無理を言っちゃダメだぜ。今はとにかく実績を積むことが一番大事、ここは俺に任せてくれ」と言う彼に、1つだけ条件をつけて交渉を頼んだ。
その条件とは、投資家の意見には従うが、契約した4人の中から僕たちが1人を選び、その人と一緒に製作をさせてもらうということ・・・・・・会社設立で、喉から手が出るほどお金は欲しかったが、それだけで外されるのは、自分の子供を金で養子に出すような辛さ。夢か金か?・・・・・・僕たちはハリウッドの入口で、しばらく踏切が開くのを待つことにした。
数回の話し合いの後、最終的にはSFコメディーという企画の特性を吟味して、「未知との遭遇」のプロデューサーであり、「スティング」でアカデミー賞を受賞したマイケル・フィリップスと共同製作をするということで一件落着し、その後8ケ月間、素晴らしいボスのマイケルのもと、キャスティングから脚本会議、セットのデザインまで広域に渡って製作を続け、プロデューサーとしてだけでなく、人間的にもいろいろな勉強ができた。
HBO側が送り込んでくるアイビー・リーグ出身の若手マーケッティング・マンとワーナー側の(俗に「スーツ」と呼ばれる)監視役との板挟みになったり、創作面でスタッフとトラブったり、映画自体は思ったほどヒットせずガッカリしたが、1年の大半を200人近い人々と過ごし、人間関係や製作上の葛藤などを通して自分の夢に執着することで起こる奇跡や、新しく満ちあふれてくる自信を自ら体験できたことが、なんといっても一番大きな収穫だったと思う。