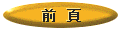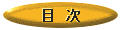28ケ月間世界一周
28ケ月間世界一周
6年間アメリカで暮らした後、世界旅行を決意した僕が、現金800ドルと毛布や着替えの入った大きなリュックサックを背負い、雪の降りしきるボストンを後にしたのは1977年の暮だ。当然ながら、自分の将来のことなど、現実への不安はあったが、未知との遭遇、自分の知らない文化との出会い、そこで育った人々との交流を思えば胸は高鳴り、もはや旅立たずにはいられなかった。
グレイハウンド・バスでボストンを発つ僕が考えていた計画(プラン)は、まず歴史の匂いを嗅ぎながらアメリカ東海岸をフロリダ州まで南下し、ディズニー・ワールド、NASA、マイアミ・ビーチなどを見た後、さらにミシシッピー州、ルイジアナ州と南部経由でテキサス州へ向かう。そして、メキシコ、グァテマラ、ニカラグア、コスタリカと中米諸国を巡りながらパナマ運河を経て南米に入り、コロンビアからインカ帝国遺跡のあるペルーへ・・・・・・いちおう、そこまでのアウトラインしか決まっていない。
とにかく、感性のおもむくまま世界を見たい、その願望が将来のことはおろか、映画のこと、大学のこと、その他、諸々の現実を放りなげてまで僕を旅立たせた以上、何事にも束縛されたくなかったのである。じっさい「カメラも時計もない旅」を始めるや、頭の一角を占めていた経済的な不安なども払拭され、僕はグレイハウンドの窓の向こうで流れる景色へ心を奪われていた・・・・・・この旅が将来、映画プロデューサーとして、あるいは1人の人間として、どれだけ多大な影響を及ぼすなど思いもよらずに!
ジョージア州の片田舎で初めてバスを降りた僕は、停留所近くのカフェテリアへ入る。コーヒーを飲んでいると、なんとなく見られているようで居心地が悪い。話しかけた地元の客は、まるで僕を無視するかのごとく無関心を装う。その瞳の奥に憎悪の光が宿り、ますます不可解だ。と、年配のウェイトレスから、
「この町は息子たちを第二次大戦で亡くした人が多いのよ。たぶん『ジャップ』を見るのも初めてかもね」
ぶっきらぼうに言われ、僕は返す言葉がない。その一方で、若いウェイトレスは視線が合うと偏見のない笑みを浮かべ、ますます世代のギャップを感じさせる。また、彼女の笑みは囲りの反感を誘い、いよいよ険悪な雰囲気なのだ。東部と南部の違いこそあれ、まさに“イージーライダー”の世界だ。しかし、彼らの気持ちもわかるような気がして、数分後、店を出る時、僕は深々と頭を垂れて一礼した。バスへ乗ろうとする僕を不思議そうに見つめる彼らの中でも、ひときわ皺(しわ)の深い老人の目から憎しみが消え、微笑すら浮んでいると思ったのは、僕の目の錯覚だったのであろうか?
マイアミのYMCAで知り合ったドイツ人の放浪者がいろんなヨーロッパ情報をくれたおかげで、南部道中は、なんとなくこの先の旅が長引きそうな予感にかられながら始まった。ニューオリンズ名物のバーボン通りではアメリカで息づくフランス文化を実感し、テンガロン・ハットやカウボーイ・ブーツがその独自の文化を象徴するテキサスでは、あまりの広さに外国へ来たような違和感を覚える。そして、サンアントニオのアラモ砦遺跡が、幼い頃母と見た同名のジョン・ウェイン主演映画で涙した瞬間を思い出させ、日本の家族に想いを馳せたものだ。
 メキシコでは、学校へ行かず通りすがりの車に窓拭き代をたかるメヒカリの少年たちと、高級リゾート・ホテルがひしめき合うカンクーン海岸で日光浴をする金持ち連中との、あまりの貧富の差が理解しがたかった。中南米では「貧乏」と「政治の腐敗」が国民色になっているかのごとき現状を見て、僕の考え方は根本から覆(くつがえ)されてゆく。コスタリカの熱帯ジャングルで知り合った原住民との触れあいを通じ、「地球人として生まれてきた歓び」を感じ、いつしか軍事独裁政権下の母国から憧れの国アメリカへ逃れ、家族に心の安らぎを与えたいと語るエル・サルバドールの情熱的な青年との握手へ「地球」を感じた頃、旅立ちから早1ケ月が過ぎようとしていた。
メキシコでは、学校へ行かず通りすがりの車に窓拭き代をたかるメヒカリの少年たちと、高級リゾート・ホテルがひしめき合うカンクーン海岸で日光浴をする金持ち連中との、あまりの貧富の差が理解しがたかった。中南米では「貧乏」と「政治の腐敗」が国民色になっているかのごとき現状を見て、僕の考え方は根本から覆(くつがえ)されてゆく。コスタリカの熱帯ジャングルで知り合った原住民との触れあいを通じ、「地球人として生まれてきた歓び」を感じ、いつしか軍事独裁政権下の母国から憧れの国アメリカへ逃れ、家族に心の安らぎを与えたいと語るエル・サルバドールの情熱的な青年との握手へ「地球」を感じた頃、旅立ちから早1ケ月が過ぎようとしていた。
南米ペルーのマチュピチュは科学や考古学の見地から諸説のある不思議な遺跡だ。古代インカ帝国が建てた山岳都市という定説ながら、電車に揺られて長い道のりの果て、出現するその光景は、人間が構築した都市とは思えぬほど異様である。これだけの高地へ、どうやってあのような街を建てられたのか不思議でならない。宇宙船の発着場だったという説もある滑走路のような平地でたたずみ、「地球の旋毛(つむじ)」とも呼ばれるこの古代遺跡の真ん中に立つと「地球人以外の存在」が力強く感じられ、僕のそれまでの人生観は吹き飛ばされてしまう。
日々の喧噪、仕事や人間関係の摩擦など、現代人のストレスを温かく包み込むかのごとくそそり立つマチュピチュの神秘。UCLA時代に訪れたグランド・キャニオン以来の「地球の神秘」と触れた僕は、そのエネルギーにわけもなく涙が溢れ出てくる。あれは、きっと遠い昔に宇宙の彼方から飛来し、われわれのDNAに刻み込まれた魂が、当時を懐かしんでいたのかもしれない。
ペルーの山奥で表現しがたい感動の瞬間を体験した結果、そこから先の予定はおのずと決まった。それは何事にも束縛されない、さらなる「時間のない旅」を続けることであった。気分がおもむくまま、好きな街で好きなだけ時を過ごす。生活費はその場その場で調達すればいい。かつて憧れた世界を放浪する日本人青年の姿が自分の姿と重なり、僕は二度とない青春を悔いなく送ろう決意したのである。ペルーへ至る旅で得たかけがえのない体験を、もっともっと重ねたいという「若さのなせる技」であったともいえよう。
次の日から新たな旅が始まった。当時一泊8ドル程度のユース・ホステルやYMCAを根城に、同じ南米でも赤道を隔てた文化の違いを肌で感じながら、ボリビア、チリ、アルゼンチンと南米大陸西部を南下した後、ブラジルへ北上する。アマゾンのジャングルで数日を過ごし、日本人移民の目立つサンパウロ、褐色の美女に印象づけられたリオデジャネイロなどを経て、今度は航路アフリカ大陸を目指す。
懐具合が寂しい僕に客船の切符を買うのはとうてい無理だ。かといって“タイタニック”の主人公と違い、それをギャンブルで勝ち取るだけの才能や運があるはずもない。結局、ケープタウンへ向かう貨物船で甲板掃除の仕事を見つけたのである。チリ以来ずっとパンと豆の毎日だった僕は、3食付きでアフリカに渡れるなど夢のような話・・・・・・と思いきや、これが意外と重労働なのだ。天候さえ穏やかなら、食後はデッキで昼寝をする余裕もある一方、海がしけた時は大西洋の荒波が大きな貨物船を弄(もてあそ)び、夜など初心者の僕にはたまらないほど揺れる。
オランダ系白人が上級船員のほとんどを占めるその貨物船は、下級船員、つまり労働者のほとんどがアフリカ系黒人だ。朝は船酔いした彼らの汚物で蒸す船内の掃除から始まり、連日、汚物の臭いと弱り切った体力との戦いである。しかし、8日間の航海が終わる頃、体力はついた上、それぞれ興味深い背景を持つ船員との交流や3度の食事へ感謝の念を抱きつつ、僕は喜望峰を望む。
 アフリカ大陸の土を踏んだ後も、いま振り返ると気が遠くなりそうなほど、果てしなく旅は続く。南アフリカ、モザンビーク、タンザニア、ケニア、エチオピア、スーダンとアフリカ大陸の東海岸諸国を巡りながらエジプトに北上し、ピラミッドやスフィンクスで再び「地球の神秘」と触れたことが、いよいよ僕の人生観を覆(くつがえ)す。そして、リビア、アルジェリア経由でモロッコへ辿り着き、そこから南北アメリカ、アフリカに続く4番目の大陸、ヨーロッパを目指して地中海を渡る。
アフリカ大陸の土を踏んだ後も、いま振り返ると気が遠くなりそうなほど、果てしなく旅は続く。南アフリカ、モザンビーク、タンザニア、ケニア、エチオピア、スーダンとアフリカ大陸の東海岸諸国を巡りながらエジプトに北上し、ピラミッドやスフィンクスで再び「地球の神秘」と触れたことが、いよいよ僕の人生観を覆(くつがえ)す。そして、リビア、アルジェリア経由でモロッコへ辿り着き、そこから南北アメリカ、アフリカに続く4番目の大陸、ヨーロッパを目指して地中海を渡る。
ポルトガルからスペイン、フランス、イギリス、そしてドイツ、スイス経由でイタリア半島へ向かい、イタリアは相性が良かったのか、北部、南部を含めて2ケ月ばかり滞在した。その後、オーストリア、チェコ、ポーランドなどの東欧諸国に続いて、オランダからデンマーク、ノルウェー、スウェーデンと北欧3国を訪れる。さらにフィンランドから現在のリトアニア、ポーランド経由でハンガリー、ルーマニア、ブルガリアからギリシャへと抜けた。
ギリシャでは古代遺跡に感動し、そこからトルコへ向かい、シリア、レバノン、イスラエルと下って聖地エルサレムに着く。さらにヨルダン、サウジアラビアと中東を南下し、当時は平和なイラク、イランから、いよいよアジア大陸へと舞台が変わる。アフガニスタン、パキスタンを経てインドに入り、カルカッタでは1ケ月間ヨガの学校へ通う。その後、ネパール、ブータンを回って、ブルマ、タイ、マレーシア、シンガポールに足を伸ばす。
インドネシアを周遊後、ラオス、フィリピン、マカオから香港へ着く。そこで3週間ホテルのベルボーイをやりながら骨休めをした後、空路、6番目の大陸オーストラリアに向かう。パプア、ニューギニーやソロモン諸島まで足を伸ばす途中、生々しい戦争の傷跡が心を痛め、その時の衝撃も「地球の神秘」同様、この旅で獲た貴重な経験だ。
ニュージーランド、フィジー、トンガ、サモアと南太平洋諸島を巡り、ハワイへ辿り着く頃、長い旅はそろそろエンディングを迎えようとしていた。ハワイで数週間、通訳のアルバイトをした後、空路カナダのバンクーバーに向かい、そこからカナディアン・ロッキー山脈横断鉄道でモントリオール、トロントを回り、締めくくりがナイアガラの滝である。新婚旅行中とおぼしき観光客に混ざって絵はがきのような景色へ感動した後、マサチューセッツへ戻ったのは、雪の降りしきるボストンを後にして2年4ケ月を経た初夏のことだ。髪の毛が30センチ伸び、髭はボウボウであった。また、音信が途絶えた僕を心配し、母は捜索願を出していると知ったのも、戻ってからである。
世界旅行の後、2年間ニューヨークで俳優学校へ通い、いよいよロサンゼルスに戻るのが1982年の夏だ。ハリウッドを目指して「華の都(ティンセル・タウン)」へ舞い戻った僕は、旧友であるマイク・アーウィンと映画のプロダクションを設立し、ようやく長年の夢を実現した。いまハリウッドで映画を作る人間として、また常に向上心を持つ人間でありたいと願う僕は、あの世界旅行から学んだことがその後の人生へどれだけ影響したかを考えるたび、改めて衝撃(インパクト)の強さを感じずにはいられない。
キャンパスや本で学ぶ知識が人生の指針となるのは当然だ。しかし、キャンパスや本でどれだけ学ぼうが、見知らぬ土地で出会う人間や文化、そこへ秘められた歴史の重みなどから直接学ぶ知識とは比べようがなく、それゆえ「百聞は一見にしかず」という。僕がそれを痛感できたのも、あの世界旅行の時であった。以来、他人(ひと)と触れる中で自分の感性を高めることは、他人(ひと)の心を動かす創作の原動力へつながってゆくと信じている。
ハリウッドという独特な「宇宙」、映画のセットや脚本会議で触れる何百人もの人々。時として自分が状況や感情に振り回されていると気づく瞬間、その1人1人の表情は、あの世界旅行で見た目や涙や笑顔とダブり、じっと僕を見守ってくれているように思えてならない。そんな時、他人(ひと)との触れ合いから獲たエネルギーを1つにまとめることこそ、いい映画作りの第1歩だという気がする僕なのだ。