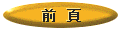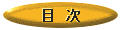太陽の彼方へ!
太陽の彼方へ!
渡米一年後、ハイスクールを終え、UCLA(カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校)の奨学金を受けた僕が専攻するのは、いうまでもなく映画学科であった。そして、庭師の助手(ガーデナー)や日本レストランの皿洗い(キッチン・ヘルパー)といったアルバイトで生活費を稼ぎながら映画製作の基礎を学ぶと同時、日常生活を通じてキャンパス・ライフでは味わえない「異邦人」としての世界を垣間見る。日本にいれば、とうてい体験できなかっただろう。
日本レストランが数百軒以上ひしめく今のロサンゼルスと違って、当時はまだ日本人留学生の数も少ない時代だ。会う人間、会う人間で、示す反応がごろっと違う。日本のことを興味深く聞いてくる人間、露骨な人種差別をする人間、珍重されたり中傷されたりしながら、僕は新しい友人関係を築き始める。そんな中で学んだことは、どのような相手であれ会った人間から何かを獲ようとする姿勢だ。
ウェストウッドのUCLAへ通いだした最初の数ケ月間、まだ僕がアーウィン宅で居候をしている頃、マイクはビバリーヒルズ・ホテルでベルボーイのアルバイトに精を出していた。ホテルへ行き来するついでに、いつも僕を送り迎えしてくれた彼がある日、
「マックス、今日は用事があって迎えに行けないんだ。ちょうどいい機会だから、帰りはアメリカ文化の一つでもある『ヒッチハイク』を試してみればいい。すぐ誰かが拾ってくれるよ」と、言う。
その日の夕方、いつもはマイクを待つヒルガード通りに面したゲートの前で、行き交う車へ左手の親指を掲げる日本人を、何台もの車が怪訝そうに見るだけで通り過ぎてゆく。15分ばかり経っただろうか、僕は内心、「これじゃ話が違うぞ!」としびれを切らし始めたところへ近づいてくる一台のベンツ、運転しているのは善良そうな顔つきの中年紳士だ。運転席の窓を下ろした彼が、穏和な表情で何処まで行きたいのか聞く。そこで、すかさず、
「スタジオ・シティーです」と答えるや、助手席側へ回るよう首を振る。その合図で、僕はやっと安堵の息を漏らす。
豪邸宅が立ち並ぶベネディクト・キャニオンを抜けながら、ウォーレンというその紳士は自分が映画のプロデューサーであることや、有名な映画スターとの交流、あげくのはてはロサンゼルスの歴史までを懇切丁寧に説明してくれる。話を聞くうちベンツがハリウッドヒルへ差しかかり、峠を越すと目前に薄暗くなりかけたサンフェルナンド・バレーの街灯が開け、スタジオ・シティーは目と鼻の先だ。
ところが、その手前で突如ベンツは脇道へ逸れ、地理感がない僕はさほど不信感を抱かなかった。しかし、ひと気のない小道で止まって、ようやく異常に気づいた瞬間、いきなり僕の手を握ったウォーレンが、
「私は若い男の子が好きでたまらないんだ。これから家へ遊びに来ないかい?」と、熱い視線を投げかける。あまりのショックで思考力は麻痺したまま、僕はベンツを飛び出すや、カバンを抱えて元来た道を一目散に駆けだす。
ゲイが多いハリウッドで仕事をしながら彼らとつき合ううち、今でこそ偏見はなくなった僕も、さすが初体験のインパクトは強い。ただ、同じ初体験でも、カージャックやピストルを持った強盗事件が横行する昨今のロサンゼルスから比べ、なんと愛らしいハプニングであったことよ!
こうしてUCLAでの四年間はあっという間に過ぎ去り、将来を選択する時期が訪れた。ワーナーブラザーズ・スタジオの下働き(インターン)など、いくつかの就職口はあったが、エンターテイメント関連の法律を学ぶ必要性を感じる僕は、東部マサチューセッツ州ボストンにあるハーバード大学のポスト・グラジュエート・コース(大学院の準備コース)へ進もうと決意する。
その理由は、当時、ジョージ・ルーカス監督が'50年代の若者像を描いた"アメリカン・グラフィッティ"や、フランシス・フォード・コッポラ不朽のマフィア映画"ゴッドファーザー"など、スケールの大きな映画に圧倒された僕は、自分でも同じような「感動」を人へ与える仕事がしたいと思っていたことだ。やがては優れた創作性とビジネス感覚を兼ね備えたハリウッド映画プロデューサーになろうとすれば、それなりの準備がなくてはならない。
また、キャンパスで知り合った友人の多くが東部出身であったり、アルバイト先で知り合った日本人から興味深い東部の情報を聞いたりするうち、僕の内部では「イーストコーストへの憧れ」が脹らんでいたのも影響しているだろう。一年を通じて春と夏のようなロサンゼルスで過ごし、温暖な気候と相まって自分までなんとなく「イージー」になっていた当時の僕は、ごろっと響きの違うニューヨーク訛(アクセント)さえもが新鮮で、カリフォルニア以外のアメリカ文化を体験すれば人間として成長を約束されるような気がしていた。
11月末の感謝祭(サンクス・ギビング)といえば、アメリカでは重要な祭日だ。そもそも、イギリスから渡ってきた初期の清教徒が、暖かく迎えてくれた原住民のインディアンを七面鳥料理で持てなし、その慣わしを引き継いだこの祭日には、どの家庭も盛大な夕食会を開く。ふだん会わない家族が、この日とクリスマスだけは顔を合わす、いわば「お盆の里帰り」のような習慣もある。
独り身の留学生が一番孤独を感じるのはこういう時かもしれないが、僕の場合は幸いアーウィン一家という素晴らしい家族がいた。夕食会では毎年きまってマイクの両親が思い出話を語ってくれる。そのほとんどはマイクが生まれた頃住んでいたニューヨークの話だ。清々しい春先のセントラルパーク、コニーアイランド海岸へドライブした蒸し暑い夏の日、紅葉と青空が美しい秋のニューイングランド、ロックフェラーセンターのスケートリンクで過ごしたホワイト・クリスマスなど、目を輝かせて語る彼らの話を聞きながら、僕の脳裏を駆けめぐる東部のイメージ・・・・・・
日本食レストランで知り合った青山さんは、時を超えて自由奔放な世界旅行を続ける青年だ。その彼も、やはりニューヨークやマサチューセッツの文化、街並みに心を奪われていた。持ち金が底をつくと仕事をしながら放浪し続ける彼の生き方は、連日勉強とアルバイトで明け暮れる僕からすれば天国のような生活である。'70年代はまだ移民局も規制が緩く、旅行者が仕事をするのは意外と簡単だった。彼がメキシコへ旅立つまでの数ケ月間、一緒に皿洗い(キッチン・ヘルパー)やウェイターのアルバイトをしながら、開店前のひと時は彼の旅日談へ胸を躍らせたものだ。ニューヨークやマサチューセッツでの体験談を聞きながら、僕の脳裏を駆けめぐる東部のイメージ・・・・・・
こうした人々の影響で、まるで外国を夢見るような東部への憧れがいよいよ弾けんばかりのある早朝、コーヒー片手に東の空を望む僕は「虹の彼方へ(オーバー・ザ・レインボー)」ならぬ、
「よし、あの太陽の彼方へ行こう!」
と日の出に向かって独語し、とうとうマサチューセッツ州ボストンへ移住する。1976年の夏だった。
 アメリカでも独立戦争の頃から由緒ある街ボストン、チャールズ川が流れるその小じんまりとした瀟洒(しょうしゃ)な佇(たたず)まいは、ほぼ関東平野に匹敵する広さのロサンゼルスと比べ、まるで別世界だ。僕が落ち着いたケンブリッジという学生街のアパートは、学生専用だけあって夜でも騒音が絶えない。南カリフォルニアと違って湿気は多く、びっしょり汗をかきながら、住み慣れたロサンゼルスを去った実感が涌く一方、これから始まる新天地での生活へ心は弾む。空虚さと興奮が入り交じり、なんとなく心細い想いで過ごしたその夜の感触を、今でもはっきりと憶えている。
アメリカでも独立戦争の頃から由緒ある街ボストン、チャールズ川が流れるその小じんまりとした瀟洒(しょうしゃ)な佇(たたず)まいは、ほぼ関東平野に匹敵する広さのロサンゼルスと比べ、まるで別世界だ。僕が落ち着いたケンブリッジという学生街のアパートは、学生専用だけあって夜でも騒音が絶えない。南カリフォルニアと違って湿気は多く、びっしょり汗をかきながら、住み慣れたロサンゼルスを去った実感が涌く一方、これから始まる新天地での生活へ心は弾む。空虚さと興奮が入り交じり、なんとなく心細い想いで過ごしたその夜の感触を、今でもはっきりと憶えている。
東部で初めて迎えた厳冬、朝は降り積もる雪に埋もれた車を掻き出し、エンジンをかけるとヒーターを全開のままいったん家の中へ戻り、数分経ってから出かけるのが恒例となったある日のこと、どうやらエンジンは暖まった僕のポンコツ車を運転しているとブレーキが故障し、道ばたに掻き溜めた雪へ突っ込んで大事故を免れた。そうかと思えば、マサチューセッツ西部にある僕の好きなNBAの殿堂へ見学に行く途中、突然の吹雪で2メートル先も見えなくなって高速道路で立ち往生したりと、冷や汗もののエピソードは尽きない。
そんなエピソードの一つ一つをいま振り返ってみると、その後の僕の人生へ何らかの意味を持っている。出来れば避けて通りたい出来事は日常茶飯事だが、そういう出来事と直面した時こそ何かを学べるのではないだろうか? この東部時代の体験から学んだことが、その後、「人生において、あらゆる経験が無駄ではない」という僕の人生観へつながってゆく。
雪解けの街で緑が芽生え、コートを脱ぎ捨てた人々の表情も浮かれる頃、ニューイングランドに美しい春の訪れだ。久しく季節の移ろいを忘れていた僕は、春を迎えた心身の開放感を堪能し、四季の変化がもたらす喜びを満喫した。そして季節は変わり、J・F・K・ジュニアの魂が眠るマーサズ・ビンヤード島へガールフレンドとフェリーで行った時の海、透きとおるような夏の海はあくまで青く、どのような名画にも勝る色彩が僕の胸を打つ。
9月の勤労感謝の日(レイバー・デイ)は、大勢の友人とコネチカットの海岸へドライブし、どこで誰と寝たのか判らないほどビールを飲んで騒いだり、そろそろ学業より「アメリカ生活」を楽しむほうが忙しくなってきた。というより、じっさいは逆で、法律に対する興味が薄れていたのだ。日本から西海岸を目指し、今度は西海岸から東海岸を目指すと、まったく異なる文化や人間と触れるうち、もっと違う文化を見たいという探求心が生まれ、その欲望は人を感動させる映画作りよりも大きなスケールで僕の心を占めつつあったのかもしれない。
昔のアメリカ人は東部を拠点に西部を開拓していった。西を目指す当時のスローガンを東へ置き換えると、ちょうどその頃の僕の心境とピッタリ合いそうだ・・・・・・
「ゴー・イースト・ヤングマン!」
そして、僕は大西洋を越え、さらに東へ向かうのである。