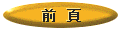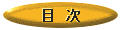夢のカリフォルニア
夢のカリフォルニア
僕が初めてアメリカ本土を訪れたのは、1971年8月22日のことであった。機内アナウンスがロサンゼルス上空へ差しかかったと告げ、窓から下を見れば、そこにはだだっ広い街並が広がっている。その広々としたどこまでも平らな街並を見ながら、いよいよ「約束の地」へ着いたという実感が湧くと同時、ある種の不安感の伴う感動で胸はいっぱいだ。腕時計を現地時間に合わせる僕の心で、その得もいわれぬ感動がじわじわと広がってゆく感覚は未だ忘れられない。
いま思えば、歴史が感じられるほど時代は違っていた。まだ成田空港の「な」の字もなく、僕が出発したのは当時日本の空の玄関である羽田国際空港だ。また、羽田を出発間際、円をドルと両替した時も「1ドル=360円」の固定相場制であり、レートを気にする発想すらない。機内を見渡すと、その頃から乗客の多くは日本人であったが、どの表情も深刻で現在のような気安さは窺(うかが)えなかったような記憶がある。
1972年夏−若き日のマックス(中央) |
|---|
日本での初対面以来、久し振りで顔を合わすアーウィンだが、僕の描いていたイメージとまったく変わらない。しかし、出会いの衝撃(インパクト)は次元が違う。当時を振り返ると、ぼやけた記憶の中で色あせず残っているシーンはいくつか浮かぶが、空港ロビーで見た彼の笑顔もその一つだ。そして、空港からスタジオ・シティーのアーウィン宅へ向かう車中、燦々と降り注ぐ南カリフォルニアの太陽はやけに眩しく、それから30年近く経った今も僕の心で輝き続けている。
太陽の眩しさを感じながら、日本だと大使館でしか見かけないような大型車(セダン)の中でアーウィンとの会話が弾む・・・・・・そもそも文通を始めるきっかけとなったのは、数年前マイクが初めて日本を訪れ、わが家から近い代々木のオリンピック村で滞在したことであった。ここは、もともと終戦以来アメリカ軍の駐屯地となっている渋谷のワシントン・ハイツという広大な敷地へ、東京オリンピックの選手村を建てた際、そのまま外国人旅行者の宿泊施設として解放したものである。まだ小学生の僕は、各国のオリンピック選手からサインをもらいたくて通い始めたわけだ。
メイン・ビル前の広場に大勢いる外国人の群、その中で優しく微笑みながら周りの人たちと語り合うマイクの姿へ、なぜか僕は目が止まった。まるで磁石に吸い付けられる鉄のごとく、人混みをかきわけ、彼めがけて突き進む。初対面のマイクは僕が見上げるほど長身の、好奇心でいっぱいのティーンエージャーだ。日本の文化、歴史へ興味を持つ彼は、見知らぬ外国人の僕をまるで長年の友人のごとく接してくれる。片言の英語しか喋れない僕と、お互いの趣味などを語りつつ、「運命の出会い」は舞台を広場からロビーへ移す。
当時、強さが売り物のプロレスは今のようなショーアップしたものとは違っており、中でもロサンゼルス、ミネアポリス、セントルイス、ニューヨークといった大都市のプロレスが僕を夢中にさせた。これまたプロレス大好き人間とわかったマイクへ、僕は知っているレスラーの名前を連発しながら話は弾む。WWA、AWA、NWA、WWFといった団体が群雄割拠するプロレス戦国時代の状況を、現地ファンから聞く興奮度たるや、洋書店で入手するプロレス雑誌のそれとは比べものにならない。
日系二世のミスター・モト、キンジ渋谷などの活躍、日本でも人気のあった「吸血鬼」フレッド・ブラッシーなどの話題に固唾を呑む僕へ、マイクはプロレスばかりか、フットボールやバスケットボール、アイスホッケーや野球などが雑居するスポーツ天国ぶりを熱弁する。言葉と環境の違いを越えて接点を見つけた我々は、この日を境にお互い人生の伴侶となるなど、誰が想像できようか!
マイクともう一つの接点である映画を語る前に、まず母のことを述べたい。外交官を父として鎌倉で育った母は、女学校時代からの洋画好きで、当時の大スター、グレース・ケリーやオードリー・ヘップバーンなどに憧れ、学校をさぼっては映画館へ足を運んだという。結婚後もその癖が抜けない母は、まだ小学校の僕を頻繁に映画館へ連れ出した。母が若かりし頃魅了された映画のリバイバル公開ということで、ある日僕が見に行ったのは“エデンの東”だ。微妙なストーリーなど理解できぬ子供の僕も、想像を絶する70ミリ大型スクリーンの迫力や胸を打つ音楽、そして言葉や文化を超越して伝わってくる若きジェームス・ディーンの強烈な存在感で圧倒され、母の手を握りながら映画館を出る時、なぜか涙が止まらなかったのを憶えている。
「大人になったら映画の仕事、それもあの表現しがたい感動を与えてくれたハリウッドで仕事をしたい」と思うようになったのは、この頃だったと思う。アラン・ラッドの後ろ姿へ母と涙した西部劇のクラシック“シェーン"、銀幕(スクリーン)に広がる広大なテキサスの平原でディーンとリズ・テイラーが繰り広げるロマンス“ジャイアント”など、いつしか母好みの名作によって、幼い僕の心へ「映画との絆」は着実に芽生えてゆく。
いっぽう、両親とも映画俳優という環境で生まれ育ったマイクの場合、妹二人と弟が全員モデル兼子役の仕事をしていた。舞台好きの父親は、なかなかいい役柄に恵まれないなど、ユーモアたっぷりで語った彼が、その時ポツリと言った。
「僕は将来、映画を作りたいと思ってるんだ」
プロレスの話題で始まった運命的な出会いを感じ始めていた僕の耳へ、その一言が与えたインパクトは周りが真っ白になるほどと言っても大袈裟ではない。数年来、ハリウッド映画への想いが募っていた僕にとって衝撃的なマイクの言葉は、パートナーとして彼と映画を製作する今も脳裏から離れず、その後、ヨーロッパの映画祭などへ旅する二人のアルバムを飾る第一頁なのだ。
この「一期一会」がきっかけとなり文通を始めた僕とマイクは、彼がカリフォルニアからプロレス雑誌、僕が東京から日本製(メード・イン・ジャパン)グッズを送り合う仲となって交友を深め、僕をアメリカへ旅立たせる起爆剤になったと言えよう。まだ未成年の僕の身元引受人となるよう、両親を説得してくれたのも他ならぬマイクだった。
日本が本格的な高度成長時代を迎えるきっかけとなった東京オリンピック開催から七年余りを経た留学当時は、日本人留学生はおろか、東洋人さえ珍しい時代である。人種偏見の強いテキサス出身で、自らヨーロッパ戦線へ赴(おもむ)いたマイクの父親ビル、元映画女優で同じ俳優仲間のビルと演劇学校で知り合った母親フラニー、彼らがそんな時代に共稼ぎの家庭で見ず知らずの日本人少年を養うことは決して楽じゃない。今でこそポピュラーなホームステイだが、当時はさぞや決断に迷ったはずだ。今は亡きフラニー、80代を迎えた今も現役で俳優家業を続けるビル、僕が彼らへ抱く感謝と尊敬の念は、日本の両親へのそれに勝るとも劣らないだろう・・・・・・
そして、いざアメリカ生活が始まると、何を見ても何を聞いても物珍しい。ハイスクールへ編入した当初、しばらくは授業に追いつくのが精一杯で、それどころではなかったが、いったん自分のペースをつかむと心の余裕は戻ってくる。若さとは素晴らしいものだと思う。その若いエネルギーで、日本文化特有の「人前で恥をかくこと」や「知らないことを知らないと認めること」などのタブーを、いとも簡単に「恥をかく勇気」や「知らないと認める勇気」へと変えてくれるのだ。
時としてホームシックにかかりながら「アメリカン・ドリーム」へ第一歩を踏みだしたある日、ふと耳に止まったのがFMラジオから流れるママス&パパスのヒット曲“夢のカリフォルニア”である。その響きは日本から馴染んでいた曲とは思えぬほど新鮮で、まだ頼りない息子を送り出してくれた両親、兄のいない寂しさをこらえて暮らす妹たち、家族一団となって僕のドリームを支えてくれるアーウィン一家への僕の想いを乗せて、澄み渡ったカリフォルニアの空にいつまでも響きわたっていた。