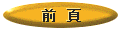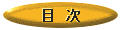カンヌの長い夜 (下)
カンヌの長い夜 (下)
カジノの興奮が冷めやらぬまま外に出た僕は、葉巻と香水で麻痺した体を屈伸させながら、すがすがしい空気を胸いっぱい吸い込む。そこへ、顔を真っ赤にしたジェフとその一行が浮かない顔で出てくる。チラッと腕時計を見ると、早くも午前3時半だ。さあ、そろそろお開きかなと思った矢先、機嫌を取り直したジェフが例の電子手帳を取り出し、
「よ〜し、気分転換に刺激の強い所へ行くぞ!」と意味ありげに叫ぶや、カジノの前で待機中のタクシーを呼びつける。
先に乗り込んだジェフは運転手へたどたどしいフランス語で行き先を告げ、全員が乗ったところで来た時の道とは違うルートを走り出す。真っ暗で曲がりくねった道路を走るタクシーの窓から、闇の中で広がる地中海を見ると、遥か彼方の海岸線が建ち並ぶ豪華ホテルの明かりでうっすらと浮かんで見える。なだらかな丘を登ったり降りたりするタクシーに身を任せてウトウトし始めた頃、めざす大邸宅へ到着だ。ジェフの説明では、ある大富豪の住まいらしい。観葉樹が生い茂る玄関は、まるでジャングルのようで、中へ入るとライブバンドの音楽が聞こえてくる。その音を頼りに大きな螺旋階段を登ってゆく。2階の大広間では高価なスーツを着たヨーロッパ風の紳士たちと混じり、サングラスとゴールド・チェインをまとった一目で映画関係者とわかる「ハリウッド・タイプ」の男達が、シャンパン・グラスを持って屯(たむろ)している。
その空間の広さと調度品の豪華さにしばし見惚れながら気づいたのは、カクテルを運んだりゲストを接待する数十人の女性が、どれも目を見張るの美女ぞろいなのだ。広間のところどころへ置かれたイタリア製の高級ソファーや、オリンピック・サイズのプールを中心に広がる広大なテラスのベンチで、ゲストと話す彼女たちの服装はまちまちである。ミニスカート、ロングドレス、目の置き場に困る大胆なカットのドレスを着た者もいるが、日焼けした見事な小麦色の肌という点では全員共通している。
現地のコンパニオンを接待係として呼んだのかな、などと考えながら、ムンムンする熱気の中をテラスへ向かう途中、すれ違った美女が、
「何か飲む?」と、ジョージアあたりらしき南部訛りの英語で聞く。明け方にカクテルという気分じゃないので、ペリエのライム入りを頼んでテラスに出ると、冷たい夜の空気が快い。眼下のフレンチ・リビエラは月明かりでほんのり照らし出され、その夜景を満喫しつつ深呼吸をしていると、さっきの美女がドリンクを持って現われる。いろいろと話すうち、彼女たちは“ハワイアン・トロピック”という有名な日焼けオイル会社のキャンペーン・ガールだとわかった。商品の宣伝や会社イメージアップのため世界中を回っているらしい。また、コンテストを通じて全米各地から選ばれた彼女たちのほとんどが、体力トレーニングやエチケット訓練などで自分自身を磨きながら、将来のスーパー・モデルや女優への道を夢見ていることも教えてくれる。
 名前をテリーという彼女は南部アトランタ出身の大学3年生で、若い頃のジャクリーヌ・ビセットを彷彿させる顔立ちだ。一見派手で華やかな彼女たちも、ホームシックや家族の反対、そして宣伝する商品の関係上、どうしても水着姿が多いことからボーイフレンドとの口論など、裏では人知れず悩んでいると言う。時おり酒臭い息で寄ってくるプロデューサー・タイプの自慢話へも耳を傾けながら、テリーと話し込むこと約1時間。将来の夢で一杯の若いエネルギーに感動していると、誰かがトントンと肩を叩く。振り返った僕へ、
名前をテリーという彼女は南部アトランタ出身の大学3年生で、若い頃のジャクリーヌ・ビセットを彷彿させる顔立ちだ。一見派手で華やかな彼女たちも、ホームシックや家族の反対、そして宣伝する商品の関係上、どうしても水着姿が多いことからボーイフレンドとの口論など、裏では人知れず悩んでいると言う。時おり酒臭い息で寄ってくるプロデューサー・タイプの自慢話へも耳を傾けながら、テリーと話し込むこと約1時間。将来の夢で一杯の若いエネルギーに感動していると、誰かがトントンと肩を叩く。振り返った僕へ、
「そろそろ行こうか?」と、ニンマリ微笑(ほほえ)むジェフ。目で合図を送り、彼は無言のうちに遠去かる。向き直ると、テラスのバルコニーへ寄り添うように夜景を眺めるテリーの横顔が美しい。僕の視線を感じたのか、こっちを向いた彼女へ、
「僕の知らない世界の話をありがとう。もっともっと見聞を広め、楽しい人生を送ってね!」と、別れを告げる。3日後にはモンテカルロへ移動するという彼女がニッコリ笑い、
「マックス、知ってる? このパーティーで私の電話番号を聞かなかったのはあなただけなのよ・・・・・・」これが誉め言葉なのか嫌味なのかわからないまま、唇に残る「サザン・ベル(南部美人)」のキスの温もりを感じつつ、僕は豪邸(マンション)を出る。玄関先でみんなと合流した後、ようやくホテルへ向かう。帰途、テリーのことを冷やかされながらも、気だるさと時差ボケが相まって思考能力はほとんど機能せず、痺れきった脳裏を彼女の横顔が掠(かす)めては消えてゆく。ホテルの前でタクシーを降りるまでの約20分間、なんとも妙な気分であった。
宿泊先のホテル・カールトンに着いたのが午前5時過ぎ、寝息を立てているジェフは起こさず、いったん自室へ戻りかけたものの、8時にエージェントと朝食を兼ねたミーティングの予定があり、寝る気はしない。そこで、ボーッとした頭を醒ますためにも、海岸通りへ散歩に出る。あと数時間で、大きなバッグを背った配給会社のバイヤーやベルサーチのプリント・シャツで決めた映画プロデューサーが縦横無尽に徘徊する目抜き通りも、この時間はひっそり静まり返っている。頭の中でさまざまな想いが交差しつつ、夜明け前の通りを歩く。
と、僕の視界へ飛び込んだのは、なにやら怪しげな4〜5人の東洋人が前方の角を曲がろうとする光景だ。人一倍好奇心の旺盛な僕は、歩調を早めて彼らの後を追う。全員が黒装束で長髪にサングラス、1人は楽器のケースらしき物を抱え、別の1人はベレー帽をかぶっている。人目をはばかりながら辺りを詮索するような態度へ、ますます興味が湧く。街灯の薄明かりで照らし出された古い石畳の裏道と、くわえ煙草で話し込む神妙な面もちの男たち・・・・・・どことなくフィルム・ノワールの世界に通じる異様な雰囲気だ。
そして、海岸沿の表通りへ引き返す彼らの後を尾(つ)け始めた僕は、路地からプーンと漂ってきたコーヒー豆を轢く強烈な香りで立ち止まる。ふだん、ほとんどコーヒーを飲まない僕が、なぜかその朝は尾行も忘れるほど欲しくなり、蔦(アイビー)の絡まる小さなカフェーへ飛び込む。入れたてのモロッコ・コーヒーを飲みながら、ふと目を上げれば、路地の向こうの地中海は、いつの間にやら朝日が昇り、海岸通りをジョギングする人の姿さえチラホラ見える。
モロッコ・コーヒーを味わいつつ、頭は中では再び取り留めもない想いが駆けてゆく。つい今しがたの不思議な東洋人グループ、夜通し楽しんだパーティー、カジノでの体験、テリーと束の間の触れあいなど、昨夜からのさまざまな出来事を回想するうち、昼間は喧騒でかき消されて聞こえなかった鐘の音が僕の耳元へ届き、いったん思考を中断する。耳を澄ますと鐘は七つ鳴り、つまり小一時間も物思いに耽ったわけだ。ゆっくり考える時間が持てたことを感謝しながらカフェーを出た僕は、ブレックファスト・ミーティングの支度をするためホテルを目指す。
シャワーを浴びた後、カジュアルな格好でロビーへ降りると、スザンヌが昨晩は早く寝て時差ボケが回復したのか、すがすがしい顔で待っている。朝食の相手は僕たちがプリ・セール(映画の製作予算を捻出するため製作前の企画段階で配給権を前売りする方式)を任せた海外配給会社の社長テッドで、宿泊先はカンヌの目抜き通りから海岸線をタクシーで15分ぐらい南下した岬のデゥ・キャップという超一流ホテルだ。玄関先の南仏情緒あふれるフラワー・ガーデンは数百年の歴史を誇り、ヨーロッパ調のアンティーク家具が目を楽しませてくれる豪華なロビーは時間を忘れそうで、映画祭の多忙さが嘘のような別世界である。
 待ち合わせの場所は、岬の突端を削って造られた大理石のプール脇を抜けたところにあるレストランで、行ってみると、まず巨大な氷の彫刻が目を引く。白鳥をかたどった彫刻のまわりへセンスよく並ぶ珍味の数々も印象的ながら、もっと驚いたのはガーデン・スタイルのテーブルで食事中の客に映画界のスーパースターが多いこと。僕たちの案内された隣のテーブルでは、“ショーシャンクの空に”のティム・ロビンスとミラマックス・スタジオのハービー・ワインスタイン社長がフルーツ・サラダをつついており、それを横目にさっそくビュッフェ・テーブルへ足を運ぶと、長いテーブルの向こうの端ではクリント・イーストウッドがスモーク・サーモンを数切れ皿に取っている。ベランダではラリー・ゴードン("ダイ・ハード”シリーズのプロデューサー)が暖かい朝の日差しを浴びながら葉巻をくゆらし、そんな穏やかなムードの中で始めた朝食会議も順調に進んでゆく。
待ち合わせの場所は、岬の突端を削って造られた大理石のプール脇を抜けたところにあるレストランで、行ってみると、まず巨大な氷の彫刻が目を引く。白鳥をかたどった彫刻のまわりへセンスよく並ぶ珍味の数々も印象的ながら、もっと驚いたのはガーデン・スタイルのテーブルで食事中の客に映画界のスーパースターが多いこと。僕たちの案内された隣のテーブルでは、“ショーシャンクの空に”のティム・ロビンスとミラマックス・スタジオのハービー・ワインスタイン社長がフルーツ・サラダをつついており、それを横目にさっそくビュッフェ・テーブルへ足を運ぶと、長いテーブルの向こうの端ではクリント・イーストウッドがスモーク・サーモンを数切れ皿に取っている。ベランダではラリー・ゴードン("ダイ・ハード”シリーズのプロデューサー)が暖かい朝の日差しを浴びながら葉巻をくゆらし、そんな穏やかなムードの中で始めた朝食会議も順調に進んでゆく。
デザートのフルーツ・タルトと紅茶を楽しんだ後、テッドは映画祭会場へ向かい、午後2時まで予定がない僕とスーザンはプールサイドで一休みすることにした。正午前だというのに思ったより日差しが強く、僕たちは大きなクリーム色のパラソルの日陰で落着いた。快いラウンジ・チェアーから、巨大なプールの水が外側のガターへ滝のごとく落ちる光景や、プールと地中海がつながって見える目の錯覚に酔いしれながら、この平和でリッチな一時の安息を満喫していると、
「今度はウェスタンを撮りたいもんだ。ブラッド・ピットかウッディー・ハレルソンが主演だな」誰かが2段プールの下で叫んでいる。どうやら、“アポロ13”や“バックドラフト”のパワー・プロデューサー、ブライアン・グレーザーらしい。その声を聞いたのが最後で、いつしか意識は遠のき、スザンフが起こしてくれるまでの2時間、僕は安らかな寝りを堪能した。
そしてホテルへの帰途、タクシーの中で聞いたラジオ・ニュースが、今朝がたの疑問を解決してくれたのは予想外のハプニングだ。例の不思議な東洋人グループの正体が判明したのである。スザンヌの通訳で知ったニュースの内容とは、今日の昼頃、日本人ミュージシャン内田裕也、宇崎竜童とその一行が、クワゼ大通りで許可なく演奏パフォーマンスを敢行し、カンヌ警察に逮捕されたというもので、ニュース・キャスターは彼らのことを「日本の神風バンド」と呼んでいた。なるほど、僕が今朝がた尾行した時、彼らは今日のパフォーマンスの下見をしていたわけか!
数日後、彼らが製作した“ダイオキシン”という映画の試写会へ招かれ、例の黒ずくめの服装とサングラスに身を固めた彼らと会い、映画の内容はさっぱり理解できなかったが、なんとかして話題を作ろうとするエネルギーは今でもはっきりと印象が残っている。ともあれ、ニュースの内容を聞いた僕は、タクシーの窓越しに昨夜と違う明るい表情の地中海を眺めつつ、警察と揉み合う裕也さんたちの姿を想像したり、一晩で垣間見たいろいろなドラマを思い起こすたび笑いがこみ上げ、スザンヌの心配そうな視線は感じながらも止まらない。僕が初めて訪れ、ミステリーあり、ロマンあり、刺激たっぷりで、二度と体験できない「カンヌの長い夜」は、こうして終わりを告げようとしていた。