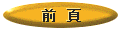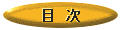創作の泉
創作の泉
高校生の時、アメリカへ移住して以来、ずっと思い続けてきたことの一つは、アメリカの文化および国民性が、いかに独創性を育(はぐく)むかというテーマである。僕のハイスクール時代といえば、まだ今のようなギャング、ドラッグ、ティーン妊娠といった社会問題こそ起きていなかったものの、そのジェネレーションなりの葛藤は多々あった。
コンピュータ時代の今でこそもてはやされる「ナード(ガリ勉)」や「ギーク(お宅)」タイプだが、当時は皆からのけ者にされ、スポーツ選手やチアー・リーダーたちばかりがもてた時代だ。そんな風潮の中、自動車のメカに凝る者もいれば、煙草を吸ってドライブイン劇場でナンパに励む輩(やから)と、千差万別の若者像を見ながら僕は自分なりの個性を見つけようと苦労していた。教師や親たちが、他の皆と同じ行動を奨励したり、個性の強い者を叱ったりした記憶はいっさいない。むしろ、個性的な面を伸ばすことへ焦点を当て、たとえ成績が良くなくてもスポーツに秀でるとか、スポーツは駄目でも別の才能を活かすことにエネルギーが注がれていたと思う。
反面、日本での子供時代を振り返ると、とにかく「出る杭は打たれる」式で社会全体が画一性を強調し、独創性や強い個性は「世間の調和を乱す害」とさえ見なされた傾向がある。学生は制服を着用し、髪の色が同じところへ長さも同じ、目指す社会像はほとんど変わらず、集団でいると心強いが個人だと自分の意見も述べられないという環境では、やはり個々のオリジナリティーを発揮することが難しくなるのかもしれない。
国際的にも統計的にも、日本人は「コピーや改良が得意で、オリジナルを創るのは苦手」というレッテルを貼られている。それが美徳として奨励された文化の賜といえばそれまでながら、ハリウッド映画界という「独創性の坩堝(るつぼ)」みたいな世界で動く僕は、見ていて非情に歯がゆい。東京へ行くたび感じるのは、茶色く染めた髪、アムラー現象、男のイヤリングなど、皆がしているから、しないと流行に乗り遅れるという理由ではなく、「自分がしたいから」それをする若者は、いったいどれだけいるのだろうか? 独創性という側面から見ると、流行っていなくても自分の好きなことやるほうが遥かに素晴らしい。独創性を育てる第一歩は、トレンド雑誌やマスコミの仕掛けた流行に振り回されず、世間から白い目で見られようと、ともかく自分なりの自己主張をする若者が増えることだ。
その点、アメリカは60歳の暴走族もいれば、真っ赤な靴を履くお婆ちゃんもいる。また、それをとやかく言う風潮もない。そして、好きなこと、得意なことを伸ばそうとする体質の根底が、「人に迷惑をかけなければ何をしてもOK」という無言のルールだ。こうした状況の違いを比較してみると、いい悪いは別として、それがそのままハリウッドと日本映画界の相違であるような気はしなくもない。
アメリカの大学で映画学科を卒業後、僕の製作会社や他社(よそ)でしばらくアシスタントをして帰国した日本の若者から、よく手紙を貰う。監督などの創造的な仕事を目指した彼らが書く内容には、多かれ少なかれ年功序列や封建的なシステムへの不満が含まれている。その壁を打ち破れな当人の責任はさておき、会社社会と同じく「年期が入っていない」、「若いから」、「その地位で生意気な」といった、その人の持つ才能やアイデアとは本質的に関係ないことで判断するシステムが、彼らの不満の大きな原因だ。日本で想像力や個性を伸ばしにくいのは、「グループ・ダイナミックス」のマイナス面といえよう。
日本を離れてみると、住んでいた頃は見えなかった良い面や悪い面がよくわかる。個人主義の国アメリカではめったに経験しない「気配り」、「心使い」という素晴らしい要素、外国の料理や自動車、家電機器などの技術を取り入れ、世界一に改良してしまう才能、そういった長所へアメリカ的な独創性が加わると、はじめて日本の「個性」を海外で発揮できそうだ。映画という創造的な分野にも世界で通用する人材が出てくるに違いない。未だ、年老いたら日本の片田舎で暮らしたいと願う僕は、決して日本の悪口を言うつもりもなく、海外居住者として日本で見えない落とし穴や、日本の限りない可能性みたいなことを書き、それが国内で住む人たちへ少しでも役立てば本望なのである。
 さて、ハリウッドで8本の映画を製作するうち、いろんなタイプの監督とその独創性に触れてきた。それぞれの個性やスタイルは、今も僕の脳裏へ鮮明に焼き付いている。とくに個性が強かったのは、最初の作品“ナイト・ウォリアー”を監督したポーランド出身のラファエル・ザリンスキー。なんと19歳で名門MIT(マサチューセッツ工科大学)を卒業した秀才で、僕が初めてのプロデュースということもあったせいか、なにしろ自分のクリエイティビティーを表現することしかなく、製作予算とか撮影スケジュールという数字はいっさいお構いなしのタイプなのだ。
さて、ハリウッドで8本の映画を製作するうち、いろんなタイプの監督とその独創性に触れてきた。それぞれの個性やスタイルは、今も僕の脳裏へ鮮明に焼き付いている。とくに個性が強かったのは、最初の作品“ナイト・ウォリアー”を監督したポーランド出身のラファエル・ザリンスキー。なんと19歳で名門MIT(マサチューセッツ工科大学)を卒業した秀才で、僕が初めてのプロデュースということもあったせいか、なにしろ自分のクリエイティビティーを表現することしかなく、製作予算とか撮影スケジュールという数字はいっさいお構いなしのタイプなのだ。
時間的な制約でカバレッジ(同じ場面を違うカメラ位置からの撮影)が少なくなると感情的になったり、俳優の演出よりもセット背景を重視したり、いわゆる芸術家肌の典型であった。妥協を許さぬ彼は、1日の撮影時間が延々20時間という場合もあり、テイクの数などまさしくプロデューサー泣かせといえよう。撮影終了後の編集たるや、細部へ神経を配りすぎて、見かねた僕はとうとう彼を編集室から閉め出す始末!・・・・・・だが、痩せる思いで完成してみると、前編流れるような仕上がりで、事業としても成功し、配給会社は大喜びと、ハッピーエンドで幕を閉じた。いろんな意味で印象が深いラファエロは、現在、スタジオ作品の監督として活躍中だ。時たま、その撮影現場を訪れると、あいかわらずプロデューサーが頭の毛を引き抜くような監督ぶりに、僕は内心、ほくそ笑んでいる。
一方、監督の中にはラファエルと対照的な、何でも僕の言うなりで優等生みたいなタイプもいた。また、予算などの数字をリクエストすれば、ことごとく了承し、妥協案を打ち出して実行するのが上手いタイプや、意気消沈してしぶしぶ仕事を進めるタイプと、それぞれの監督ぶりへ人柄を窺(うかが)える。そして、監督という仕事は独創性を表現する技術だけでなく、100人以上のスタッフとの協調性、第一助監督や現場監督的な存在であるライン・プロデューサーとの調和など、多面的な才能が問われるだけに、「アンダー・ザ・プレッシャー」でどこまで手腕を発揮できるかは重要な決め手だ。一見、プロデューサーの言いなりでおとなしいマイケル・クーシュ("ワイルドハート")が、ある寒い早朝ロケで、スタッフを統率できない助監督を大声で怒鳴った時、僕は彼を見直し、トラブルを心配するよりむしろ安心した。やはり、生意気なぐらい自己主張の強い監督のほうが、作品への拘りも強く俳優の演技指導にも力が入るので、僕は好きだ。
“オルテリア・モーティブス”の脚本と監督を担当したジェームス・ベケットも、まるで大学教授のような風体でハーバード出身の元弁護士という変わり種だった。彼の物静かな態度は、トラブルの巣窟のごとき撮影現場へそよ風のような雰囲気を醸(かも)しだし、どんなピンチも「必ず解決出来る」という自信に満ちあふれていた。政治的スリラーという作品の性格上、緊迫したシーンが多く、緊張している俳優の肩へ手をかけ、セットの端で何やら懇談中のジェームス、その優しい横顔は、いま思い出すと懐かしい。毎日、撮影が終わると彼のトレーラーで行った会議の時は、それだけ柔和な彼が真っ赤な顔で自己主張をする。自分で良しとしない場合は決して妥協することがない。その時と場所で独創性と協調性を自在に操る彼の器量は、プロデューサーばかりか人間として学ぶところが多かった。そんなジェームスの慌てる姿を初めて見たのは、僕の結婚式・・・・・・式の終わりで花嫁が花束(ブーケ)を後ろ向きに投げ、そこへ並ぶ独身女性たちはそれを奪い合う。取った者が次に結婚するといわれるこの儀式で、花束(ブーケ)はジェームスのガールフレンドの物となり、彼女がそれを渡した一瞬、彼の青ざめた表情だけは一生忘れないと思う。
 クインテン・タランチーノもそうだが、ハリウッドで意外と多いタイプは、子供がそのまま大人になってしまったパターン。人間いくつになっても少年のような感動、好奇心、喜びを忘れてはいけないと日頃から感じる僕は、このエレメントこそ独創性と創造性を表現するため不可欠の要素だと信じている。「年相応の態度」とか「大人げない」とかいう観念を捨てて初めて個性が活きるのであって、やはり社会のルールへしがみつく者にハッとするような独創性を期待するだけ無駄ではないだろうか?
クインテン・タランチーノもそうだが、ハリウッドで意外と多いタイプは、子供がそのまま大人になってしまったパターン。人間いくつになっても少年のような感動、好奇心、喜びを忘れてはいけないと日頃から感じる僕は、このエレメントこそ独創性と創造性を表現するため不可欠の要素だと信じている。「年相応の態度」とか「大人げない」とかいう観念を捨てて初めて個性が活きるのであって、やはり社会のルールへしがみつく者にハッとするような独創性を期待するだけ無駄ではないだろうか?
僕がスタジオ作品として最初に作った“スペース・エイド”で抜擢した監督のグレグ・ビーマンは、製作予算2,000万ドルが当時の大型映画クラスであろうと、ワーザーブラザース期待のSF企画であろうと、プレッシャーなどどこ吹く風、監督候補インタビューの際、この映画について彼のあまりの熱狂的なスピーチは、こちらのほうが腹を抱えて大笑いさせられたほどだ。その少年のような情熱、新しいこと試みへの飽くなき好奇心、彼独自の観点から誰の前でも意見を言う勇気、これらのエネルギーは大人になる仮定で「悩み」、「憂い」、「悔やみ」といった現実的かつマイナスの観念と置き換わりがちだが、彼の態度は「楽しみ」、「喜び」、「希望」など、プラスの意志そのものであった。
グレグの「明陽素楽」さのおかげで、4ケ月という長丁場の撮影は、まるで文化祭のごとき雰囲気のまま終わり、その間、彼が連日のハプニングやトラブルを処理する態度に、スタッフは全員、心が洗われる思いをしている。「猜疑心」とか「恐怖心」で対処する大人の世界でなく、彼は誰と対する場合も「信用」と「自信」が溢れた子供の世界を失わなかった。
もちろん、いい監督ばかりとは限らず、二度と仕事をしたくないストレス過剰の監督もいれば、何事も人と相談しなければ判断できない頼りない監督などもいたが、いま言えることは、自己主張をしながらプロデューサーである僕との信頼関係を上手く築こうとする監督ほど、結果としていい作品が仕上げったことだ。わがままを通す頑固さで個性を主張するより、ここだけは譲れないという一線を引いた上で、状況へ合わせる柔軟性があれば、より強く個性を主張できるのだと思う。
トレンドの「フォロワー」ではなく「セッター」、つまり流行を追うより自分で作ったほうが面白い。他人(ひと)と違っても、自分の信じることは勇気を持ってやれる人、これすなわちオリジナルなのである。体制側から批判されながら長髪をトレンディーにしたビートルズから、中傷されながらも自分のトレンドを築いたマドンナ、そして「勝つために来た」という生意気な台詞を吐きながら、そうは感じさせないヒップな個性のタイガー・ウッズ・・・・・・誰であれ、自分自身の人生を歩もうとする者が持つオリジナイティーは永遠に不滅だ。映画という限られた場面だけでなく、いつも個性的で創造力に富み、独創的な生き様が他人(ひと)へ何かを与えられる存在、そんな「そよ風のような」人間になりたいと努力しつつ、僕は日々、個性と創造力をしっかりアピールできる日本の若者が増えてくれることを祈っている。