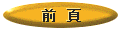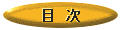ベニスの商人(下)
ベニスの商人(下)
リド島に着いてみると、そこはもう映画祭一色だ。水上タクシーの乗り場から映画祭の会場まで軒並み映画のビルボードが立ち並び、ヨーロッパらしく、アメリカでは見かけない映画も多い。イタリア語やフランス語の映画ポスターを脇目で見ながら、会場脇のプレス・クラブ で待ち合わせたフランス人プロデューサー、ジャック・レノー氏を探す。行き交うヨーロッパ美女たちへ、つい目線を奪われていると、それをたしなめるかのごとくザックの奇声が聞こえ、視線を向ける。走り寄る彼とガッチリと抱き合っているのは、想像以上に痩せた品の良いロマンス・グレーのレノー氏だった。
ベニスは常連という彼の案内でプレス・クラブへ入り、世界中の芸能記者がたむろするカフェーや、実行委員会の事務所にあるスケジュールなどを見せてもらい、映画祭の入場パスを受け取ると、いよいよ会場へ足を運ぶ。パスの発券を待つ間、手振りを交えて話す例のイタリア独特の会話風景で混雑する事務所を出た僕は、おもてのテラスで目前に広がる燦々と輝くアドリア海を見つめながら、それまで一映画ファンとして知り得なかった映画作りの舞台裏へ入り込んだような気がして興奮した記憶だけは、今もクッキリ脳裏に焼きついている。
会場へ入ると、同じイタリアでもミラノ映画祭のような商業的な雰囲気が鳴りを潜め、場内は参加作品に対する畏敬の念といった古典ムードが漂う。レノー氏の先導のもと、紹介されるまま次々と名刺を渡し、挨拶を交わしてゆく。会場がイベント・ホールなのでホテル会場のようなプライバシーはないが、各ブースごとの小綺麗な飾り付けは配給会社の作品への入れ込み様を感じさせるようで印象的だ。アメリカ生活が長く、久しくヨーロッパ映画と触れ合わなかった僕は、純愛や小さな出来事がテーマの「ユーロ・ムービー」にかえって刺激される。また、母国語のフランス語はもとより、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、英語と、完璧でなくとも数カ国語を自由に操り人脈を広げるレノー氏へ、自分自身バイリンガルなどと満足せず、もっともっとグローバルな人間に成長しなければと痛感した。
2階の大部屋で陣取るイタリア最大の配給会社RAIを訪れると、美味(うま)そうにシガーを燻(くゆ)らす紳士がいる。レノー氏の紹介で握手を交わしたその人物こそ、MGMスタジオの買収へ乗り出したヨーロッパ映画界のパワー・ヒッター、チャッキー・ゴーリー氏だ。RAIの社長でもあるゴーリー氏は、机の上からマホガニー製の葉巻ケースを取り、勧めてくれたハバナ・シガーの芳ばしい香りが鼻をつく。葉巻愛好家へ仲間入りしたばかりの僕は、涎を垂らさんばかりで、ありがたく手を伸ばす。
もっとも、僕がありがたかったのは葉巻よりアーノルド・シュワルツェネッガーやメル・ギブソンとシガー友達だというゴーリー氏の話で、我々が企画する映画より数段違うレベルのキャストや予算で勝負する氏は、いろいろと興味深いエピソードを聞かせてくれた。直接事業へ繋がらない出会いであったが、ハリウッドでも業界紙でしか馴染みのない大物プレイヤーと懇談できたことは貴重な経験である。彼にしても、シリアスなハリウッド映画重役とタイプが違うエネルギッシュな若手プロデューサーとの交わりを楽しんでいるようだった。おかげで、それ以来、どんな重要人物であろうが、「誰でも僕と同じ普通の人」という意識で接することを学んだ。
 ゴーリー氏の話へ耳を傾けるうち、僕の腹時計はそろそろ正午を指し始める。と、レノー氏のそばでおとなしくしていたザックが「ランチでもどう?」と切り出す
ゴーリー氏の話へ耳を傾けるうち、僕の腹時計はそろそろ正午を指し始める。と、レノー氏のそばでおとなしくしていたザックが「ランチでもどう?」と切り出す このベニスをきっかけに、ザックとはいろいろな土地を旅するのだが、彼の場合、「食事」と「ナイトライフ」なら、まず任せておけば心配ない カジノでも有名なリド島は、ベニスと違って車も走っているが、気のせいか大半は年代物なのだ。そんなのんびりとした大通りを横切り、我々が入ったのは海辺のバロック風レストランテである。
案の定、映画関係者が溢れる店内は、ランチからワインやマティーニが当たり前のイタリアらしく、大声で話す客のほとんどは赤ら顔で禁煙など何処吹く風だ。もうオーブンの中のごとく煙が充満した店内で待つこと15分、さすがレノー氏のクラウト(コネ)で窓際のテーブルへ案内され、彼が携帯電話で呼び出したフランス系カナダ人プロデューサーも合流して待望のランチ・タイムとあいなった。
フランス料理はもとよりコンチネンタルまで幅広いメニューを見ながら、チーズ・バーガーとフレンチ・フライなどとアメリカ人根性を発揮する相棒(パートナー)のマイクを説得、チキンの胸肉へほうれん草を詰めたものと、北イタリア風ラザニアを注文して2人で分ける。一緒に飲んだ赤ワインと、料理で使う白ワインが効いて、その日の午後は意識が朦朧(もうろう)としていた。ともあれ、食後を終わりかけた時、ふと気づいてみると、舌づつみを打つ僕の横で、マイクは何やら神妙な様子なのだ。向こう側のテーブルをじっと睨む彼の視線を辿(たど)ってみると・・・・・・上品なスーツを纏(まと)った紳士がチーズバーガーを賞味しており、胸のナプキンといい丁寧なフォークとナイフの使い方といい、教科書どおりのマナーである。
自分はバーガーを食べ損なった恨みも手伝ってか、忌々しそうな目つきで見つめるマイクの視線がわかっているのかいないのか、その紳士は小さく切ったバーガーを、これまた小さく開けた口許(くちもと)へ運んでゆく。「ハンバーガーの本当の食べ方を教えてやる!」と言って立ち上がりかけたマイクを制止しながら笑いころげる僕に、レノー氏が皮肉たっぷりに言う。「間違いなく、イギリス人だな!」と・・・・・・
レノー氏と友人のカナダ人(といってもフランス語圏ケベック州出身)は、その紳士をいい魚に英国人とその威張った態度をこけ降ろしはじめ、世界の動きから取り残される「大英帝国の陰」みたいな話題となってしまう。国力が衰えたとはいえ、年々ハリウッドへ力作を送り込んでくるイギリス映画界。そして、ハリウッドで主役を張る実力あるイギリス人スター。そんなブリティッシュ・パワーに同じヨーロッパ陣営として妬(ねた)みを抱いているかのような過激なコメントを聞いて、むしろ「食べたいように食べればいいさ」と僕は思った。
風習の違いや言葉の違いを通じて、改めて世界の広さ、素晴らしさを痛感しているところへ、またまた感性の個人差といったものを考えさせられる出来事(ハプニング)が起こる。それは、映画祭3日目のグランプリ試写会でのことだ。レノー氏が推薦する候補作の1つに上がっていたドイツ人監督ワーナー・ハーゾッグの“スクリーム・オブ・ストーン”を見たマイクと僕は、ロッククライミングという地味なテーマと動きのないストーリー展開、ドナルド・サザーランド("評決のとき")以外、全員が無名のイタリア人俳優ということもあって、すっかり期待は裏切られた。映画の途中で飽きてしまうほどの愚作なのである。
ところが、映画終了と同時、一部の観客は感激のあまり招待席にいるハーゾッグ監督のところへ殺到、彼を肩車に乗せて気勢をあげるほどの興奮ぶりなのだ。その有様を見て、彼らがどこへそんな素晴らしさを感じたのか疑わずにいられない。後日、共同製作の打ち合わせをしている時も、レノー氏から映画の感想を聞かれ、本音を言えずにごまかしたことは、未だ苦い思いとして残っている。結局、感性というものが生まれ育った環境や個人的な生活の結晶であり、人は素晴らしいと思っても自分がそう感じるとは限らないのが当然だという、いい教訓になった。
ヨーロッパ、カナダとの映画共同製作事業を軌道に乗せる当初の目的は上手くいき、リド島の映画祭会場とベニスを往復する合間を縫って名ガイド、ザックの案内で国際的に有名なベネチアン・グラスの発祥地ムラノ島を訪れたり、かのグーゲンハイム美術館で名画を鑑賞したりして過ごす。ベニスの街を散歩すると、ロサンゼルスで言えばガソリン・スタンドくらいの頻度で教会があるのに驚かされる。それだけ、中世の世界は教会が中心だった名残であろう。ただ、シェークスピアの描いた商業都市ベニスとそこで徘徊する精悍なユダヤ商人はもういない。古びた桟橋につながれているペンキの禿げたゴンドラと、映画祭へ来たついでに観光スポットを訪れる現代人のノスタルジアがあるだけだ。
今でも、たまにヨーロッパ映画を見ると、あの穏やかなベニスの日々が蘇ってくる。リド島へ走る水上タクシーで頬を撫でた快い風とザックの笑い声。サンマルコ広場に群がる鳩と正午を知らせる鐘の音。そして、ホテルのレストランから運河越しに見た巨大な教会・・・・・・どれも僕のプロデューサーとしての初期を思い起こさせてくれる素晴らしい「心のアルバム」となった。挫折した時や思い通りことが運ばない時などは、ホテル近くのひと気のない暗い広場で深夜マイクと語り合った将来への夢を思い出し、初心に帰って溌剌(はつらつ)と人生を送ってゆきたいと願う僕である。