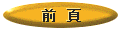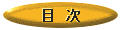キャスティング・カウチ(下)
キャスティング・カウチ(下)
俳優とは見上げた職業だとつくずく思うのだが、オーディションのつど、その役柄に合わせた服装や髪型でキャスティングへと赴(おもむ)く。自分のエージェントから得たわずかな情報を頼り、自分なりの役作りをして夢を託す。自ら俳優の立場でオーディション・テーブルに座った経験があるだけ、今は製作側として対面する俳優たちの心中が、僕へは察して余りある世界なのだ。
その日、サンタモニカにあるコディアック・フィルム本社内のキャスティング・オフィスでは、いろいろな人の思惑が犇(ひし)めき合うセッションの途中であった。僕の処女作“ナイト・ウォリアー”が、主人公はホームレスやギャング・メンバーの寂しい表情をカメラに収める趣味があるハーレー(バイク)好きの青年で、母親と経営するダンス・クラブ運営のため、やむなく得意の空手を駆使してアンダーグラウンド・ファイトで金を稼ぐストーリーの手前、あまり上品な人間は登場しない。その日のキャスティングも、ファイト賭博を牛耳る悪役が抱えるファイター役数人と、主演ロレンゾ・ラマスの恋人役がメインである。
まず登場したブランスキャムは、奇しくも数年後、ロレンゾ主演の人気TVシリーズ“レネゲード”で相棒役を務めることになるハワイアンの俳優だ。肩まで垂れた黒い長髪をかき分けながら、120キロ前後とおぼしき巨体を縦横に動かす演技は迫力がある反面、顔は優しく今いち威圧感がない。キャスティング・ディレクターの用意したリーダー(読み手)相手に指定された場面を演じ、ひととおり終わるとプロデューサー数人は合図をしたごとく顔を見合わせ、
“Nice work!”の決まり文句だ。僕の経験上、この時点で役が取れたかどうか俳優たちは直感で知る。本当に使いたい俳優を見つけた時や、思ってもいなかった役作りを見せられて興奮した時など、まずプロデューサーの笑顔が違う。僕はどちらかといえばお世辞が下手なプロデューサーだ。しかし、俳優時代に出会った中で、君の演技こそ最高だと思わせる人もいた。断られる俳優サイド側からすれば思わせぶりな態度は迷惑なようだが、「たまたま、その役のイメージと合わなかっただけで、個人的な好き嫌いは関係ない」のである。このアクターの鉄則が身につくまでは、オーディションで落ちるたび惨めな想いをする覚悟が必要なのだ。
相手役の台詞を読んでくれるリーダーの腕は、キャスティング・オフィスでまちまちだが、中にはキャスティング・ディレクター自身がリーダーを務める場合もある。どんなタイプの人とでもシーンを演じられる柔軟性や、相手はトチろうが慌てない余裕を持ち合わせる俳優ほど、当然ながら好感度は高い。僕がいつもリクエストするのは、今いち売れない現役俳優をリーダーに使う。というのも、役に成りきれる彼らだからこそ、オーディションを受ける俳優がやりやすいよう、また本領を発揮できるよう、上手くし向けてくれる。
話を戻し、コディアック・フィルム社のオーディションは数人目を迎えながら、監督を含めたわれわれ製作側のイメージと合う者が現われず、そろそろ苛立ち始めた。そこへ、キャスティング・アシスタントに紹介されて入って来たのは1人の中国系男優だ。シルクのような艶やかな黒髪をオールバックで決め、大きなジム・バッグを抱えた黒いジャージー姿の男がにっこり笑う。その優しいスマイルは、悪人面ばかり見てきたわれわれに異様かつ新鮮なインパクトを与えた。
それが、いざ演技となるや顔は引き締まり、相手のリーダーが圧倒されるほどの熱気で押しまくる。クライマックス・シーンの一騎打ちで敵対する重要な役柄だけ、何か主役のロレンゾと正反対のものを求めていた僕は、彼の静かなる闘志がすっかり気に入った。外見で見栄えのするタイプより、むしろ存在感は強い。彼がオフィスを去ると、われわれは顔を見合わせ、誰ともなく相づちを打っていた。名前がジェームス・ルー、スタントマンから出発し、今では準主役級のアクション俳優だ。思い返せば、「感動」という言葉どおり、彼の「気」がわれわれプロデューサーを「感じさせて動かした」のであろう。
“ナイト・ウォリアー”のキャスティングは、テーブルのこちら側へ座るのが初めてだったせいか、他の作品よりも印象は強い。その後7本を製作しながら1,000人以上の俳優を吟味させて頂いた。やはり、最終的に決めた俳優や、それがきっかけとなり別の作品へ出てもらった俳優は、最初から感じさせるものがある。「僕を使わなかったら、あなた方の損ですよ」みたいな雰囲気を持っているのだ。奢(おご)った態度とは別物の、自信で裏付けられたカリスマ性のような掴み所がない感覚ながら、選択側へ与えるインパクトは「これが駄目なら路頭に迷う」という切羽詰まったエネルギーと雲泥の差で強い。キャスティング・テーブルの両側を経験した僕は、それが痛いほど判る。デスパレーション(必死さ)を嫌う傾向のハリウッドでは、「ケ・セラ・セラ(なるようになる)」ムードのほうが大成できるのかもしれない。
 女優のキャスティング風景は、またひと味違う。男優と違って“色気”という強い味方(?)を引き連れた彼女たちは、よほど清純な役どころでないかぎり、セックスアピールのある服装でやって来る。一目で整形と判るぐらい豊満なバストラインを強調したブルーネット(黒髪)、動いたらビリッと破れそうでハラハラさせるほどタイトなワンピースの金髪、“氷の微笑”の有名なシーンを彷彿させる超ミニからスラリと伸びた脚線美を巧みに組んで座る赤毛と、まさしくプロデューサー冥利に尽きる情景ではある。
女優のキャスティング風景は、またひと味違う。男優と違って“色気”という強い味方(?)を引き連れた彼女たちは、よほど清純な役どころでないかぎり、セックスアピールのある服装でやって来る。一目で整形と判るぐらい豊満なバストラインを強調したブルーネット(黒髪)、動いたらビリッと破れそうでハラハラさせるほどタイトなワンピースの金髪、“氷の微笑”の有名なシーンを彷彿させる超ミニからスラリと伸びた脚線美を巧みに組んで座る赤毛と、まさしくプロデューサー冥利に尽きる情景ではある。
香水風呂を浴びて来たと思わせるような強烈な匂いで我々の目を眩ます女優もいるが、いくらプロデューサーの多くは男性といえど、やはり第一印象が大事だ。場数を踏んだおかげで、今では真っ赤な口紅やセクシーな微笑みの下に潜む演技力や存在感へ焦点を合わせる余裕が出てきた僕も、最初の頃のキャスティング・セッションでは“上辺の妖艶さ”に翻弄されることが多々あった。
ワーナーブラザーズ作品“スペース・エイド”は製作予算が1991年当時としては桁外れの2,200万ドルをかけたSF大作で、大物のエージェントからも打診が続き、我々の期待は日に日に膨らんだ。“スティング”でアカデミー賞を受賞し、“未知との遭遇”などをプロデュースするマイケル・フィリップスが共同製作とくれば、低予算映画2本の製作経験しかない僕のような若造へも、いろいろな面で注目は集まってくる。
ロサンゼルス紙が「日本人プロデューサー、ハリウッドで活躍」と大々的な見出しの記事を掲載したり、業界紙デイリー・バラエティーからインタビューを受けたり、僕は夢の実現で有頂天になっていた。そんなある日、オフィスのボイス・メール(留守電)へ知らない女性からのメッセージが残されており、内容は「製作中の作品の件で、絶対に会っていただかなくてはならない話がある」と、まるでE・S・ガードナー("ペリー・メイスン")かレイモンド・チャンドラー("フィリップ・マーロウ")小説の出だしそこのけだ。
折り返し電話をかけると、相手はこれまで聞いたことがないぐらいセクシーな声のメラニーという女性である。どこで聞きつけたのか、あれやこれやと“スペース・エイド”の質問をするばかりか、当然のごとく面会を迫ってくる。好奇心旺盛な僕は、数日後にオフィスで会う約束をし、もしかしたらこれが例の「フレンジ・ベネフィット(役得)」かなと密かな期待を抱く。
数日後、オフィスへ現れたメラニーは声に劣らず超セクシー美人、ピッタリとしたノースリーブでオレンジ色のサマー・ドレスがその脚線と見事なヒップラインを強調している。初対面とは思えぬほど情熱的な抱擁(ハグ)の後、流れるようなウェーブの長い金髪を首の横へまとめながら席についた彼女は、透き通るヘイゼル(緑)の瞳で僕を見つめ、
「新聞で見るよりハンサムね!」と切り出す。大学時代から結構アメリカの女性に好かれる自負がある僕も、爽やかなシャンプーの香りとしなやかな肢体、そして意識的にそり出した見事なバスト・ラインに、もう貧血を起こしそうなのを堪えるので必死だ。
キャスティング・カウチならぬ、わがオフィスのバイオレット色の応接用長椅子(カウチ)へ妖艶に身を崩しながら、じっと見つめる美女の意図は話をちゃんと聞くまでもなく判った。いま大きな事務所から引き抜かれる寸前であり、この作品で自分ピッタリのセクシーな宇宙人役に抜擢されれば、念願だったスターへの道が開けるという打ち明け話を、薄いチェリー色のルージュが目に痛いほど色っぽい半開きの唇で囁く彼女。身を乗りだしてウットリ耳を傾けるうち、僕はハッと気がついた。その役はワーナーからの注文で、当時売り出し中の今を時めくスーパー・モデル、キャシー・アイランドが既に決定しており、われわれ内部関係者以外はまだ誰も知らない。数日後、形式だけのオーディションが持たれるはずだったのである。
この瞬間、「悪魔と取引」のチャンス到来と気づいた僕は、理性が支配する上半身と動物的な欲望が蠢(うごめ)く下半身との激しい葛藤の中、「据え膳食わぬは男の恥」などという日本の諺が脳裏を掠(かす)めてゆく。内情を隠したまま「ベストを尽くすよ」とお茶を濁し、目くるめく一夜を過ごして平然とするベテラン・プロデューサーもいるだろう。しかし、光り輝く彼女の肢体の底で切ない「必死の想い」を見た僕は、ひとときの快楽のため人を欺くことは出来なかった。どうしても役得と割り切ることが出来なかった。
おそらく僕は涎(よだれ)を垂らしそうな表情だったに違いない。そんな自分を叱咤激励しながら、ビバリーヒルズの高層ビルへ忍び寄る夕闇の中、コンピュータのスクリーンがメラニーを妖しく照らしだす。脳裏へは薄明かりに悶える彼女の一糸纏わぬ姿が浮かぶのを打ち消し、鳥肌が立つほどに身を寄せてくる彼女へ「キャスティングで会おう」と言って別れたものの、帰宅の車中、楽しみにしていたご馳走をパッと取り上げられたような未練がましい気分を打ち消せなかったのは事実だ。
当然ながら役を射止めることが出来なかったメラニーも、正直に対処した僕へは好感を抱いてくれて、それ以来、時おり会う良きフレンドとなった。そして、何より中堅女優として活躍中なのが嬉しい。人間、生きていると、世俗的な欲望に駆られて「自分の値打ち(セルフ・エスティーム)」を下げるような選択はあって当たり前。そうしそうな自分に気づいた時、一瞬の「勇気ある選択(チョイス)」が出来てこそ、生き生きとした生涯へ結びつくのだと思う。また、「男の真の器量」はどこでどう試されるか判らないところに、人生の醍醐味があるのだとも思う今日この頃である。
キャスティングという媒体を通じて営まれる人との出会いのドラマ、未来のスターを夢見る俳優たちの不屈の精神を陰ながら応援すると同時、映画作りの創造的なプロセスから生まれる数々の“罠”へ陥らず、思いやりのある選択(チョイス)をし続けたいと願う。これからも新しい映画を作るたび、キャスティング・カウチを横目で見てはメラニーと過ごした夕暮れ時を思い浮かべるに違いない。それが僕の原体験なのだから・・・・・・
なお、今回の写真はテーマと直接関係ないことを最後にお断りしておく。だが、長椅子(カウチ)でポーズを取るマリリン・モンローを見れば、彼女はキャスティング・カウチにまつわる、どのような想い出があるのか、男たるもの、やはり興味を引かれずにはいられない!?