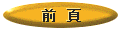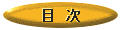チームワーク
チームワーク
西洋風に言うと“チームワーク"、東洋的な表現では「一致団結」と称される漠然としたこの言葉が、エンターテイメント、中でもスポーツと映画製作の分野ほど大きな意味合いを持つ業界も少ないだろう。ゴルフなどの個人スポーツを除いて、複数プレーヤーの競技なら必ずチームワークの善し悪しで結果は左右されるし、プリマドンナが独り舞台のチームへ一致団結のエネルギーを感じるケースは希だ。また、いろいろな才能や技術の集積である映画の場合、100人を越す人々のエネルギーが解け合ってこそ素晴らしい作品となり、スタッフを「物」のように扱う独裁プロデューサーの下で、決して傑作は生まれないと思う。
その好例がバスケットボールであり、スター・プレーヤーの犇(ひし)めくNBA(全米バスケットボール協会)でさえ、12人の要員中7〜8人といわれる主力選手全員の総力を結集して試合の出来るチームは数えるほどしかないのである。L・Aレイカーズの本拠地“フォーラム”だとジャック・ニコルソンやチャーリー・シーン、またニューヨーク・ニックスのホームコート“MSG(マジソン・スクウェア・ガーデン)”だとスパイク・リーやビリー・クリスタル("ファーザーズ・デイ)などのショービズ常連が詰めかけるほど、ハリウッドと密接な関係のNBA。今回は、これら2つのエンターテイメント業界を見比べながら、ハリウッドにおける“チームワーク”の神秘を探ってみたい。
強豪ジョージタウン大出身で昨年の新人王に輝いた若手プレイメーカー、アレン・アイバーソンが抜群のシュート力とアクロバチックな運動神経を兼ね備えながらチームメートの評判は悪く、率いるフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズといえば、リーグのお荷物チームだ。個人プレイへ専念するあまり、チームメートにパスしたり仲間を盛り立てようとしないアイバーソンは、ある意味で未だストリート・ボールの域を脱しきれない二流スターといえよう。そして、シアトル・スーパーソニックスのエースでありながら、
「このメンバーでは、いくら俺が頑張っても優勝は無理だ」
と言い放ち、クリーブランド・キャバリアーズへ移籍したものの、相変わらずマイクならぬ「ボール離さず症候群」で独り寂しくダンクを連発するショーン・ケンプなど、ハリウッド映画界にもよくいるワンマン・タイプの典型である。
「花形志向」のキャストがいたり、手柄を独り占めしようと躍起になるスタッフのいる映画セットも同じく、どことなく雰囲気は閑散として、それぞれが違うゴールへ向かい空回りをしているような印象さえ与えるものだ。狭い舞台に立ちたがる人間は、数が多ければ多いほど人間関係は軋(きし)んだり嫉妬がらみの問題が起こりやすく、この点はNBAの世界とまったく変わらない。
引退したスーパースター、マジック・ジョンソン(L・Aレイカーズ)やラリー・バード(ボストン・セルティックス)がレジェンド(伝説の選手)と呼ばれるゆえんは、彼等個人の能力もさることながら、プレイ仲間の力を最大に引き出す特異な才能があるからだ。マジックは19歳のルーキー時代、風邪で倒れた当時のレイカーズのエース、ジャバーの代役でセンターとして決勝戦へ先発、42点のスコアでチームを王座に導き強心臓ぶりを見せた。一方のバードも、映画“ハード・プレイ”の原題が“White Men Can't Jump”であったごとく、白人のジャンプ力の弱さをカバーして余る超人的コート・センスで、名門セルティックスを何度も優勝へと導いている。毎試合で高得点をマークする力を持ちながら、“パス”という日陰の技をメインに押し出した2人は、“ノールック・パス(逆方向を向いたパス)”や“ラップ・アラウンド・パス(背後からのパス)”などをヒップにした立役者であり、チーム全体のレベルを高める魔力があった。
友人の招きで“身代金”のセットを訪れたおり、そこで見かけた名監督ロン・ハワード("アポロ13")は、セットで働く誰からの提案も熱心に聞き入り、自分のアドバイスでスタッフが手柄を立てた時は「他人を舞台へ立たせて自分は観客席で拍手をする側に回り、人が脚光を浴びて喜ぶことを自身の喜びとする」器の大きな人物だった。ともすれば自分のエゴを通すことしか眼中にない職人肌のディレクターたちや、そういう威圧的な雰囲気の中で自分の才能を発揮できないスタッフ連中、そういう環境で仕事をしてきた僕へ、ロンとの出会いは「自分の才能を誇示する必要のなくなった時こそ本物である」という武道の教えを再確認させてくれる珠玉の瞬間だったのである。そして、マジックやバードのごとく囲り全員のパフォーマンスをレベルアップする不思議な力、誰もが彼のためなら精一杯尽くそうと意欲を燃やす魔力を感じた「奇蹟の日」だ。
バスケットの“パス”は、英語で言う“デリゲート"、つまり「任せる」という意味があり、映画界にも生きている。また、日々の生き様へ現われることだと思う。何でも自分でしなくては気が済まない人、人に任せてみるものの、心配で結局は自分が仕切る人、任せた人を100パーセント信頼し、その人の失敗さえ許す包容力のある人、人間タイプは様々だ。バスケットであろうが映画であろうが、その人の生き方、そして性格はプレイや指揮の仕方に反映するから面白い。
仲間がオープンにも拘わらず、ダブル・チーム(2人の敵が防御する状態)で無理なシュートをして失敗するアイバーソンや、せっかく絶妙のパスをしながら、タイミングが合わず得点できないチームメートを叱咤するケンプの一方では、電光石火の完璧なノールック・パスを決めた後、簡単な得点チャンスをものに出来ず肩を落とした仲間へ、「マイ・フォルト(パスが悪かった自分の責任)」と自分の胸を指差す励ましのゼスチャーがトレードマークのマジックとバード。NBAゲームはまさしく映画セットの縮図であり、また映画のセットはNBAゲームの延長だ。いつもチームメートの「プラス面」へ焦点を当てるマジックやバード率いるチームが'80年代に君臨したのも、あるいは子役で名を馳せ、ジョージ・ルーカス監督の名作“アメリカン・グラフィティ”や人気TVシリーズ“ハッピー・デイズ”での主演経験さえあるロン・ハワードが「アシスト」上手な監督として数々の傑作を生み出すのも、集約すれば鍵は「チームワーク」にあるような気がする。
 100人以上の大所帯である映画製作スタッフは、数ケ月間、連日顔をつき合わせて暮らすだけ、自己主張の強いアメリカ人にとっては、まるでサーカスへ入団したようなものだ。1つのプロダクションが終われば次のプロダクションへと移ってゆく、いわば流浪の集団だから、当然、小競り合いや口論、果ては殴り合いの喧嘩なども生じる。日本の団魂社会と異なり、1人1人がまるで違う発想をし、またその風潮を奨励する文化背景に魅力を感じるアメリカという国では、千差万別の意見や見解を、どう巧くセットへ反映させて団結を計るのかがプロデューサー・チームの腕の見せどころ。
100人以上の大所帯である映画製作スタッフは、数ケ月間、連日顔をつき合わせて暮らすだけ、自己主張の強いアメリカ人にとっては、まるでサーカスへ入団したようなものだ。1つのプロダクションが終われば次のプロダクションへと移ってゆく、いわば流浪の集団だから、当然、小競り合いや口論、果ては殴り合いの喧嘩なども生じる。日本の団魂社会と異なり、1人1人がまるで違う発想をし、またその風潮を奨励する文化背景に魅力を感じるアメリカという国では、千差万別の意見や見解を、どう巧くセットへ反映させて団結を計るのかがプロデューサー・チームの腕の見せどころ。
ワードローブ(衣装部門)とSFX(特撮部門)の予算拡張大合戦からはじまり、AD(助監督チーム)と監督のスケジュール調整絡みの押し問答、そして撮影許可や駐車場確保を巡るトランスポート(車両部門)とロケーション部門の食い違いなど、バスケットボール・コート上でセットプレイ(事前の作戦)を敵チームに崩された時とそっくりだ。慌ててパニックするようでは、まず事態の収拾がおぼつかない。瞬時に豹変する“映画製作”という動物を手なずけるのは、“手持ちの札”でどこまで勝負できるかというゲーム同様、臨機応変な対処いかんで、アイバーソンとなるかマジックとなるかが決まってしまう。
今は故郷インディアナ州の地元チーム、ペーサーズの監督であるバードがまだ現役の選手時代、「最大のピンチには最大のチャンスが潜んでいる」という名言を吐いた。映画作りも人生も、まったくそのとおりだと思う。どのような状況へ置かれても、そのピンチをどうチャンスに活かせるかを考え、“チームワーク”というミラクル・パワーさえ味方につけておけば、10の力は12となり、1人なら思いもつかない突破口が開けたりするから不思議なものだ。
テニスのダブルスやビーチ・バレー、運動会の二人三脚といった娯楽スポーツは勿論のこと、仕事上のパートナーシップ、あるいは「夫婦」や「家族」など身近な人間関係でも、チームワークが原動力の鍵となる人生ゲーム。どれだけ愛し合って結ばれた関係であろうと、「1+1=3」の関係を目指し、知り合った当初のトキメキをお互いに維持する努力を怠れば、いつしか「1+1=1.5」の人生となってしまうのは自然の成り行きである。パートナーの素晴らしい部分へ焦点を当て、我慢ができない部分は見て見ぬふりをする思いやりに、奇蹟の芽が育(はぐく)まれるのではないだろうか?
能力が自分より劣るチームメートへ自信を抱かせ、“パス”というお膳立てで相手を引き立てたからこそ、“チームワーク”の持つ個人技では出せない力を発揮できたマジックとバード。そんな彼等のコート哲学が映画作り、しいては生き甲斐のある人生を送るための大きなヒントだという気がする。20代の頃は、せっかく“舞台”に立った仲間を引きずり下ろしてまで、絶えず自分が注目を浴びようとした僕も、最近どうやら観客席へドッシリ腰を下ろし、スポットライトを浴びる仲間に心から拍手を送れる人間となれた。そして、自分自身で気づかぬ能力を引き出してしてくれるような「チームメート」との「チームワーク」を心がけ、「この人のためなら何でもしてあげたい」と思われる大きな器の人間になりたいと願う僕だ!