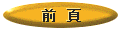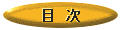ザ・スタントマン
ザ・スタントマン
スタントマンといえば、ハリウッド映画では不可欠な要素の1つだ。無声映画時代から白黒トーキーの初期ハリウッド時代も変わらず、ドタバタ・コメディーでスタントマンが活躍していたことは、バスター・キートンのような自らスタントをこなして名をなした役者を見れば納得できよう。ジョン・ウェインに代表されるウェスタン全盛時代は、喧嘩アクション・シーンのスタントが重要な役割を果たし、ますます存在価値を増す。そして今や、カーチェイス、派手な爆破シーン、高所からのジャンプ、リアルな銃撃戦と、ハリウッド映画は彼ら抜きで製作できないほどの“花形スター”なのである。
莫大な予算を注ぎ込んだスタジオ作品はもとより、僕が作るような独立プロ映画も、ジャンルを問わずスタントマンを必要とする点では変わりがない。ただ、武道やボクシングなどの格闘技に優れたファイト・シーン専門の喧嘩屋から、炎上や爆発シーンで活躍する特殊技術を備えたスタントマン、高層ビルや家の屋根から飛び降りるジャンプ専門家、危険なカー・スタント技術を披露するデアー・デビル(命知らず)まで、そのタイプは様々だ。
ファイト・スタントの場合、カメラ・アングルが鍵となる。それを熟知しているスタントマンほど重宝がられるのはいうまでもなかろう。派手な動きが要求されると同時、あくまで自分の存在を目だたせずに主役を引き立てなくてはならない。10センチ離れた空間をかすめる主役のパンチが、あたかも顔面で炸裂したかのごとく演じるプロの技を、彼らは“売り物”と呼ぶ。カメラの捉(とら)えた映像が、どうすれば大げさでなく真実味(リアリティー)を持つかを把握し、そこで迫真の演技を売る商売なのだ。
また、彼らの“売り物”をどう活かすかはDP(撮影監督)の腕が左右する。飛んでくるキックの真正面にスタントマンを配置し、その後ろへカメラを設置すれば、スタントマンは主役のキックに直撃された場面を“売る”ことが可能であり、その時、主役の背後から別のカメラで狙い、パンチのインパクトとスタントマンのリアクションも撮るDPのワザ次第では、同じスタントの迫力が倍増する。ちなみに、話はそれるが、時おり雇ったスタントマンから聞く情報(ゴシップ)は撮影中の楽しみの1つだ。彼らなりの「評価リスト」みたいなものがあって、アクション・スターの誰々はパンチやキックの「寸止め」が下手で、よくスタントマンへ怪我をさせるとか、某東洋人スターはスタントマンを粗末に扱うとか、貴重な内部事情を聞かせてくれる。
同じスタントでも、火を扱う場合だと、まったく様子が違う。全身を宇宙飛行士の着るような耐火服(ファイヤー・スーツ)で包み、小さな酸素ボンベから呼吸をしながら全身火だるまと化して悶えるスタントは、見ているだけでも怖くなるほどの緊張感を伴うが、当の本人はさして熱さを感じないのか、監督の「カット!」の声と同時にスタント仲間から浴びた消化器の泡で煙が収まるや、涼しい顔で耐火服を脱ぐ。ベテランほど監督やプロデューサーの狙いどおりの場面(え)が撮れたか? また、アクションはあれで良かったか? と、細かい配慮を示す。自分の演技が納得できなくて、1回数百ドルというスタント料を請求できながら、無償でやり直しを申し出たスタントマンさえいた。
ある作品で爆発の犠牲者を演じたスタントマンは、腰にバンジージャンプのロープのようなゴムでつないだパラシュートを巻き付け、「ファイアー・イン・ア・ホール(爆破)!・・・・・・アクション!」のかけ声もろとも爆発の勢いで吹っ飛ぶドアや自動車とタイミングを合わせ、引っ張られたロープの威力で地上何十メートルへ舞い上がる。続いて、今度はクローズアップでと言う監督に、
「先週、高価な54インチのTVを買ったばかりでね。満足いくまで何度でも飛ばされるよ」と、ウィンク。衣装のシャツを着替える時、背中へ生々しいロープの痣(あざ)が刻まれているの見た僕は、飛ばされながら空間で手足をバタバタさせて「恐怖感」と「臨場感」を“売る”彼らの姿に、妙な感動を覚えたものだ。
ジャンプ専門のスタントの場合、主人公の代役(ダブル)で飛び降りるケースが多い。衣装や髪型は主人公と同じで、顔だけ判別しにくいアングルの“売り”である。日頃から「仲間意識(コムラドリー)」が強いスタントマンたちは、危険な飛び降りスタントともなれば、屋外ロケであれスタジオ撮影であれ、全員が着地マットの位置や膨らみ具合、また飛び込み地点の足場など入念なチェックをするのが普通だ。飛び降りる高さと平行して、当然マットの大きさや厚さは増す。いつだったか、着地点を示す眼下のXマークが信じられないほど小さく見える高い屋上へ自ら立ち、僕は初めてスタントマンのプロとしてのワザを実感した。ビルの階数でジャンプ料金が決まるというジョークは、裏返せば飛び降りスタントがそれだけの離れワザだという意味合いを含む。空を舞う一瞬へプロデューサーの想いは凝縮され、次の瞬間、マットに着地したスタントマンと、駆け寄ってヒーローを抱え起こすスタントマン仲間の燃えるような視線。緊張が緩むと同時、静寂を破った大拍手の音は今でも耳元から離れない。
“ライジング・サン”に出た時、僕たちチンピラが乗る'55年型キャデラックの運転主を演じた日系スタントマン、ジェフ今田はハリウッドでも有数のカー・スタントマンだ。あの垂直尾翼(テールフィン)が突き出たキャデラックの長くて重い車体(ボディー)を絶妙のテクニックでスピンさせたり、車幅と同じぐらい狭い路地を全速力で突っ走るなど朝飯前、メキシカン・ギャングに追い駆けられるシーンでは、急ブレーキを踏んで猛進する車の向きを90度回転させて逃走という離れワザが、コフマン監督を唸らせていた。ハラハラさせられ通しの撮影中、こっちは寿命が縮む思いの超過激なチェイス・シーンを薄ら笑いでこなすジェフの横顔へ、僕はハリウッドの裏舞台に現われ、そして消えゆく荒くれスタントマンたちの歴史を垣間見たような気がする。
 いろんなタイプのスタントマンをキャスティングしたり、脚本からスタント予算を組んだり、スタント全般をコントロールするのはスタント・コーディネイターの役目だ。僕が処女作である“ナイト・ウォリアー”以来、何本かでスタント・コーディネイターを頼んだリック・エイボリーは、エルビス・プレスリーの師で知られるエド・パーカーから日本拳法を教わった経歴を活かし、彼自身、長年スタントマンとして活躍する他、売り出し中のアクション・スター、ジェフ・スピークマン("パーフェクト・ウェポン")といえば彼の拳法の弟子である。最近はメジャーのスタジオ作品も手がけ、生々しいファイト・シーンやカメラ・アングルの“売り”へ気を配ると同時、何よりスタントマンの安全第一を考えるリックの姿勢が、初めて一緒に仕事をした時はまだ新米プロデューサーの僕へ、映画作りが人間と人間の“触れ合いのビジネス”だと教えてくれた。
いろんなタイプのスタントマンをキャスティングしたり、脚本からスタント予算を組んだり、スタント全般をコントロールするのはスタント・コーディネイターの役目だ。僕が処女作である“ナイト・ウォリアー”以来、何本かでスタント・コーディネイターを頼んだリック・エイボリーは、エルビス・プレスリーの師で知られるエド・パーカーから日本拳法を教わった経歴を活かし、彼自身、長年スタントマンとして活躍する他、売り出し中のアクション・スター、ジェフ・スピークマン("パーフェクト・ウェポン")といえば彼の拳法の弟子である。最近はメジャーのスタジオ作品も手がけ、生々しいファイト・シーンやカメラ・アングルの“売り”へ気を配ると同時、何よりスタントマンの安全第一を考えるリックの姿勢が、初めて一緒に仕事をした時はまだ新米プロデューサーの僕へ、映画作りが人間と人間の“触れ合いのビジネス”だと教えてくれた。
ちなみに、最初は軽いスタントを予定していた場面が、全体の流れや監督の感性で大々的なスタントへ膨れあがることは、さほど珍しくない。そこまでじゃなくとも、狙う場面を撮り始めて思ったより危険なスタントなら料金が変わってくるだろう。こうした状況で予算を組み直すプロセスを“調整(アジャストメント)”と呼ぶ。中には必要以上の危険なスタントを行い、コーディネイターへ調整(アジャストメント)を要求するスタントマンがいる一方、製作側の立場を考えてくれるリックのように良心的なコーディネイターは、そのようなわがままを許さないばかりか、自分の経験から、もっといいアイデアを提供してくれたりする。多少コストがかかっても、ここ一発のところでスタントマンを増やしたり、もっと派手な落下(フォール)で決めろと、彼の助言に従い迫力は倍増し、助けられた場面が多々あるのだ。
身体を張って盛り上げた映画の完成と同時、たちまち忘れ去られるスタントマンたちの結束は固い。そして、お互いが一致団結して護り合う絆の裏には、人知れぬドラマが隠されている。ブルース・リー直伝「ジークンドー」の達人でもある前述のジェフ今田は、ヒットTVシリーズ“6百万ドルの男”のスタント・コーディネイターとして「ハリウッド・スタントマン・オブ・ザ・イヤー賞」に輝いた実績を持つ。以前、僕の映画へ参加してくれた彼が、昼食を食べながら話してくれたエピソードは、そんな1つ・・・・・・
ブルース・リーの息子、故ブランドン・リーの映画でスタント・コーディネイターを務めるジェフが、ブランドンの遺作“クロウ/飛翔伝説”を撮影中のことだ。彼は次のシーンで悪役の銃弾を浴びるブランドン相手に、コーヒーを飲みながら雑談を交していた。そこへ、「第1ポジション!」のかけ声が響きわたり、ブランドンはマーカー(所定の位置)で立つ。空砲の詰まった拳銃を持つ悪役が5メートル離れて向かい合う。照明やメーキャップは最後の点検を済ませ、耳栓をしたジェフ以下、スタッフ全員が見守る中、
「アクション!」と、監督のひと声は張りつめた空気を破り、銃声が轟(とどろ)くや、腹を押さえて呻き声をあげたブランドンは“迫真の演技”で床に崩れ落ちる。
すべてが、あたかもスローモーションの1駒を見ているようだったというその一瞬、撃鉄ではじき出されたパレットと呼ばれる堅いゴム状の弾(たま)が、実弾と変わらぬ威力でブランドンの腹部を貫通していたなど、いったい誰にわかろう? 「カット!」の声で起きあがろうともしないブランドンへ、また悪ふざけをしていると思い、笑いながら駆け寄ったジェフは、身体から流れ出す大量の血に顔色を失くす。事の重大さを悟ったスタッフが応急処置の後、ほとんど意識のないブランドンを救急車で病院へ担ぎ込んだ数日後、彼は28歳の若さでこの世を去った。
以来、脳裏へ焼き付いたシーンがスローモーションで繰り返され、眠れぬ日々を過ごすばかりか、ブルースの未亡人でブランドンの母親リンダからも起訴されたジェフのショックは大きい。長い年月を経てようやく立ち直れたと語る彼の表情へ、目前で親友を失った者しかわからないような物悲しさと、そばで何もできなかった悔恨の念が浮かぶのを見て、僕は彼が生きてゆく限り心の傷を癒すことはないような気がする。この悲惨な事故の教訓を活かし、今では銃を撃つシーンで小道具係が必ず空の弾装(チェンバー)を撃たれ役へ見せて確認するのは、ジェフの苦悩へせめてもの報いだろう。ひょっとすれば、ブランドンの死が未然の事故を防ぎ、それで命を救われた役者は随分いるのかもしれない。ジェフが話し終え、ふとそう思った時、僕の心は感謝の気持ちと不思議な安らぎで満たされていた。歳月を経て記憶が色褪せようと、その感触はくっきり残りそうだ。
「映画作り」という総合芸術の製作過程で、一瞬のうちにスクリーンから消えてしまうスタントマンたち。プロダクションからプロダクションへと渡り歩き、一匹狼でありながら「仲間意識(コムラドリー)」の強い裏方さんたち。彼等のプロ精神なく迫力あるシーンは生まれない。主役を輝かせ、シーンを盛り立てる影の存在ながら、ちょうど「空気」のように、それがなくては映画という生き物が死んでしまう。あの明るいスタントマンの背中の痣(あざ)やジェフの孤独な瞳は、これからも映画を作るたび、きっと僕の脳裏を掠(かす)めるに違いない。