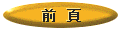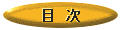オーディションと演技の日々 (下)
オーディションと演技の日々 (下)
約2年振りで再会した僕とジョンは、ペアを組んで台詞の練習を始めた。おかげで、プロデューサーや監督の厳しい眼差しの中、満足のゆく演技を披露できたと思う。親子の役柄だったせいもあり、久しぶりに会って懐かしいところへより親近感が湧いた僕は、オーディションの後ジョンをお茶に誘った。パラマウント・スタジオがあるメルローズ通りは洒落たカフェも多い。その1軒で入口がジャングル風のエキゾチックなカフェに入り、お互いの近況を話すうち、いつしか話題は「ハリウッドの東洋人」へ移ってゆく。
以前からハリウッド映画の東洋人、特に日本人役の言葉使いや衣装考証の怪しさが引っかかっていた僕は、その疑問をぶつけた。すると、それまで黙って僕の話を聞いていたジョンが、
「マックス、ハリウッド・プロデューサーにとって、日本人だろうと中国人だろうと、あるいは台詞が少々おかしくたって、演技さえしっかりしてれば関係ないんだよ」と、物静かな口調で言う。
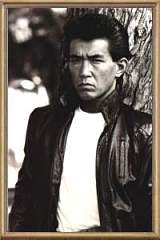 実際、観客の多くは日本語も東洋文化も知らない欧米人だ。我々日本人がイギリス人とドイツ人の区別をつけられないように、白人から見た東洋人はみんな同じ。ましてや、日本人が中国人を演じようと、韓国人が日本人を演じようと、大切なことは「役を売る」才能なのである。外人(日本人)の言葉が正確かどうかは、映画製作全体からすれば取るに足らない。
実際、観客の多くは日本語も東洋文化も知らない欧米人だ。我々日本人がイギリス人とドイツ人の区別をつけられないように、白人から見た東洋人はみんな同じ。ましてや、日本人が中国人を演じようと、韓国人が日本人を演じようと、大切なことは「役を売る」才能なのである。外人(日本人)の言葉が正確かどうかは、映画製作全体からすれば取るに足らない。
以前、寿司マン役でTVコメディーへ出た時、ウェイトレス役の着物姿がおかしかったので、彼女の着付けは間違っていると指摘し、監督の顰蹙(ひんしゅく)をかった。また、同僚の商社マン役を演じる日系俳優の日本語を正し、嫌がられたこともある。ジョンの話を聞くうち、それらのエピソードが脳裏に浮かび、日本人として些細な部分へ拘(こだわ)る自分を認識できたのは、僕にとって大きな収穫だ。
リチャード・ギアがアイルランド人を演じようと、シュワルツェネッガーがロシア人を演じようと違和感はないのと同じく、どんな東洋人の配役であろうが、それを受け入れる器量は“ハリウッド・ゲーム”のルールであると気がつき始めた。拒否している限り、その配役は活かせない。ただ、僕自身、“オルテリア・モーティブス”を製作した時、カメラ・アングルの関係でヤクザの腹に入れ墨を描き、日本人の方々からお叱りを受けた苦い経験がある。要は(配役の)活かし方だろう。
ともあれ、ジョンとの相性(ケミストリー)が良かったせいか、僕達2人はヤクザ親子にキャスティングされ、1週間のハワイ・ロケをエンジョイしながら、より親交を深めた。その後も、数々のオーディションで顔を会わせ、何度か一緒に仕事をしている。ハリウッドで俳優業40年の大ベテラン、ジョンから多くを学んだが、最大の収穫は演技や俳優業とまったくかけ離れた彼の「生き様」だ。
“Go with a flow.(流れのまま)”という姿勢が、オーディションの心構えから撮影現場(セット)での過ごし方、またプロデューサーの意図をどう表現するかといった範囲にまで貫かれ、その心の奥深さは彼の口癖「俳優になれて幸せ」のさり気ない一言へ窺(うかが)える。製作側に立場が変わった今、俳優の頃とはまた違う問題を抱えることも多く、そんな時こそ彼から学んだ「流れのまま」の姿勢が役立つ。もっとも、当時はそれがストレス軽減へ貢献するなど考えもしなかった。
人間、「乗ってる」時は何事も驚くほどスムーズに運ぶ。無駄な労力を費やさず結果が実ることも多々ある。オーディションの「乗り」をつかみだしたのか、以前ほど「拘り」や「余裕のなさ」は薄れ、肩の力を抜いて自分を出すことが出来るようになると、仕事のペースも変わり始めた。「警察もの」のTVシリーズや「中国人マフィアもの」の映画、武道の心得を活かせる「アクションもの」と、順調に入ってくる仕事を次から次へとこなすうち、履歴書(レザメ)は重みを増す。こうした流れの中で弾(はず)みだした「乗り」が僕を新たな体験へと導いてゆく。
スティーブン・セガールのデビュー作“刑事ニコ/法の死角”でベトナム兵を演じた時のことだ。撮影所は当時の僕の住まいから近いバーバンクのワーナー・ブラザーズ・スタジオでもあり、朝7時の集合時間(コールタイム)より少し早くセット入りした。ウォーキートーキーを持ったサードAD(第3撮影助手)が各出演者に提供されるトレーラーの一室へ案内してくれる。あてがわれた3畳ほどの小部屋は蛍光灯が眩しい。エンジンの振動で微かに震える楽屋で落着いた僕は、改めて辺りを見回す。ベッドと机、そして小さなタンスがあるだけだ。机の上へポケットベル、携帯電話、新聞、読みかけの小説などを入れたバックパックを置き、タンスの前に吊された衣装の軍服をチェックしておく。
下見の次は腹ごしらえ、水性マジックで“MAX K.”と書かれたドアの位置を覚え、出前(ケータリング)トラック目指す。早朝といえど、真夏のL・Aはもう暑い。短パンにスニーカー姿のクルーや早くも衣装変えを済ませた俳優達が、トラックの前では列を作っている。そこへ加わって間もなく、先に並んでいた白人俳優が、
「また、ブレックファースト・ブリート(メキシコ風の朝食)だってよ。ランチはもう少しましな食事だといいけどね!」と、声をかけてきた。内心、美味そうなブリートだなと思っていた僕も、黙って相づちを打つ。それがきっかけとなり、お互いの役柄を話すうち、湯気の立つキッチン・トラックへ徐々に近づいてゆく。その後方では、数着の衣装を抱えた数人が輪になっている。彼らは何の役だろう、と興味を引かれた僕の目線を察してか、
「仕事が入ってこなくなったら、俺も彼らみたいなエキストラ稼業の仲間入りさ!」と、説明する白人俳優の口調は皮肉たっぷり。
出番を待つ間、自分の楽屋(トレーラー)がある出演者と違い、“Atmosphere(空気)”と呼ばれるエキストラは「その他大勢」用の一室しか与えられない。わずか1日60ドルのギャラで、使われるかどうかもわからない衣装を持参し、長く退屈な撮影時間、ひたすら出番を待つ。食事の順さえ一番最後と決まっていて、出演者やクルーが全員並び終わった頃、ようやく彼らは列に着く。
偶然、楽屋が隣り合わせだった白人俳優テッドは、食後も相変わらず文句タラタラ。照明が暗いだのトイレが臭いだの、楽屋のドアを閉めるまでブツブツ言っていた。先程のエキストラ軍団に気を引かれた僕は楽屋入口の階段へ腰を下ろし、ブリートにかぶりつく彼らの姿を観察する。人がどうあれ、僕の夢だったハリウッドの撮影風景、それも俳優として参加する喜び、忙しく動き回るクルーの発散するエネルギー、そんな空気で感無量の僕は、つい頬がほころんでしまう。
新聞や読書で待ち時間をつぶすうち、そろそろ昼食時も近づき、コーヒーを飲みたくなった僕は楽屋のドアを開けた。ちょうどそこへサードAD(第3撮影助手)が通りかかったので進行状況を聞く。出番を確かめると、今日はそこまで行かず、明日に持ち越される気配が濃厚だ。慣れるまで、こうした情報に一喜一憂していた僕も、この頃は退屈しないで時間を過ごす“セットの心得”を会得し、「流れるまま」自分のペースを保つ中で、それを楽しんでいた。
昼食の時間がきて、テッドとランチ・テーブルを設置した広場へ向かう途中、彼はいかにも寝起きの顔で悲観的なグチばかりこぼす。そんな白人俳優と広場で別れた後、エキストラたちが集まっている場所に足を運んでみる。僕の気さくな態度で気を許してくれたのか、全員と自己紹介を交す。彼らはほとんど全員が折り畳み式の簡易椅子へ腰かけ、その横に大きなジム・バッグを置くワンパターン、そこからは分厚い本や編み物などが顔を覗(のぞ)かせ、彼らの“セット慣れ”を物語っている。
エキストラ歴20年のローランドは、映画好きの上品な老人だ。家でブラブラするよりセットのほうがいいと語る老人の目はキラキラ光っていた。ローランドと同じぐらいキャリアが長いパットは、「座ってりゃ金になるし、主演スターの近くで写されると出演者へ格上げの可能性もあるからね!」と、現実的な意見と比べ、いまいち意気消沈気味。アラバマ州出身のローラは結婚と同時にL・Aへ引っ越し、主婦をやりながら出来る限りエキストラ稼業を続けたいと話す、食べてばかりいる肥満中年である。そして、演技クラスに通いながら俳優を夢見る若者ロジャーと、同じエキストラでも多彩な顔ぶれなのだ。
彼らと昼食を取るうち、ロジャーが「日系人俳優のケーリー・ヒロユキ・タガワを知ってるかい?」と聞く。そして、かつてはエキストラであったケーリーが“ラスト・エンペラー”で出演者へ格上げされ、以来“007シリーズ”などの悪役スターとして活躍している経緯(いきさつ)を話してくれた。周りでも、昔ケーリーと一緒にエキストラの仕事をしたという者が結構いる。そのケーリーとは後日“ライジング・サン”で共演し、以来親しくつき合う仲だが、かつて彼の武勇伝を熱っぽく語ったロジャーの瞳に「明日は俺の番!」というハリウッド特有の熱気が漲(みなぎ)っていたのは忘れられない。
彼らとの昼食が終わりかけて、その上品な笑顔でローランドは言った。
「この仕事がただでも僕はやるね。憧れのハリウッドで撮影現場にいられるなんて最高じゃないか!」と。人間、誰しも日常生活の中で夢を失しがちだ。昔の感動が忘却の彼方へ置き去りにされると、テッドのような文句タラタラ人生・・・・・・人生の素晴らしさを忘れ、辛い面ばかりへ目をやる人間と出会うたび、あのローランドの心意気を知って欲しいと願う。
彼らと昼食を取って以来、多くの映画に出演しながら、時とすれば“自分の幸運さ”を忘れることもあった。その僕が俳優稼業を続ける中で得たものは、人脈や仕事へつながるコネとかでなく、ハリウッドという小宇宙で生息する様々な生き物を通じて学んだユニークな「生き方」、「流れ方」である。舞台裏を知らなければ、エゴの強い大スターの演技が輝いて見えるだろう。才能のある俳優は他人へ気配りせずに成功するかもしれない。しかし、シェークスピアが言った如く「世界は舞台であり、人間誰もが俳優」であるなら、映画の世界を超越した「人間としての俳優業」を感動的に全(まっと)うできる者こそ、真のスーパースターではないだろうか?
僕の現役時代と比べ、日本のスターがハリウッドへ挑むケースは多くなった。ソニー千葉こと千葉真一、若手の加藤昌也、吉田栄作なども腰を据えてがんばっており、僕が“俳優(アクター)稼業”を通じて素晴らしい宝物を獲たごとく、彼らなりの実りある成果を心から望む。そして、今プロデューサーとして僕を助けてくれる俳優当時の経験や、多くを学ばせてもらった様々な出会い。その「感謝、思いやり、奉仕、親切、明朗、素直」という心を洗い精神を清めてくれる感情を自分の生き様へ反映させていくことこそ、彼らへの恩返しであり、素晴らしい作品を生み出す活力だと信じ、映画作りに勤(いそ)しむ僕なのである。(完)