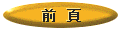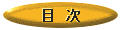|
ハリウッド |
映画産業の中心地であり“華の都(ティンセルタウン)”と呼ばれるハリウッドながら、その黄金時代を築いた人々の名残(レガシー)は意外と人目につかないところでポツリと佇(たたず)んでいる。たとえば、マリリン・モンローの墓はUCLAで有名な学生街ウェストウッドの片隅へ寂しく奉られていたり、ハリウッドから遠く離れた辺鄙(へんぴ)な町にある、かつてハリウッド・スターが挙って押しかけた大富豪の“不夜城”などは、いわばハリウッド史の1頁を飾る隠れた名所といえよう。
この豪邸があるのは、ロックバンド“アメリカ”のヒット曲で一躍有名になった国道101号線“ベンチュラ・ハイウェイ”を、ロサンゼルスから車で3時間ほど北上したあたりだ。海岸線沿のPCH(パシフィック・コースト・ハイウェイ)へ乗り換えて少し行けば、広大な原野が広がるサン・シミオンという田舎町に着く。太平洋の風でそよぐ果てしない草原の向こうは丘陵地帯、いったん道端へ車を停め、なだらかな丘陵に目をやると、頂上でそびえ建つ白亜の城が頭を中世へ翔ばす。
 左に太平洋を眺めながら、“ハースト城”と看板(サイン)のかかった入口を入れば、中は牧場風の観光センターだ。その巨大な駐車場へ車を乗り入れ、そこから歩く。観光ツアー専用のビジター・センターは、各ツアーのスケジュールを表示した入場券売場が何ブースかあり、囲りにはレストランや土産物の売店、そして映画で城の歴史を見せる劇場まで完備している。
左に太平洋を眺めながら、“ハースト城”と看板(サイン)のかかった入口を入れば、中は牧場風の観光センターだ。その巨大な駐車場へ車を乗り入れ、そこから歩く。観光ツアー専用のビジター・センターは、各ツアーのスケジュールを表示した入場券売場が何ブースかあり、囲りにはレストランや土産物の売店、そして映画で城の歴史を見せる劇場まで完備している。
ビジターが自分の好みと時間帯で選択できるよう、キャッスル全域をカバーする初心者向けツアー、ゲスト部屋など特定の建物を見て歩くミニ・ツアー、闇の中へ色とりどりの照明で浮かび上がった城を巡るナイト・ツアーなど、趣向を凝らした各ツアーは一定の間隔でスタート時間が決まっているわけだ。電話の予約を入れおいた僕は、ブースで入場券を受け取り、ヨーロッパやアジア系の観光客で賑わうセンターをブラつきながらバスの発車時間を待つ。
映画のプロデューサーという職業柄もあってか、観光客を横目にこの城の生い立ちを想えば、いろいろ感銘深いものがある。海岸線を望む閑散とした丘陵へ“夢とロマン”を求めて壮大な城を建てる人物、そう、“ハースト城”の名のごとく、サンフランシスコの新聞王ウィリアム・ランドール・ハーストこそ、この城を築き上げた人物であった。
いよいよスタートの時間となり、バスは走り出す。裾野から眺めた時と違って、目の当たりにする城の巨大さが迫力だ。“ハースト城”の歴史を淡々と語るテープの声を聞き流しながら、なだらかな斜面を15分ばかり登ってゆく。母屋(メインハウス)へ着きバスから降りると、ゴシック建築の粋を凝らした建物の壮大なスケールに溜め息が出る。その重みは中世ヨーロッパの教会といえば多少なりともおわかりいただけるかもしれない。そして、囲りの雰囲気で圧倒されながら、約20人のツアー・グループは無言のうち先導のガイド氏へ続く。
僕が初めてここを訪れたのはUCLA在学中だが、当時はビジター・センターの規模もバスのサイズも小さく、数々の装飾品や歴史の重みを感じさせる骨董品へ目を奪われ、創始者ハーストの生涯や彼の夢など、ほとんど考えなかった。以来、友人や恋人、そしてワイフと、僕にとって大切な人達とここで時を過ごすうち、少しずつハーストのロマンの欠片(かけら)みたいなものが見えてくる。それは、何度も足を運んだせいというより、僕なりの人生経験を積む中で物事の本質を探る姿勢(アティテュード)が育(はぐく)まれた結果だと思う。
ハワイの知人を連れ立った今回の訪問では、僕たちを案内してくれたガイド氏がここの歴史やハーストの生き様に人一倍詳しい年配の紳士であったせいか、よりノスタルジックな気分を味わえた。淡々と説明する彼の口調は優しく、あたかも自分の体験談を語るがごとく、建設時の苦労話、あるいは調度品の一つ一つへ秘められた逸話などを聞かせてくれる。耳を傾ける僕の頭で現実が遠去かってゆく。そして、想いは20年の歳月を遡(さかのぼ)ったサン・シミオンへ・・・・・・
無声映画華やかれしハリウッド、かつて父親が細々と経営するサンフランシスコ・エグザミナー紙を若干24歳で引き継いだハーストは、それを全米で有数の購読数を誇る一大新聞社へ育てあげた他、多くの雑誌を成功させていた。その頃、“新聞王”の名を欲しいままにする彼が、もう1人のトレンド・セッターと出会い、その出会いは新しい時代のスタイルを築いてゆく。そして、出会うきっかけとなるのが他ならぬ“ハースト城”なのである。
巨万の富を築き上げ、世界を旅し、グルメにも飽きたハーストは、そろそろ中年へ差しかかる年齢であった。ちょうど、後生に何かを残したいという願望が頭をもたげ始める時期だろう。何かを残したい、人生の証(あかし)となる何かを、そう考えた彼は余生を過ごせる安住の地へ“安住の場”を築く決意を下す。ヨーロッパや南太平洋、そして東海岸など世界各地で住んだハーストが最終的に選ぶ場所は、気候温暖で太平洋を臨み、栄華極めるハリウッドから比較的近いここサン・シミオンなのである。場所が決まって、予算や工事期間に糸目をつけぬ一世一代の建設事業へ着手したハーストは、サンフランシスコ大地震で唯一の生存ビルを設計した女流建築士ジュリア・モーガンに白羽の矢を立てた。
ヨーロッパ王朝時代のアンティックを惜しみなく使った内装、アジアやヨーロッパから集めた由緒ある家具調度品、イタリアから直送した大理石の豪奢な玄関や暖炉、ロサンゼルスで1エーカーの地価が20セントであった当時、エーカー当たり15セントという法外な土地の購入価格、世間の顰蹙をかったのもわからなくはない。しかし、世間の思惑がどうあれ、彼のビジョンは日を追ってエスカレートし、とうとうアフリカから運んだシマウマ、ライオン、ゴリラなどの野生動物を動物園なみの檻や放し飼いにした“地上の楽園”を築いてゆく。
教会風の巨大な母屋、南カリフォルニアの陽光が降り注ぐ“太陽の館”と呼ばれるゲスト・ハウス、離れの“海の館”はすべての部屋から海を眺望できる。また、海の神ネプチューンの名を冠したギリシャ風マンモス屋外プールや、古代ローマの大浴場を模した純金張りの室内プールなど、完成当時、世紀の建築物として脚光を浴びる頃、着工から早10数年の歳月が流れていたのだ。
これだけの城を完成させた以上、それを披露したいハーストの心境は当然だろう。そこへ、恋人をハリウッド女優に仕立てたい私欲が手伝い、彼は有名な映画スターたちへ片っ端から招待状を送る。ただ“Come to my ranch.(私の牧場へおいで下さい)”としか書かれていない招待状を受け取ったスター達が「牧場」の響きにラフな格好で訪れ、まず驚かされるのは所狭しと群をなす放し飼いのシマウマや、お伽話から抜け出たような城のスケールだ。ゲスト・ルームへ案内されるや、仕立て屋が洋服の仮縫いに現れ、間もなく届くワードローブはカジュアルなものからタキシード、水着からパジャマまで揃っていた。これだけあれば、滞在中、何があろうと着る物で困りはしない。ばかりか、帰り際、すべてのワードローブを詰めた高価なスーツケースがお土産に待っているという徹底振りである。
財力を誇示する嫌らしさはなく、ただただゲストへ最高の想いをしてほしいというハーストのささやかな願いがそこにはあった・・・・・・ガイド氏の説明を聞きながら、ふと現実へ戻った僕が見るバラ園では見知らぬ人々がカメラを構えている。シャッター音の充満する空間に、高価なティーカップを持った無声映画時代のスターたちがオーバーラップし、消えてゆく。
ガイド氏はなおも語り続ける。面識のない映画スターや知識人、政治家などのゲストと交流を図るべく努力したハーストの思いやりが窺えるエピソードだ。古今東西を問わず、食事時は人が一番和む。そこへ目をつけ、ハーストは考案した。ゲスト・ハウスにキッチンを設けないというアイデアである。夕食が毎晩9時、朝は天窓から燦々と太陽が降り注ぐブレックファスト・ルームで焼きたてのパン、敷地内の牧場で搾りたてのミルクと新鮮な卵、農場でもぎたてのフルーツをふんだんに盛ってゲストを持てなす。自室で食べられない以上、空腹のゲストは母屋のキッチンへ行く。すると他のゲストと顔を合わせ、スキンシップが生まれるきっかけを増やせるという発想らしい。
夕食の時間を9時と遅くした理由も、そうすれば7時半頃には待ちきれないゲストたちがゾロゾロと母屋へ集まり始め、ワインとチーズで懇談が盛り上がる。その頃合いを見計らい、隣接の豪華なダイニング・ルームへ続く扉を開くという演出だ。100畳はありそうなダイニング・ルーム中央で、ヨーロッパの修道院を思わせる樫の木の食卓(テーブル)が一直線に並ぶ。それを挟んでゲスト達は向かい合う。見かけどおり修道院が使っていた食卓(テーブル)には違いないが、本来は壁際へ置かれ、静かに食事をするためのデザインを、ハーストが上手くアレンジし、彼は席順まで気を配った。面識のない者、ハリウッドでライバル視されるスター同士を向かい合わせ、交流を図ろうとしたそのホストぶりが憎い。
ディズニーランドなどと比べ、展示品を触ったりフラッシュ撮影を禁じたルール違反への監視は厳しいのも、由緒ある品々を保護すべく当然の処置といえよう。うっかり絨毯を踏んだり、プールサイドの大理石に腰を下ろそうものなら、ガイド氏とコンビを組む監視役のおばさんが甲高い警告を発し、ギロっと睨む。学生時代、初めて訪れた時は「小うるさいバカめ!」と無視しながら、いざ自分が一家の主となり「自分の城を大切にする」おばさんの気持ちを知ってからは、「他人の城を尊ぶ」ことを覚えた。成長の喜びを感じつつ、ツアー最期のハイライトであるローマ・プールへと向かう。
ベニスのガラス細工をあしらった底といい、金箔を散りばめた側面といい、凝りに凝ったプールは、ちょうど子供の頃通った代々木のプールを思い出させるオリンピック・サイズだ。夕闇の迫る中で微かな陽光を照り返す水面へ、「強者どもが夢の後」・・・・・・脳裏に浮かぶ一句を噛みしめながら、その昔、ここに集い楽しんだハリウッドの亡霊たちを僕は見た。光と影が触れ合う異次元の世界(トワイライト・ゾーン)を震わす歓声、レトロ調の水着に颯爽(さっそう)と身を包む金髪(ブロンド)たち、葉巻をくゆらしながらそれを見つめるハーストの満足気な笑顔、そんな幻想へ心を奪われた僕を、ツアーの終了を告げるガイド氏の声が呼び覚ます。
3時間のツアーは「たくさんの階段を登るので、軽快な服装と運動靴で」という最初の注意書きどおり、結構上り下りが激しい。ガイド氏の情緒たっぷりな「紙芝居的語り」と、古き良きハリウッドを偲ばせるツアーは、不思議なほど堪能させられる。バスで丘を下りながら見かけた錆び付いた動物の檻、昔シマウマが駆けめぐった海を見下ろす丘陵、かつてハリウッド人の胸を躍らせた宴を催した庭園、過去の映画を偲ばせる“新聞王”ハーストの遺産は、今もなお訪れる人へロマンを与え、その気遣いの余韻を味わいつつ、ほとんど日が暮れたサン・シミオンを後にした。
バックミラーを覗くと、地平線まで一直線を描くPCHから外れた丘の上では、くっきりシルエットを浮かび上がらせた城が別れを告げている。その昔、無声映画でゲストを持てなした映写室で見たハースト家の古ぼけたホーム・ビデオ。白麻のスーツをダンディーに着こなすハーストの印象的な姿。この城の常連であった黄金時代のハリウッド・スターに囲まれた彼の亡霊が、手を振りながら「また、いつか会う日まで!」と、ニッコリ微笑む。いつまでも、いつまでも・・・・・・