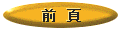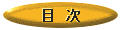ディレクターズ・チェアー
ディレクターズ・チェアー
映画の製作工程で僕たちプロデューサーが最もエネルギーを費やすプロセスの一つは監督の選択だ。作るのが「ドラマ」なら“ストーリー・テリング"、つまり映像を通じて観客へ物語の展開を明快に語れる能力や、人物像を掘り下げて観客の心へ訴えかける“キャラクター・ディベロップメント”の才能を重視して選ぶ。このジャンルは特に、脚本の魅力をどれだけ活かし、俳優たちの演技力をどこまで引き出せるか、監督の力量が問われる。
 「アクション」作品の場合は少し違って、映像のインパクトが重要性を増す。爆破や銃撃戦、あるいはカー・チェイスやファイト・シーンで映像の迫真度、つまり“プロダクション・バリュー”を高める手腕が作品の出来映えを左右する。したがって、監督の選択はストーリーの信憑性とか重厚さよりも“コマーシャル性”を基準に、どこまで観客受けする派手な映画作りを出来るかが決め手だ。
「アクション」作品の場合は少し違って、映像のインパクトが重要性を増す。爆破や銃撃戦、あるいはカー・チェイスやファイト・シーンで映像の迫真度、つまり“プロダクション・バリュー”を高める手腕が作品の出来映えを左右する。したがって、監督の選択はストーリーの信憑性とか重厚さよりも“コマーシャル性”を基準に、どこまで観客受けする派手な映画作りを出来るかが決め手だ。
「コメディー」は当然ながら“笑わせる”能力がポイントとなり、老若男女はおろか、文化や生活様式、そして知識層などの違いを超えて笑わせられる監督ほど映画が成功する可能性も高くなる。タイミングや表現方法は簡単そうで難しいのが、このジャンルだ。ともすれば“演技過剰(オーバー・アクティング)”となりがちな俳優を抑えながら、きちっと笑える場面を作ってゆくには、ある種の勘が冴えていないと務まらない。
たえず観客の目を画面へ引きつけることは「スリラー」映画の基本的な要因だ。観客をどこまで“ハイ・テンション”にもっていけるか、そしてどこまで“ハイ・テンション”を保てるかが監督の腕の見せ所。登場人物の動機や心理状態といった繊細なモチーフを、照明や音響効果などの“手段(バイプロダクト)”を駆使しながら描いてゆく中へ、さまざまな“伏線(ルースエンド)”を張るのは、このジャンルの典型である。さり気ないことが、物語の展開につれ、とつじょとして重要性を帯びたり、一見ばらばらの要素と思いきや、意外なところでつながっていたり・・・・・・と、お馴染みのパターンをあの手この手で観客の気を引く。いわば監督と観客との駆け引きであり、重要なチェックポイントは“遊び心”だ。
対照的なのが「ラブ・ロマンス」や最近流行りの「ロマンチック・コメディー」、このジャンルは観客層が大人のカップルという特定市場なだけ、彼らの共感を誘えるかどうかで商品価値は決まる。言い換えれば、“イメージ”の勝負だ。登場人物の台詞が現実的でないとか、俳優とその役柄がマッチしていないだけで、観客のイメージを壊してしまう。違和感を抱き映画へ感情移入の出来ない観客に、共感は誘えない。したがって、笑い、怒り、情熱などの感情を世界中の観客へ訴えかける映像として描きだす腕、また映画でこそ可能なファンタジーをロマンチックに表現できる監督技が求められる。
一家揃って楽しめる「ファミリー」映画、あるいは子供が主人公の「キッズ・ムービー」は、他のジャンルと比べて製作工程で考慮すべき要因が多い。繊細な演技を要求されるシーンや、より表現力のいる会話の場合、人生経験の少ない子供は大人のように自分の体験から演技が出来ず一苦労。ぎこちない演技は、下手をすると他の俳優へ影響し、シーン全体を台なしにすることがある。そこらを巧くコントロールしながら映像を作ってゆく多才な、そして“子供の視野”から物を見られる柔軟な創作力はこのジャンルで不可欠だ。
時代の最先端をいくハイテクCG技術が「SF」映画へめざましい発展をもたらした結果、昔は仕上げの修正で使う“手段(バイプロダクト)”にすぎないCGが、今や主役の座を占める映画まで登場し始めた。大手スタジオは、その財力をCGへ費やす余裕もある。修正ばかりか、映像のインパクトを強める道具として使い、それが効果的なら、もっと使う。修正から改善の道具となり、ますます活躍するうち、とうとう映像そのものまで生み出すレベルへ到達した。中にはCGが製作予算の大半を占める作品さえ現われ、今後も増え続けることは間違いない。
限られた予算枠で中身の濃い映画作りを目指す我々“独立プロダクション(インディーズ)”にとって、そこまでCGを使う余裕がなく、肝心なのはストーリー・ラインや登場人物だ。それらが薄っぺらくならない程度の予算でCG処理を加え、どれだけ効果的な“ストーリー・テリング”を出来る監督かを見る。監督へCGの知識は問わない僕だが、観客のレベルに合わせた作品を仕上げるための最低限必要な知識ぐらいは常識だろう。ともあれ、撮影段階から編集時のデジタル処理を考慮できる監督のほうが、僕はSF向きだと思っている。
最後のジャンルが「ドラメディー」、コメディーとドラマを掛け合わせた造語だ。いま最もホットなジャンルであり、監督としては言葉通り観客へ何らかのメッセージを伝える「ドラマ性」と、軽さの中でセンスの光った「コミカルな要素」を兼ね備えているのが最適である。1つの映画に確かな演技で裏付けられたリアリティーと、観客の笑いを誘う軽妙な仕草や台詞の同居するこのジャンルは、見終わった観客が清々(すがすが)しく映画館を出られるかどうか?・・・・・・僕の経験上、観客の心へ何かしら快い感触を残せる才能の持ち主なら、その監督自身、人生の難題さえ「楽しい」観点から捉えられる気楽な性格だと思う。
以上、プロデューサーの立場でジャンル別監督人選基準みたいなものを述べてみた。彼らから提出される自作のハイライトを選りすぐった“ディレクターズ・リール”と呼ばれるビデオを見たり、仕事を始めてから面接ではわからないプラス・アルファの要素が出てくることは、監督選びの楽しみの一つだ。性格や人生観の違う人間が、それぞれに適した職業へ就く現実社会同様、いろんなジャンルで成るハリウッド映画業界も、製作工程はさまざまな監督候補者の素顔や生き様を浮かび上がらせるのが面白い。
監督にとって、自分の右腕を務める撮影監督(DP)や第1助監督(ファーストAD)との関係、出演者との関係、中でもプロデューサーとの相互信頼関係は重要である。脚本という1次元の世界を映像という2次元、3次元の世界へ広げてゆく上で、プロデューサーである自分のビジョンの具体化を託す以上、誰がディレクターズ・チェアーに座るかは他の人選より難しく、かつ個々の関係が絡み合って形成された人脈構成と、そこでの監督の位置づけを把握することは非常に大切なわけだ。
“バック・トゥー・ザ・フューチャー”シリーズのSFアクション監督として知られるロバート・ゼメキスが、繊細な人間ドラマ“フォレスト・ガンプ/一期一会”を見事に演出したり、“エアープレイン!”などの風刺コメディー監督として知られるジェリー・ザッカーが、万人の心を打つドラマ“ゴースト/ニューヨークの幻”を作ったり、まったくタイプの違う映画を作れるのは、ただ監督の才能というより、その人なりの人生観から生まれた感性や人間性の幅広さだと思う。どちらも友人がスタッフで参加していた関係上、何度かセットを訪れる機会に恵まれた。そこで感じたのは、ゼメキス監督もザッカー監督も、撮影監督(DP)や助監督(AD)との緊迫した連携プレーに「思いやり」、「感謝の念」が溢れ、そのエネルギーでセット全体は包まれていたことだ。
過去、僕が雇った監督で、助監督(AD)と怒鳴り合う者や撮影監督(DP)の助言を聞かず遠回りする者を見てきただけ、ゼメキスとザッカーの真剣な、そして心底楽しそうな様子は印象深く、その違いへジャンルを超えた名監督ぶりの秘訣があると悟った。昼食時、隣で食べながら照明に関して意見を述べる撮影監督(DP)へ耳を傾けるゼメキスは、真剣な表情に微かな笑みを浮かべ、そこへ自信のほどが窺(うかが)える。他人の意見を素直に聞けるのは、それだけの信念がなければ無理だ。この一瞬は僕にとって大きな収穫であった。
プロデューサー稼業を始めた当初、才能がありながら人間関係はまるで駄目、もろスタッフの反感をかうほどエゴが強い監督を雇って苦い経験をさせられた僕は、その後、面接時の印象やディレクターズ・リールだけで監督を選ばないよう心がけている。過去の作品のプロデューサーへ、その監督が現場ではどんな感じだったか聞いたり、かつて一緒に仕事をした助監督(AD)や撮影監督(DP)へも電話で探りを入れ、才能と人間性の両方を考慮し始めると撮影までスムーズに運ぶ。人間、視野が狭くては駄目だという、いい教訓だ。また、半年近くを過ごす中で物を作る以上、楽しくやれる奴と組むほうが出来もいいのは間違いない。
このところコメディー“ファーバーズ・ガイド・トゥー・ベター・リビング”の準備(プリ・プロダクション)で追われ、連日監督の面接が続いている。僕は面接で気に入った人間とカフェテリアなどでコーヒーを飲むのが好きだ。特別コーヒー党というわけでもなく、いわば僕にとっては面接の第2ステップ。商社マンの友人が「ゴルフをすれば本性はわかる」と口癖のように言うだけあって、彼が仕事をする時は、まず取引相手をゴルフへ誘う。ある招待相手はミスショットをしても笑える一方、真っ赤な顔で怒る相手がいたり、ミス・パットを次のホールまで引きずるタイプの一方では切り替えが早いタイプ・・・・・・頭を切り換えられる人間は、それだけ仕事でトラブルの処理能力があると友人は言い切る。
同じく、カフェテリアの長い列で待たされた時なども、人間観察の格好の場だ。釣り銭を渡すのが遅い従業員や、もたもたする年寄りの客、あるいは注文が決まらないカップルと、イライラの原因だらけ。そんな状況で順番待ちの途中、連れ立った面接者は僕と立ち話をしながら絶えず前を気にするタイプから、周囲のことは構わず会話へ没頭するタイプ、そして、もたつく客を指差し文句タラタラまで、いろいろなタイプがいて、それを見るとその監督ぶりも浮かぶ。
僕は「一時が万事」という言葉へ真理を見出す。長蛇の列でイライラしたり怒る人間に、まず映画監督は務まらないと思う。自分自身の精神状態をコントロールできなくて、人が動かせるわけはない。セットでプロデューサーの仕事といえば、大半は“問題処理(トラブル・シューティング)”だ。同じく、監督も怒濤のごとく押し寄せる問題を次々と対処しながら映像を作りあげてゆく。処理能力がなくては物を作る以前の段階で終わる。個々の出演者やスタッフが尊重できてこそ、彼らからも同じ目で見られ、初めて心は通じ合う。人が自分を映し出す最良の鏡と知り、それを実践する監督探しも、僕にとってはなかなか楽しいプロセスだ。
監督の選択という映画製作の一工程を通じて学んだこと、外見とか履歴書が人を判断する参考になるのは確かだが、肝心なのは中身のほうである。上辺にまどわされ、相手が見えない限り、心の奥へは触れられない。そして気心の知れない監督と作った映画で観客の心を動かすことなど、どだい無理だ。名監督スピルバーグがインタビューで成功の秘訣を聞かれ、
「ぼくは観客を今まで彼らが知らなかった空間へ誘(いざな)うことだけを考えている」・・・・・・この言葉こそ、ディレクターズ・チェアーに座る資格みたいなものを集約しているのではないだろうか? 心が豊かでない限り、社会的な地位や財力はどれだけ豊かであろうが貧しい人間だと、最近つくづく思う。肩の力を抜いてつきあえる仕事仲間と製作へ没頭しつつ、「一緒に居るだけで楽しい」と誰からも言われるようなプロデューサーを心がけ、その延長線上で監督選びを楽しみながら心を磨いてゆきたいと願う日々である。