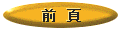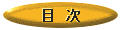パーティー・アニマル
パーティー・アニマル
人類の歴史が始まって以来、宴を設け祝い事や嬉しさを分かち合う風習は、地球上の何処(いずこ)であろうと共通している。中でもローマ帝国が栄華を極めて以来のパーティー好きといえそうなハリウッド、何かのイベントに託(かこつ)けてはパーティーを開く。撮影が終われば「打ち上げ(ラップ)パーティー」、カンヌ、ミラノ、AFM(アメリカン・フィルム・マーケット、通称ロサンゼルス映画祭)などのフィルム・フェスティバルでは各配給会社主催の「ごますり(シュムージング)パーティー」が開かれ、参加者はハロウィーン同様コスチュームを着て子供時代へ逆戻り、そして仕事仲間やクライアントを自宅に招き「ホーム・パーティー」と、一年を通じて様々な“宴会”が催される。
「打ち上げ(ラップ)パーティー」は、基本的に製作へ参加したキャスト、スタッフとその家族が招待され、大手スタジオともなればパーティー予算は余裕があり、招待客は誰を連れ行こうが問題はない。しかし、われわれ独立プロ(インディーズ)の場合は映画が完成する頃、当初の予算編成会議で割り当てたパーティー費用さえ、たいがいは製作費に化けて消え去った後だ。したがって、プロデューサーの家や友人のレストランをPRと交換(バーター)で借り切るなど、苦肉の策となる。
僕が初めてプロデュースをした“ナイト・オブ・ザ・ウォリアー”の「打ち上げ(ラップ)パーティー」は、当時僕の広報担当(パブリシスト)であったアメリコムというPR会社のおかげで、センチュリー・シティーのど真ん中にあるABCエンターテイメント・センター内の高級クラブを貸し切りで、アメリコムが手配したTV取材陣の取り囲む華やかなパーティーとなった。ビシッと決めたキャスト陣、家族連れで現われるスタッフとの再会は、撮影が終わってまだ数日足らずにも拘わらず、何か新鮮な感動を誘う。眩しいばかりの照明の下でインタビューを受けながら、僕は自分がハリウッドにいる実感を覚えたものだ。
 ビュッフェ・スタイルの軽食は、洋風餃子のような前菜からフィンガー・サンドイッチまで色とりどりで、豪華に並ぶサラダ・バーも人気がある。各自ペーパー・プレートへ盛った食べ物を肴にシャンパンやワインのグラスを傾け、撮影中の思い出話や失敗談で沸く。ロケ中はいがみ合っていたライン・プロデューサーとロケーション・マネージャーが喧騒の中で仲睦まじく語り合う姿、あるいは大道具係が幼い娘を主演のロレンゾ・ラマスへ紹介するところ、そんな微笑ましい情景は緊張の連続だった僕のプロデューサーとしての日々に一筋の光を投げかけてくれた。
ビュッフェ・スタイルの軽食は、洋風餃子のような前菜からフィンガー・サンドイッチまで色とりどりで、豪華に並ぶサラダ・バーも人気がある。各自ペーパー・プレートへ盛った食べ物を肴にシャンパンやワインのグラスを傾け、撮影中の思い出話や失敗談で沸く。ロケ中はいがみ合っていたライン・プロデューサーとロケーション・マネージャーが喧騒の中で仲睦まじく語り合う姿、あるいは大道具係が幼い娘を主演のロレンゾ・ラマスへ紹介するところ、そんな微笑ましい情景は緊張の連続だった僕のプロデューサーとしての日々に一筋の光を投げかけてくれた。
“カル/征服者”や最近のジョン・カーペンター監督作“バンパイア”で活躍しているトーマス・イアン・グリフィスを起用した“オルテリア・モーティブス”の時は、編集段階で思わぬ出費がかさんだため「打ち上げ(ラップ)パーティー」はオジャンかと諦めていたら、ルイジアナ州から出稼ぎに来ていた照明係(グリップ)のチームが滞在中のマジック・ホテルで持ち寄りパーティーを開こうと提案する。急拠、スタッフは大量のスナック、ビール、フライドチキン、ピザなどを持参し、大盛況となった。彼らが宿泊する4部屋のテラスを中心に、中庭でバドミントンをする者、部屋の片隅で次の仕事の話で盛り上がる者、ビールの勢いも手伝ってか、プロダクション・マネージャーへロケ中の食事の文句を言う者、また数人でマリファナを吸いながら大笑いのグループは、いかにも楽しそうだ。
この作品で第2助監督として頑張ってくれたローレンス・ベンダーも、そのパーティーではビール片手に“夢のプロジェクト”への情熱を語ってくれた その時、脇に抱えた脚本“レザボア・ドッグス”が彼のハリウッド登竜門となり、その後“パルプ・フィクション”から“ジャッキー・ブラウン”へと移行していくあたりは「明日に向かって撮れ!?」で書いたのを、ご記憶のかたもおられよう また、パーティーの盛況さと共にエスカレートするラジカセ音楽へ他の宿泊客が文句をつけた時、彼らの部屋に行ってお詫びついで、パーティーへ招待し、和やかさを演出するという外交手腕を見せたPA(プロダクション・アシスタント)のキャロルは、現在ワーナーブラザーズの製作部門で企画を練るまでに成長している。
その後も、いろいろな映画製作へ携わるつど体験してきた「打ち上げ(ラップ)パーティー」、場所や豪華さこそ違え、作品から作品を転々とするジプシー軍団のごときスタッフが、またいつ会えるかも知れぬ人々と、ひとときの安らぎと憩いを得られる宴の場。そう考えると、「打ち上げ(ラップ)パーティー」の足跡はハリウッド・ゲームへのめり込んでいった人々の足跡でもありそうだ。
映画祭のパーティーとなれば、さすが公開作品や撮影前の配給権前売り(プリセール)の宣伝効果が目的とあって、メニューの内容からして豪華絢爛(けんらん)である。ビュッフェ・テーブルに飾られた巨大な氷の彫刻の周りへ所狭しと置かれた食べ物も、ベルーガ・キャビアあり、シュリンプ・カクテルあり、握り寿司ありのハイソ風。おまけに、広大なダンス・フロアの一角では生バンドが洒落たモダンジャズを奏(かな)で、シックなムードを盛り上げるばかりか、演奏の合間には目玉映画のハイライト場面が映写される演出ぶりだ。ヨーロッパの映画祭、特にカンヌは夜を徹してのパーティーが有名で、招待状を貰ったパーティー全部に出席しようものなら、2〜3日の徹夜は覚悟しなければならない。
また、ヨーロッパ・スタイルのパーティーといえば、配給会社がパーティーの象徴として主演スターたちを招く。カクテルとリラックスした雰囲気の中、彼らは時として地元ロサンゼルスで見せない素顔を出す。ハリウッド・ゲームへ参加しながら“一映画ファン”であり続けたいと願う僕にとって、映画俳優でなく人間として彼らの内面が垣間見られる絶好の機会(チャンス)なのだ。ミラマックスの船上パーティーで会ったティム・ロビンスの柔和な微笑(スマイル)と地中海をクルーズしながら彼と交した映画談義、また中世の城を借り切った20世紀フォックス主催のパーティーで会ったショーン・ペンの形容しがたい存在感、こうしたパーティーの思い出の一つ一つが今では珠玉の宝物になっている。
パーティーといえばハロウィーン、ハロウィーンといえば、ご存じのとおり子供たちがバンパイアだのドラキュラだの思い思いの格好で近所を回り、キャンディーをおねだりしながら聖霊を祭る祝日だ。最近ではそのコスチュームも忍者タートル、バットマン、スポーンなど映画のスーパーヒーローが目立つ。一般社会と比べ“純真(イノセント)”なハリウッドらしく、スタジオやデザイナー、アート・デイレクターなどの主催するハロウィーン・パーティーは、大人たちが総じて子供に戻る異様な一夜と化す。
昨年はSFX(特撮)スタジオとデジタル処理スタジオが合同で催すハロウィーン・パーティーへ参加した。ロサンゼルスのダウンタウンにあるストック・エクスチェンジという巨大なディスコを貸し切りの“仮装パーティー”は、母親が子供のため余りものを使って作るハロウィーンの伝統など何処(いずこ)やら、参加者のコスチュームたるやどれも本格的だ。専門店で買った既製品は勿論のこと、映画に使われた衣装を纏う者までいて、会場はまさしく仮面舞踏会の体であった。
まず、入口で豹の毛皮と薄汚れたメークで決めた“フリント・ストーン/モダン石器時代”風の原始人カップルに度肝を抜かれる。そして、アリーナ仕立ての建物へ一歩踏み入れるや、全身銀色の「自由の女神」、例の呻き声をあげるスターウォーズの毛むくじゃら「チューバッカ」、黒タイツが何故か笑いを誘う肥満気味の「スパイダーマン」、筋肉が少々弛んだ「超人ハルク」、挙げ句は怪しげな着付けの「金髪の芸者ガール」まで、次から次へと登場。心臓が飛び出すほどのロック・ビートをバックに、正面ステージ後方のジャイアント・スクリーンでは、フランケンスタインやドラキュラで一世を風靡した白黒時代の名優ボリス・カーロフとベラ・ルゴーシの勇姿が浮かぶ。
シャンパンと寿司(カリフォルニア・ロール)という妙な取り合わせがやたらハリウッド臭く、会場に溢れんばかりのインディー・ジョーンズ数十名が、お互いを意識する不思議な世界へ別れを告げる頃、午前1時を回っていた。ちなみに、リーゼント・ヘアーで決めた僕が黒の皮ジャンとブルージーンズ、ポニー・テイルのワイフはプリーツ・スカートとツートン・シューズで決め、トラボルタとニュートン・ジョンを真似た我々の“グリース”カップル・ルックはなかなかの評判だったと自負している。そして、帰途に就く僕の脳裏で、訪れた子供達へキャンディーを与えないと、家中トイレット・ペーパーでグルグル巻きにされるというハロウィーンの言い伝えが浮かんで消えた。
さて、いろいろあるハリウッド・パーティーの中で、特にホストの好みや人柄が現れるのはホーム・パーティーといえよう。指定された時間から15分ぐらい遅れて行くのを“ファッショナブリー・レイト"、つまりカッコいい登場のしかたとされ、そこには定刻通りドアベルを鳴らしてホストを慌てさせぬ気遣いがあるようだ。持参のお土産はといえば、日本と違って駅前の和菓子屋で出来合いを買うわけにもいかず、冷蔵庫へ入れて冷やす必要のない物、その日の内に食べられる物などを持っていくよう心がけている。中でも、まろやかな赤ワインなどが喜ばれるようだ。
招待客の人数にもよるが、プロデューサー級のホーム・パーティーともなれば、たいがい赤いチョッキを着た専門の駐車係(バレー・パーキング)を雇う。レストランの正面玄関へ車をつければ、サッと現われる例のパターンで、丘の上にある邸宅などの場合、下で駐車して歩く手間を省いてくれる暖かい配慮といえる。また、玄関を潜るとホストが上着を預かってくれたり、抱擁(ハグ)を交したりのスキンシップで出迎えるほか、パーティー上手のホストともなれば、まずトイレとバーの場所を教え、既に盛り上がっているゲストへ紹介しておく。こうすれば「あとはセルフサービス」というわけだ。これがハリウッド・パーティーの特徴でもある。
もう1つの特徴は、いろいろなサークルに係わる人々の自由な触れあいが奨励され、「誰々を知っている」という“ネーム・ドロッピング”の会話は敬遠され、これもハリウッドの体質を象徴していると思う。有名人の名前を出さないと自己主張が出来ないようでは相手にされない。また、それらのパーティーで著名人ほど「腰が低い」のは、言い換えれば、そうした柔らかい物腰だからこそ著名となるわけだ。
足の踏み場もないほどの人混みを縫い、こまめにゲストへ気を配るタイプ、そうかと思えば出前(ケイタリング)サービスとメイドに持てなしを任せっきりで、仕事話ばかりするタイプと、いろいろなホストがいる。これまで多くのホーム・パーティーへ招かれた経験上感じるのは、やはりホストの人柄がそのままパーティーへ反映されることだ。大手スタジオ重役のビバリーヒルズ豪邸で開かれたホーム・パーティーは、2階に上がる階段が物々しい鉄製の柵で封じてあった。その冷たさは、友人のプロデューサー宅で催されたパーティのアット・ホームな暖かさと対局を成し、僕の脳裏へ焼き付いている。そして、初めて訪問する我々夫婦に自宅を案内しながら、友人のプロデューサーが微笑を浮かべて言った・・・・・・“My house is your home. (私の家はあなたのホームですよ)”と!
ハリウッドという華やかな世界で繰り広げられる多彩なパーティー・シーン、ホストの「気遣い」とゲストの「寛(くつろ)ぎ」が絡み合った時、初めて生まれる和やかな空気は、パーティー全体を包み込んで雰囲気を盛り上げてゆく。参加した人達のエネルギーが1つになって昂揚する。考えてみれば、人生はある種のパーティーだ。暮らしの中で同じ空間を分かち合う人々が心地よく過ごせるよう、あるいは自分が参加したことでパーティーが、より有意義なものとなるよう、今後とも素晴らしいホスト、またゲストとして“パーティー・アニマル”の人生を歩んでゆきたい!