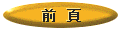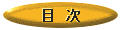聖なる森、聖なる旅 (中)
聖なる森、聖なる旅 (中)
アリゾナ州ツーソンは砂漠の真ん中にある小じんまりとした街だ。バスケット・ボールで名高いアリゾナ大学があるカレッジ・タウンなので、近郊のスコッツデールやフェニックスのような引退者コミュニティーとは、やや趣(おもむき)が違う。ハワードと連れだってツーソンへ着いた僕は、さっそくホテルをチェックイン、早くも数人の“ファイアー・ウォーク・セミナー”参加者がロビーで屯(たむろ)している。
チェックインの順番を待ちながら彼らを見ていると、ガラス張り窓から燦々と降り注ぐ強烈な日差しとは裏腹に、なんともいえない緊張感が湧く。そして、ふと列の前方へ目をやった僕は、カウンターで宿泊カードを記入している顔に気がついた。カジュアルなポロ・シャツ姿で受付嬢と話す精悍な顔つきは、あの辣腕プロデューサー、ピーター・グーバーに間違いない。数年前、ソニーがコロンビアを買収した際、運営を任された“バットマン”のプロデューサーであり、その後、パートナーのジョン・ピーターズと「ソニーを食いつぶした男達」として悪名を馳せた人物だ。
 彼以外、数人の俳優がいるのを見た僕とハワードは、話でしか知らなかったアンソニー・ロビンスの“ハリウッド・コネクション”を垣間見たようで、怖さの入り混ざった不思議な期待感がますます募り、ちょうどサマー・キャンプへ出かける少年のような気分になってきた。
彼以外、数人の俳優がいるのを見た僕とハワードは、話でしか知らなかったアンソニー・ロビンスの“ハリウッド・コネクション”を垣間見たようで、怖さの入り混ざった不思議な期待感がますます募り、ちょうどサマー・キャンプへ出かける少年のような気分になってきた。
チェックインの後、宛(あてが)われた部屋で落ち着き、向こう3日間のルーム・メイトと挨拶を交わしているところへ誰かがノックする。ドアを開けると、セミナーのアシスタントらしい青年からアンケート用紙を渡され、午後3時のオリエンテーションまでに質問事項の答を書き込んでおけと言う。質問は、「自分自身の一番好きな点」、「自分自身の一番嫌な点」、「自分はこうなりたいと思うこと」、「自分のこういうところを直したいと思うこと」、「自分の理想の人生とは?」・・・・・・
ほとんどが普段あまり深く掘り下げることのない内容であり、答は出来るだけ正確かつ詳しく書くよう注意書きが添えてある。それからしばらく、ディズニーでアニメ製作に携わっているという知り合ったばかりのルームメイト、ビルと僕は、アンケート用紙を睨んで自問自答の時を過ごす。問いかけるかのごとく窓の外へ視線を向ければ、南西部特有の尖った山々や乾ききった薄茶色の道路が無言で佇(たたず)んでいた。
3時になると約50人の参加者はホテルの会議室へ集まり、壇上に立ったロビンスが挨拶の後、さっそく「皆さんはなぜここへ来ようと思ったのですか?」と問いかける。それに応え、「知人が推薦したから」、「自分の弱点を克服したいから」と、思い思いに言う参加者を笑顔で制し、ロビンスはその190センチを越す巨体から発散されるパワフルな声で言う。
「答は簡単です。皆さんがここへ来たのは、自分で来ることを選択したからであり、それ以外の理由など、まったく考える必要がありません」と・・・・・・
そしてロビンスは、生まれた瞬間から今この瞬間に至るまで、毎日何千回と巡り会う「選択」の瞬間を一つ一つ説明してゆく。親が選んだオモチャの中から自分の好みを「選択」し、学校で「気の合う仲間」を「選択」する過程や、様々な状況下で「いい気分」、「嫌な気分」を「選択」してゆく過程、やがては長年培った習性で、自分が滅入るような「選択」をしてしまうパターンなどの説明を聞くうち、自意識へ疑問を抱き始める。しかし、これまでは自分の中にいるロボットへ選択を任せていた気分になると同時、“新しい自分”を意識した瞬間でもあった。
Aから言われると腹が立つ言葉をBから言われても平気、あるいは親から言われると反発したくなるような台詞を親友から言われても笑って聞き流す。そんな例を引き合いに出しながら、ロビンスは我々が日頃どれだけ自分の気分や満たされない心を「他人(ひと)のせい」にし、人生は自分の「選択」が決定することを忘れているかを指摘する。いい気分や笑いを誘う「自分に良い選択」は、気分を害したり怒りを誘う「自分に悪い選択」と、まったく同じエネルギーを消費することを医学的、科学的な見地から説いてゆく。
知らず知らず否定的な「選択」を続けるうち、それが潜在意識へ植えつけられ、自分に対する嫌悪感を覚え始める。その自意識は潜在意識へ影響し、ますます自己嫌悪が募る悪循環の繰り返し・・・・・・意気揚々と語るロビンスの口調に、じっと聞き入る参加者たちは、今まで自分が選択してきたパターンを探ろうとする僕とよく似た心境に違いない。そんな想いを感じたのか、「僕は今まで選択の自由を知らないロボットみたいな生き方をしていたのか!?」と、隣でハワードが呟いた。
続いてロビンスは、先ほど記入したアンケート用紙の内容を思い出すよう促(うなが)す。答の奥に潜む自分の「選択」を探り、自分の長所が育(はぐく)まれた認識同様、絶えず「選択」意識を持つ大切さを教えてくれる。そして、自分の弱点や嫌な部分も違う観点から捉(とら)えれば「長所」であり、嫌なことや「こうなって欲しくない」考えを拒否するのは自分の「選択」であると再認識させられた。選択の自由、自分の望む道を生きる素晴らしさ、その素晴らしさを参加者全員が感じているのは、会場を満たす空気からひしひしと伝わってくる。
朝からアンケート用紙と取り組み、3時から始まったオリエンテーションが終わる8時まで、強烈なインパクトで参加者全員は空腹を覚える暇もない。そのインパクトが余韻を残すまま会場を出た僕は、ふと思う。チェックインを待ちながら、ピーター・グーバーを見かけて気が昂(たか)まったのは、当人の実績や存在感の強さと関係なく、僕自身が自分で「興奮」を「選択」しただけなんだ!!・・・・・・と。
発想の転換は、ある種のパワーだ。ハワードが「彼はきっと僕らと食事なんかしないよ」と言おうが、僕は「何が自分を躊躇させているのか見つめる絶好の機会だぜ」と、ちょうど早足で先を急ぐグーバーの後を追っかける。追いついて自己紹介の後、食事に誘ってみたら、ちょうど一人ぼっちで食事をするつもりだったらしく、快く承諾してくれた。ホテル内のイタリアン・レストランでパスタを囲み、彼が語る大手スタジオ・ゲームの内幕や映画製作の面白さ、あるいは若い僕への激励の言葉を聞くうち、自分の「選択」が思いがけない方向に向かう“人生の醍醐味”を味わえた印象深い一夜となったのである。
翌朝も、意識はないまま自虐的な「選択」を操り人形のように繰り返す自分へ気づく瞬間の大事さ、これまでと違う「選択」をする勇気、その実行の思いがけぬ簡単さ、それらを語るロビンスの説得力に時間の経つのが早い。昼休みはルームメートや友人以外の初対面の人との食事を勧められ、個々の衒(てら)いを忘れて見知らぬ者同士が声をかけあう。
僕の選んだ相手は、ユニバーサルでメイクを担当するバーバラという中年の女性だ。自分の人生へ常に不安を抱く自分を変えたいというのが、彼女の新しい「選択」らしい。ツナ・サンドの昼食を囲み、お互いの「理想の自分」を語り合う僕たちの間で、初対面とは思えぬ和やかな空気が充満し、あるがままの自分で人と接する威力、また人の話を親身に聞く喜びを感じさせる充実した時間であった。清々しい気分で別れた後、午後のセミナーはちょうど昼食時の会話を彷彿させる内容なので、遠くに座ったバーバラと目を合わすたび笑みが浮かぶ。自分の可能性を信じる「選択」は、今まで自分の潜在意識を縛っていた「恐怖心」を拭う一番の手だてという下りでは、僕とバーバラばかりか、誰もが数時間後の“ファイアー・ウォーキング”へ想いを馳せていたに違いない。
参加者全員が、これからは今までと違う「選択」をし、「自分の人生という自動車を自分が運転してゆく」決意をしたところでロビンスは言い放つ。
「さあ、それでは、その新たな決意を実証する時間がきました!」この言葉に、僕は一瞬、心なしか自分の顔が引きつったようで、つい隣を窺う。そんな僕を今にも嘔吐しそうな青ざめた表情でハワードが見返していた。
アリゾナ砂漠の日暮れは早い。空へ向かって突き出した山々が影を落とし、あんなに暑かった日中が嘘のような肌寒さだ。午後7時、4人の女性を含む参加者全員は準備の整ったホテルの中庭へ勢揃い、その情景に息を呑む。中庭の一端から約1メートル幅の直線コースが10メートルばかり続く。敷き詰められた大粒の石炭(コール)は数時間前に火が点き、赤々と燃えている。コースの横で整列した参加者は石炭(コール)の照り返す熱がイヤというほど伝わり、これから裸足でこの上を歩く自体、正気の沙汰とは思えない。
コースの両側へアシスタント達が着くと、アルファベット順に並んだ参加者は、いよいよ「決断の時」を迎えたのだ。重い足取りで出発点へ移動しながら、今まで興奮のあまり目に入らなかった救急車と白衣のスタッフが炎の彼方で揺れているのを見て身震いする人、啜り泣く人、貧血で膝を落とす人、無言のうちカッと目を見開く人などが、武者震い(?)する僕と並んで進む。先ほどの「決意」は何処やら、誰もが死刑執行室に向かう囚人のごとき面もちなのだ。
どんどん重みを増してゆく辺りの空気を打ち破るかのごとく、突如として現われたショートパンツに裸足のロビンス、
「新しい生き方は、新しい選択がもたらす奇蹟の実証です。自分の可能性を信じ、この石炭(コール)は絶対熱くないと自分が『選択』すれば、火傷はおろか、熱も感じません。しかし、恐ろしい、怖い、火傷をすると思う『選択』をすれば、当然ながら大火傷をします」と、まるで人ごとのように言い放つ。大きな瞳の奥でメラメラと燃えたぎる炎が反射し、彼は先を続ける。
「この中の1人でも脱落したり火傷をしたら、グループ全員が脱落ということです。他人(ひと)は自分の延長であり、他人(ひと)の勝利は自分の成功を意味します。自分自身の選択へ、それほどパワフルな力が秘められているのです!」
そして列の最先端に立ったロビンスは大声で、「さあ、この瞬間から自分の『限りない力(アンリミティド・パワー)』を信じるという選択を始めましょう!」と叫ぶや、無言で石炭(コール)の上をゆっくり歩き出す。その後を「ゴー、レッツ・ゴー!」と囃し立てるアシスタント達のかけ声に勇気づけられた参加者一人一人が必死で進む。あと2人と迫った僕は、頭の中でアイススケート・リンクを歩くイメージを描きながら、「ノー・リミット(限界などない)! ノー・フィアー(恐くなどない)!」と自分に言い聞かせる。すると、それまでの威圧感や震えるような恐怖心が薄らぎ、一種の陶酔状態で石炭(コール)の上を歩き通せたのだ。
“ファイアー・ウォーキング”を終えた他の参加者同様、僕は興奮と満足感で止めどなくこみ上げる涙を拭おうともせず、これから歩くメンバーへ力一杯声援を送る。誰一人火傷を負わず、いよいよ2人を残すのみとなって、
「ぼ、僕には出来ない・・・・・・」、テキサスから来たダレルという青年社長が後ずさりを始めた。端で見てわかるほど膝を震わせ、自分への失望か、しゃくりあげるように泣いている。何とか力づけようと必死で声援を送り始めた我々の耳元へ轟(とどろ)くロビンスの一声、
「ダレル、ここが君の選択の瞬間だ。パワフルな君に生まれ変わるか、それとも今までどおり怯えた人生のまま一生を終えるのか、それは君自身の選択なんだよ!」
その瞬間、初めて彼の成功がわがことのように思えた僕は、ハワード、ビル、グーバー、そして周りの全員と一丸となり、涙ながらに絶叫していた・・・・・・
「行け、ダレル!」 (続く)