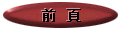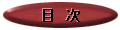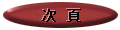映画と原作
去年のエッセイは“拳銃”や“飛行機”と、いわば趣味をテーマに書いた。そして、年が明けて第1回目の今回は、自分の専門分野である“小説”を取り上げてみたい。まず、その映画との関連だが、いくら素晴らしい原作でも映画と小説は別物であり、それが映画の出来を直接左右すると思うのは間違いだ。むしろ、小説の映画化を原作と比べた場合、期待はずれのケースが多い。
映画の出来を左右するのは“脚本”であり、名を成した監督をみると、みんなスタイルこそ違え脚本のセンスが抜群な部分は共通している。自分が書く監督もいれば、脚本家を巧く使う監督、あるいは両者を使い分けたり、その逆で人と組むのも1つの方法だろう。優れた小説がよく原作として使われるのは、脚本が生まれる時、それらの監督や脚本家へインスピレーションを与える道具と捉(とら)えれば簡単だ。
ようは原作を活かすも殺すも脚本のセンス次第、センスの良さならスティーブン・スピルバーブやジョージ・ルーカスあたりが好例だし、わが黒澤明しかり。黒沢の話はいろいろ聞くが、中でも私は2つのエピソードが忘れられない。1つは映画史上の偉業とさえいえる、あの“天国と地獄”のクライマックス・シーンだ。絶妙のタイミングで一瞬カラーを使うアイデアも、そこまでの長いプロセスがあった。黒澤は、たとえ世間がカラーへ移行しようと、納得できないうちはモノクロに拘(こだわ)り続け、その執念のごとき探求心がさまざまな葛藤を繰り返しながら、わずか何秒かのシーンへ凝結してゆくのである。


今回のテーマと関係あるのはもう1つのエピソードで、やはり黒澤の飽くなき創作欲が窺(うかが)え、なかなか興味深い。それは、あるロケ先で撮影を始めて間もない頃のことだ。夕方になって旅館へ戻るや、未完成の脚本をめぐり、スタッフと激しい議論を繰り返すのが黒澤の日課であった。未完成とはいえ、撮影を開始するぐらいだから、物語の下地が出来上がっていないわけはなく、納得できないところを修正・・・・・・いつものパターンである。だが、この時は少しばかり事情が違う。
黒澤はリアリティーを追求するための試みとして、新しい脚本形態を考えた。脚本の中で違う登場人物の台詞を同じ人間が書くと、どうしても観点は偏(かたよ)る。それなら、いっそ主要登場人物ごとの脚本を別々の人間へ書かせたらどうか? そして、定期的に全員が集まり、各自の脚本をお互いぶつけ合いながら、進路修正してゆく。つまり、1人の登場人物を演じる個々の脚本家は、他者の反応を探りながら自分のパートを固めるわけだ。こういったアイデアは、既成概念に囚(とら)われている限り生まれない。
針路修正のため全員が定期的に集まるのは、今でいう、“ブレインストーム”であり、その中から何か新しい物を求めるなら、当然“指揮者(コンダクター)”が必要だ。結局、棒を振った黒澤は、脚本家を巧く使うどころか、1つの役柄へ1人の脚本家をあてがい、全員を巧く使って見事なハーモニーを奏でた。しかし、柔軟性のある発想が素晴らしいと思う一方では、改めて映画と小説の違いを痛感させられる。
そもそも、“物書き”とは人を観察する職業だ。そんな習性があらばこそ、黒沢のエピソードへ興味を引かれ、また映画を見るとスクリーンの裏側まで気になってしまう。裏側というのはプロデューサーや監督、その他あらゆるスタッフを指すばかりか、スクリーン上へ現われる連中がカメラに向かってない時も含む。つまり、映画製作へ参加した全員を窺(うかが)い、中でも監督や脚本家は小説家同様、人を観察する職業であり、観察する人間を観察するんだから面白い。
彼らがプリ・プロダクション(準備段階)で登場人物を創作する場合、具体的なイメージは小説以上に重要となる。クッキリ絵柄が浮かばず、映像へ結びつけるのは無理だ。反面、私の登場人物が頭の中で動き出そうと、その動きは抽象的なこともある。最終的にどのような絵柄が浮かぶかは、映画と違って個々の読者へ託す。また、小説が独りぼっちの作業なのに対して、映画は共同作業。監督たるもの、(脚本家と限らず)スタッフ全員のアイデアをどれだけ引き出し、それを自分のイメージでどこまでまとめられるかが腕の見せどころといえよう。登場人物を創作する上で脚本家の比重は大きいが、いざ撮影となれば、がぜん重要性を帯びてくるのがカメラマンだ。
ただし、そうあっさり撮影開始へ漕ぎ着けられやしない。それまでには、まだまだ長い道程がある。映画を製作する過程で、撮影はほんの一プロセスだ。プロデューサーの集めた金で製作が決定すると、まずはプリ・プロダクションが始まる。脚本を準備したり、配役(オーディション)やロケハン、あるいはセットを組むなら、そのアレンジに全体のスケジュール調整など、限りなく雑務が控え、頭痛の種は尽きない。監督をはじめとするスタッフ全員が、この段階を堪えられるのは、
「いい映画を作るぞ!」という目的意識(すなわち夢)があらばこそ。目的意識を持たず、ガンバリ通せる監督がいるなら、そいつはマゾだろう。
このプロセスを経て、ようやく次の段階に進む。いよいよ撮影開始だ。頭の中で描いたイメージを映像へ移す作業の始まり、具体的なイメージを直接ファイルムに収めるのがカメラマンの役割なら、その前で演技をするのは役者である。役者と同じく、映像を決定づけるもう1つの要素が背景(ロケーションやセット)だ。SFX(スペシャル・イフェクト)を使う映画だと、映像はそちらの担当者次第。メークや衣装担当、プロップ(大道具、小道具)も、昔ながら地味な存在だが、監督の狙うイメージを具体化するため責任は重い。もっとも、最近のようにSFXが複雑化すれば、カメラやメークの領域をカバーしてしまうケースだってある。
他にも、グリップ、照明、音響から、コーディネイター、ケータリング(食事の世話係)、セキュリティーに至るまで、それぞれ欠かせぬ存在だ。また、登場のし方は最も華やかであり、且つ、最も隠れた存在がスタントマン、彼らを忘れちゃ映画を語る資格なし。そんな皆さん、顔こあお出さないものの、実際、名前はスクリーンに登場する以上、れっきとした“登場人物”・・・・・・違いますか?
スクリーンへ顔を出す人、出さない人、全スタッフが一丸となり、撮影は無事終わったとする。これで二番目のプロセスが完了、役者やカメラマンはとりあえず一息つく。反面、監督が個人レベルに帰って創造性を発揮できるのは、この最終段階だ。いくら撮影を終えようが、編集前のフィルムはただの素材、映画と程遠い。編集行程を経て、どうにか映画らしい形が整う。そして、取り直したりフィルムに特殊な処理を施さなくて済む場合、残るは“音の世界”のみ。台詞のレベル調整や入れ直し、効果音やサウウンド・トラックの録音、これでイメージがごろっと変わる。その極端な変わりようを知れば誰だって、映画の製作者は音楽一つおろそかに出来ないとわかるはずだ。
他の面でどれだけセンスが良くても、音楽面に疎い監督は、自分が描くイメージを登場人物へ託せない。観客へ伝えきれない。それは音楽と限らず、ストーリーのセンス、役者を活かすセンス、映像のセンス、スタッフを使いこなすセンス、どのセンスが欠けても同じ結果になる。映画は、ある意味で総合芸術だ。すべての面でバランスが取れたセンスを制作者は要求され、だからこそ作り甲斐がある。この面白さは“スピルバーグ”クラスであろうがB級映画であろうが根本的に変わらない。
こうした映画のプロセスと比べ、小説はすべてが心の中で進行してゆく。取材のため、あるいは編集者との打ち合わせなど、人と触れ合うことがあっても、そこから感じるものを文章へ置き換える作業は孤独である。たとえ人との共著であろうが、心は共有できない以上、最終的な書く段階で個々へ戻るしかない。映画ならスタッフ全員のリズムが合った時、撮影は順調に進み、小説なら筆が進むのは、頭の中で登場人物が動きだした時・・・・・・結局、イマジネーションの世界というわけだ。
エッセイや短編小説を除き、400字原稿600〜800枚分の長編は、書き始めて仕上がるまで2〜3ケ月から1年近くかかる。アイデアをまとめる期間を入れると、もっと長くなり、その間、頭の中は物語の世界へドップリ漬かりっぱなし。筆が進むうちはいいが、いくらがんばろうと登場人物は頭の中で静止したまま動こうとせず、いいかげんうんざりすることも多い。ひどければ、執筆への疑問さえ浮かぶ。ただ、そうした葛藤があらばこそ、仕上がった時の喜びはひとしおなのである。
マイケル・ダグラス、キャスリーン・ターナー主演の“ロマンシング・ストーン/秘宝の谷”という映画を憶えておられるだろうか? ターナー演じるベストセラー作家が長編を仕上げたところで、物語の幕が開く。完成した作品に自ら感動のあまり、涙を流しつつ独り祝杯をあげるシーンの嘘臭さたるや、なんともいえず良いのだ。コミカルなシーンとはいえ、考えてみれば長編を仕上げた時の私自身、ほとんど変わらない。さきほど、
「観察する人間を観察するんだから面白い」などと書いたが、どうやらこれは相手の立場でも言えるようだ。そして、観察しようが観察されようが、結局、出来上がった物を皆さんに楽しんでいただければ、われわれエンターテイナーは本望なのである。
横 井 康 和
|