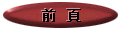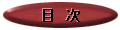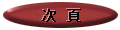映画と食べ物
人間を含め“生きている物”を生物といい、生きていくためには食べる必要がある。それを“種”として捉えた場合、生きるとは“個”が代々子孫を残していくことだ。しょっぱなから「これは本当に映画のエッセイなのだろうか?」と疑われそうで怪しげな雰囲気だが、要は人間の欲望の中でも食欲や性欲がそれだけ本質的なものだと言いたいのだ。健全な食生活や性生活抜きで健全な生活は送れない。当然ながら、人間を描いた映画や小説にそういった欲望が密接な係わりを持ち、その中でも今回は食べ物をテーマに選んでみた。同じ欲望なら他者のほうがいいとおっしゃるかたへは、エッセイより写真集とか別の形態をお薦めする。ポルノ映画をテーマにエッセイを書くのでは、どうも具合が悪い!?
さて、食べ物との関連で思い浮かぶのは、テーマが映画でも“物書き”である以上、まずは小説が絡む。マックスのような映画プロデューサーや私のような物書きはエンターテイメントを提供する側の立場とすれば同じエンターテイナーだ。そして、人が楽しんでくれてこそエンターテイメントなら、我々はどう楽しんでもらうか? どう人の心を動かせるかがポイントといえよう。観客や読者の欲望をくすぐるのは、くすぐられる側から見るほど簡単じゃない。それだけに、ゴクンと唾を呑み込むような食べ物の描写などは、人一倍感心させられるわけだ。
まだ中学生だった頃、最初の1冊を読んで以来、残りのシリーズ全作品を読破してからは次作を心待ちにした007シリーズ。その後、映画化されてますます知名度が高まるスーパー・ヒーローは、生みの親であるイアン・フレミングの死後もベルリンの壁が崩れ落ちて世界は変わろうとも生存し続けている。このジェイムズ・ボンドが成功した大きな要因の一つは、まさしく食事への拘(こだわ)りだった。
ボンドのトレードマークといえばワルサーPPKばかりか、ケメックス製ブラック・コーヒー2杯と、きっかり3分30秒ゆでた卵、クーパー製オックスフォード・マーマレード・ジャムとノルウェー産ヒース蜜蜂の蜂蜜をつけた粗麦(ホールウィート)パンの朝食、それにジン3、ウォッカ1、キナ・リレのベルモット2分の1を混ぜる代わりシェークしたマティーニや、グローヴァー・ストリートのモーランズ社製特製煙草なのだから……
執念とすら思える食事への拘(こだわ)りだが、現実はフレミンング自ら言うとおり、本物のスパイが習慣に拘(こだわ)るのは危険である。朝食に使う食器が濃紺と金と白のミントン陶器であろうと、コーヒー・ポットや銀器がクィーン・アンの物であろうと敵に目立つ心配はなかろう。だが、バルカンとトルコの葉をミックスし、金筋が三本入った特製煙草なんか吸ってると目立ちすぎてしょうがない。幸い気づかれなかったとして、マティーニを注文する時、「混ぜる代わりシェークしてくれ」などと言えば、いくらドジなKGBエージェントであろうと、「あっ、ボンドだ!」すぐわかるはずはずだ。結局、物語の中でこそ拘(こだわ)れるのであり、そのあたりは本人ばかりか、登場する女性達もなかなかうるさい。
第1作“カジノ・ロワイヤル”でヴェスパー・リンドが、
「そうねえ、まずキャビアで、それから子牛のレバーの素焼きにりんごのスフレをそえたの。それから、クリームのたっぷりかかった木いちごがいいわ」と言えば、
「わたしも、キャビアはこのお嬢さんにつきあおう。だが、うんと小さなヒレ肉を生焼き(レアー)にしてベルネーズ・ソースと小イモをそえたのがいいな。お嬢さんがいちごを味わっているときは、こっちはちょっとフレンチ・ドレッシングをかけた『わになし』だ。どうだろう?」ボンドは、こう注文(オーダー)する。またその前に、キャビアと余分なトーストを給仕長へ言いつけ、
「いつでも厄介なのは、キャビアを充分にもってこさせるより、それにそえるトーストを充分にもってこさせることなんだ」そうおっしゃる。第11作“女王陛下の007号”ではトレーシー・ヴィツェンツォが、
「今夜自分の部屋で晩御飯に何を食べたと思う? クレブスシュヴェンツェ・ミット・ディルトゥンケよ。つまり、お米にクリームとイノンドの実で作ったソースをそえたえびのことよ。それから、レーテュッケン・ミット・ザーネ。これはのろじかの腰肉にクリーム・ソースをそえたもの。あんたの夕食よりごちそうでしょ?」電話でボンドに聞く。
「マスタードをぬったハム・サンドふたきれに、ハーパーのバーボンをオン・ザ・ロックで半パイント平らげたよ。バーボンのほうがハムよりうまかったね」これがボンドの答(以上の会話はすべて井上一夫訳)。食事も我慢して読んでいる時、このような文章が出てきたなら、もうおしまいだ。読書を中断してキッチンへ行くしかない。ただ、読んだ食べ物となるだけイメージの近い物を食べたくなるのが人情である。キッチンに欲しい物がない場合、わざわざマーケットまで出掛けることすらある……私の性格が卑(いや)しいのだろうか?
ボンド(ヨーロッパのヒーロー達)に比べると、アメリカのヒーロー達は地味な食生活を送ってるようだ。せいぜいスペンサーが料理に精を出すぐらいで、マイク・ハマーならアパートのキッチンでステーキを焼いたり、あり合わせの材料でチーズ・オムレツを作る程度、ペリー・メイスンなら秘書のデラ・ストリートをよく食事に誘うくせ、メニューは(すべてじゃなく)ほとんどステーキである。私もステーキは好きだが、マイク・ハマーやペリー・メイスンを読んであまり食欲はそそられない。
ドイツの代表的な(ウィーン生まれの)ベストセラー作家、J・M・ジンメルあたり、フレミングもまっ青! “白い国籍のスパイ”など、よだれを垂らさずして読めないスパイ小説(?)だ。邦題も英題の“モンテクリスト隠蔽(いんぺい)”も、いかにもサスペンス物らしい。ところが原題は“いつもキャビアという具合でなく"、タイトル通りペーソス溢れるサスペンスなのである。空腹の時は絶対お読みにならないよう忠告しておく。
“白い国籍のスパイ”で登場する
36のメニューの1例
私はこの本をスパイ小説として楽しむばかりでなく、“クック・ブック”としても活用している。というのは、料理好きの主人公が危機に陥るや、決まって料理を作ってそこから脱出するのだ。それが36のメニューとして作中に散りばめられており、そこだけ見れば“クック・ブック”として立派に役立つ。ただし、普及版ではメニューが省かれてるので、お買いになるならハード・カバーのほうが得だ(最初に出た普及版でメニューを省いた感覚は信じられない!)。
もっとも、ハード・カバーでも訳はもうひとつ、日本語版だけだと、どうも意味を理解しにくいため、私が料理に使う時は英語版と併せて利用している。だいたい(訳者のミスかタイプ・セットのミスかはともかく?)“MI6”が“M16”となっているのは、いただけない。諜報機関の名称のはずがアルファベットのIを数字の1と間違えば銃器の名称だ。と、文句を言いつつも、じつに面白い本であることは間違いない。
ボンド同様、先のマイク・ハマーやペリー・メイスンが本から映画やTVスクリーンで活躍するようになり、未だ健在な点は変わらないが、本を読んでもあまり食欲をそそられなかったヒーロー達は、私が記憶する限り映画化されて食事と係わる印象的なシーンは皆無である。その点、食通のイメージが強いボンドは、それをスクリーンへ引き継いでおり、これまで7人のボンドが活躍しているすべての映画の中には、食事と関連したシーンを結構思い出す。もっとも、それらのインパクトが弱いのは、やはり映画と小説が違う部分だろう。
映画は性格上、小説のような多岐にわたる細かい描写が不必要であり、それをやるとむしろ肝心な部分の焦点をボカす場合もある。1つのシーンを表現する時、小説の場合は読者自身がそのシーンを頭の中で描き、イメージの限界は各読者の想像力次第だ。その点、製作者が役者を使って描くシーンを見る映画は、そこの部分で想像力の必要がない。小説の長さではロバート・ラドラムやトム・クランシーが群を抜き、彼らの邦訳は文庫本だとまず2部か3部に分かれている。読む早さがどうあれ、これらの小説を休憩しないで一気に読み終えるのは不可能だ。しかし、いくら長い映画でも1本を見るための所要時間が数時間かかることはない。
ラドラムやクランシー小説が映画化された時、原作どおり作られたためしはなく、2時間前後の枠内でどこまで原作が活かせるかを考えてみると理由は明白だろう。逆に食べ物のシーンを文章で説明すれば、たとえ数秒のシーンでも説明文のほうは読むと30分かかるかもしれない。数秒間見せて読者へ何も感じさせないシーンが、文章で伝える場合、30分間読み進むうち読者の唾液腺を刺激したり、違いはそのプロセスにある。
食べ物が物語に演出効果を持つのは、小説だと作家の力量次第であるが、映画は製作者の腕や脚本より役者といえよう。美味そうな食べ方が演技力の1つなのは間違いなく、私が思い出す限り、美味そうな食べ方で印象的なシーンを演じる役者の大半はいわゆる名優だ。美味そうに食べる役者の1人、ショーン・コネリーだからボンドの映画化が成功したのだと、私は決めつけている。キャスリーン・ターナーやミッシェル・ファイファーも、その艶(いろ)っぽい食べ方がいい。外国のスターで浮かぶのはマルチェロ・マストロヤンニ、食べ物が絡むとやはりイタリア勢は強そうだ・・・・・・いろんなシーンを浮かべてみるとセクシーな役者が多いのは、食欲も性欲も人間の本質的な欲望である以上、それらが絡む演技はどこかしら共通性があるのだろう。
忘れないでいただきたいのは、エンターテインメントが虚構の世界であり、演技と現実は別物である。食欲や性欲絡みが得意だからといって、その役者の実生活は関係ない。たとえ実生活で得意な役者でも、演技が始まればシビアーだ。イメージは固い役者や柔らかいタイプと千差万別ながら、成功した連中が演技に対して真剣なのは当たり前として、みんな真面目な部分でも共通している。いいかげんそうなイメージの役者が実生活でもいいかげんだったら、最初から使う監督はいるまい。
紙面の関係上、ようやく映画の話へ移ったかと思いきや、もうエンディングだ。書き残したことがあるのは別の機会へ譲るとして、ともかくエンターテイメントの世界ほど傍で見るのと内情が違う商売は少なかろう。よほど好きでなければ、せいぜい華やかさに憧れる程度で留めておくのが無難である。反面、本当に好きな人なら1度やるとやめられないほど面白く、歌の文句じゃないけれど、
“No business like show business.”そう、ショウほど素敵な商売はないってわけだ!
横 井 康 和
|