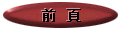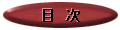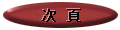映画と国境 (上)
ふと窓の外を見ると南カリフォルニアの陽光が眩しい。このカラッとした気候のまま、少なくとも今世紀(年内)は雨と無縁の生活が続きそうだ。しかし、太平洋を隔てた日本はもうすぐ梅雨の季節・・・・・・と、脳裏を掠(かす)めるのが、
「五月雨(さみだれ)を 集めて早し 最上川」
“ターザン”
芭蕉の時代は旧暦を使っており、旧暦で5月といえば新暦の6月に当たる。つまり、梅雨時の最上川の流れを描写したのが、この俳句だ。最上川を見たこともない私だが、雨期の濁流をイメージさせるのは、さすが芭蕉といえよう。このスピード感だと、荒れ狂う最上川へサーフボードに乗ったディズニー・アニメのターザンがいても違和感はない。そう思うのは私だけであろうか?
ともあれ、「五月雨」が「梅雨」を意味するのと同様、今でこそ5月上旬のカラッと晴れわたった日を指す「五月(さつき)晴れ」は、そもそも梅雨の晴れ間を意味した。毎日毎日、うっとおしい雨が続く合間に拝む太陽はありがたい。人生、悪いことが続けば、些細な事さえ嬉しくなる。映画はある意味で人生の縮図だ。当然ながら、そういったうっとおしさや嬉しさが描かれる場合、観客の受け止めかたは個々で違う。
個々で違う以上、国が変わればその差(ギャップ)はもっと広がる。梅雨のない国の人間が梅雨の映画を見ても、実感は伴わない。つまり、芭蕉の俳句に最上川でサーフィンをするターザンを思い浮かべるぐらいだから「芸術に国境がない」のは真理かもしれないが、受け止める側の人間と人間の間に国境が存在する限り、その逆もまた真理なのだ。
たとえば、日本で少なくアメリカで多い職種の典型は、なんといっても弁護士と精神分析医だろう。両者の極端な数の違いへ、それぞれの国民性が反映されている。古くはペリー・メイスン・シリーズのE・S・ガードナーから最近のジョン・グリシャムまで、弁護士あがりのベストセラー作家が多いアメリカと比べ、日本は(メジャー作家が)誰も思い浮かばない。また、O・J・シンプソン裁判を思い出すと、検察側のミスを徹底的に突っ込み、見事勝訴へ持ち込んだ弁護師団がスターであったのと比べ、同じマスコミに騒がれながらオーム教の裁判では、スター弁護士もドラマチックな展開で観客を沸かすこともなかった。
どっちがどうという問題はさておき、そこに本質的な違いがある。そこに見えない国境がある。日本でもガードナーの著書は数多く翻訳され、レイモンド・バー主演でTVシリーズ化された“ペリー・メイスン”が人気を博したのは確かだ。ところが、意味合いはかなり違う。グリシャム人気しかりで、かたやフィクション感覚なら、かたやノンフィクション感覚、つまり梅雨のある国とない国の人間が梅雨の映画を見ているようなものである。
“ペリー・メイスン”
来年は21世紀の幕開けであると同時、私個人にとってアメリカへ引っ越して四半世紀目、ちょうど日本とアメリカで半分づつ人生を送った勘定になる記念すべき年だ。そんな私が日本へ帰るたびに思うのは、いくら社会情勢が変わり、街並みが変わり、ファッションが変わり、茶髪族が増えようと、結局TVを見れば水戸黄門や忠臣蔵の世界は健在であり、何も変わっていない事実・・・・・・変わったと驚くより、変わったようで変わっていないことのほうが驚く。
ハリウッド映画の基本的な体質は「ハッピーエンド」だと思う。ある意味で、この体質へ今や世界で唯一の「スーパーパワー」として君臨するアメリカのパワーが秘められている。そして、この体質で展開する法廷ドラマを想定した場合、日本人は日本人の体質でしか受け止めない。ほぼ勝目がない裁判を、ペリー・メイスンは最後に覆し、正義が勝つ。あるいは、クライマックスで登場する「水戸家」のご紋が入った印籠、はたまた立ち上がり上半身を肌けた裁判官の背中へは「桜吹雪」の刺青・・・・・・最後の土壇場で「決め」を出して正義が勝つパターンは、日本も同じだ。
しかし、日本人が「決め」を出したペリー・メイスンへ拍手を送っても、その逆は難しい。「これが見えぬか!」のひと言でインパクトを与えられる観客は限定される。それが通じるのは、前提となる知識を持つ一部の者だけで、この一部の者が大半を占める日本国内にいる限り、自分たちを外国と比較する必要はない。その典型が日本の政治家だろう。また、海外へ進出した日本企業は、裁判沙汰と直面した時、あまりにも脆(もろ)いのが、よくわかる。
一方、アメリカはアメリカで異常なほど弁護士が多く、訴訟は日常茶飯事というのも考えものだ。モデルとなったヨーロッパの制度でさえ、もっとおとなしい。ただ、アメリカがいろいろな人種から成る以上、裁判で物事を解決せざるえない部分はあるのだろう。精神分析医が多いのも、それだけアメリカ人は自分のアイデンティティーを求めるからだ。単一民族で歴史の長い国なら、その文化が良くも悪くも拠所(よりどころ)になる。「自分は誰で、どこから来て、どこへ行くのか?」と、考えなくて済む。
アメリカの場合、古くはアルフレッド・ヒッチコック監督作“スペルバウンド(1945年)”をはじめとして、ジル・クレイバーフ、アラン・ベーツ主演作“未婚の女(1978年)"、ロバート・レッドフォードの初監督作“普通の人々(1980年)"、リチャード・ドレファス、バーバラ・ストレイザンド主演作“ナッツ(1987年)”などのヒット映画ばかりでなく、“翔ぶのが怖い”といったベストセラー小説まで、精神分析をテーマにした作品は多い。
日本でも話題になったこれらの作品だが、その受け止めかたは法廷ドラマ以上の差(ギャップ)がありそうだ。たとえば“普通の・・・”で、最後に自分自身を見つめ直すため家族を捨ててまで旅立つ母親は、多くの日本人へ「重さ」を感じさせたと思う。「あすこまで厳しくならなくても・・・・・・」が、一般的な印象だったのではないだろうか? ところが、角度を変えて見れば、あの母親の姿勢は男女平等の精神を支え、また2人に1人の女性が離婚経験者というアメリカの現状へ結びつく。
“普通の人々”
世間には妥協を許さず離婚した結果、寂しい老後を送る夫婦もいれば、経済的な理由から妥協した結果、老後、仲むつまじくなる夫婦もいる。妥協したほうがいいのか、あるいはしないほうがいいのか、こればっかりは誰にも言えない。また、映画に国境があろうとなかろうと、そのこと自体はどうでもいい。それを認識することで自分の世界が広がるかどうか、あるいは結婚生活を妥協しようとしまいとそれで納得できる人生を送れるかどうかが重要なのである。
そして、映画に国境があるとすれば、それらの映画は国境の向こうの知らない世界へわれわれを誘(いざな)う。いわば梅雨のない国の人間も梅雨を疑似体験できるのが映画だ。極端な例では、かつてアメリカ留学を控えた落合信彦が、弁当持参で映画館へ通いながら英語を勉強したと、自らの著書に書いていた。
国境といえば、私の趣味である銃器も、その違いを感じさせる1つだ。自衛隊の幹部が民間人(シビリアン)から借りた猟銃を射撃場で撃ち、大騒ぎする感性は、多くの州で火器が合法的なアメリカから見ると理解しがたい部分だろう。しかし、そういった感性は日本人の美徳へも通じる。じっさい、それが犯罪軽減に貢献している限り、アメリカ人だって見習えばいい。
ただ、先のオウム真理教「サリン事件」あたりを境に、対外的な日本のイメージは以前ほど「平和な国」でもなくなった。日本人自身が最近は新聞で発砲事件があったという記事を見て、あまり関心を示さなくなっている。せいぜい「またか!」という程度だ。こうした状況下では、むしろ自衛隊員が自衛隊の射撃場で銃を撃ってニュースになる状況を心配してしまう。
日本は集団指向(グループ・ダイナミックス)の国だ。何事にも波があり、集団でパワーを発揮できる間は強力な反面、足並みが揃わない時は国民総無責任となる。銃が持てないのは法律で禁止されているという考え方だと、持てる国へ行けば根本的な概念を覆されるが、なぜ持てないかを個々の意志として認識する限り、どこに行っても影響されることはない。そして、日本人をどちらかのパターンへ2分すれば大半が前者のパターンなのだ。だからこそ集団でパワーを発揮できる。
アメリカで暮らす日本人ガン・パーソン(銃愛好家)の目で見ただけで、些細なニュースが気になるぐらいだから、お互い自分の国しか知らない者同士が国境を隔てて理解し合うのは大変なことだ。そのギャップを映画が少しでも埋めるとしたら、これはもう立派に世界平和へ貢献している。外交官がいくら努力しても、外国の一般大衆に自分の国を理解させるのは難しい。それが出来る可能性を映画は秘めており、そのパワーが映画の素晴らしさだ。
知らない世界を体験できるという意味では小説も映画と変わらない。私自身、物を書く上で読者が何かを発見してくれれば本望なのである。ロサンゼルスに住む元ミュージシャンの日本人探偵物語を書きながら思うことは、そこから何かを感じた読者が渡米した時、少しでも役立ってほしい・・・・・・だからこそ、射撃の描写なら一般の日本人が馴染まない感触を少しでも伝えたくて書く。
たとえば、シューティング・レンジで拳銃を撃つ時、耳栓(イヤー・プロテクター)を着けていても、轟音(銃声)は耳だけじゃなく身体が受け止める。ところが、全身で銃声を聞きながら、妙な静けさを覚えるから面白い。冷たさの中に感じる長閑(のどか)な風情、そこまでリラックスできると弾は標的(ターゲット)の中心へ集まってくる。そんな時の気分が、
「ぬばたまの 光飛び散る 射的場に
しず心なく 煙(けぶり)ただよふ」おそまつ! (続く)
横 井 康 和