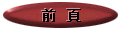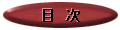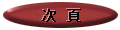映画と国境 (下)
映画を含むいわゆる芸術一般に国境があるかないかはさておき、少なくとも言葉が違えば、映画の題名1つとってもニュアンスは違う。たとえば日本の場合、外国映画の原題が邦題と置き換えられる。この邦題は大きく分けて、ただ原題をカタカナで綴ったものと意訳したもの、そしてまったく違ったものの3パターンがあり、どのパターンにせよ原題のニュアンスと変わることは避けられない。
つまり、そこへ1本の国境線が存在するばかりか、原題は同じでも時代が違うと邦題まで変わるあたりは、時代感覚に一貫性がない日本人の国民性と通じる部分も窺(うかが)えそうだ。平成か西暦かどちらを使うべきか否かは別問題として、ハリウッド映画のリメイク版とオリジナル版の邦題が往々にして違う理由を少しばかり考えてみよう。
以前、「映画と音楽」で触れたとおり、オリジナル版“華麗なる賭”のリメイク版は“トーマス・クラウン・アフェアー”と、原題をカタカナで綴るパターンへ変更された。しかし、配給会社が変更という意識を持っていたとは思わない。むしろ、原題そのままだからオリジナル版の時以上、原題に忠実かつ、こちらのほうが今の時代は「カッコいい」という判断があったのではないだろうか?
これを裏返せば、同じタイトル故、リメイク版しか知らない若いアメリカ人がオリジナル版と遭遇する機会(チャンス)を日本の若者は持たず、映画史としての一貫性を失くす。また、“トーマス・・・”というタイトルの意味合いがわかって受け止める日本人は“華麗・・・”という言葉を理解する日本人より圧倒的に少ないはずだ。ということは、タイトルの意味合いより言葉の響きだけが選択の理由とさえ勘ぐれる。
いっぽう、最近でも“グッドナイト・ムーン”や“17歳のカルテ”のような極端に原題と違う例は少なくない。ただ、なぜ「継母(ステップマム)」が“グッドナイト・・・”なのか理解に苦しむ反面、「情緒不安定な娘(ガール・イントラプテッド)」は内容からして“17歳・・・”がピッタリだ。
話は変わるが、半年前に拙著「ハリウッドで成功する方法」が出版された直後、帰国して朝日新聞出版の編集長と会った。「ハリウッド・・・」は編集長自らの担当ということで出版までの半年近いやりとりも気合いが入り、ようやく形になった直後の対面である。その時、編集長は刷り上がったばかりの数冊を入れた紙バッグをくれたのだが、中には彼が係わった他の本も何冊か入っており、別れた後で紙バッグの中を覗(のぞ)いてみれば、私好みであろうという配慮から選択されたことは明白であった。
紙バッグを覗(のぞ)き、表紙からパソコンと関係のある漫画かなと思った程度で、さして興味を引かれなかったのがサトウサンペイ著「パソコンのパの字から」と題した1冊だ。しかし、後で開いてみると予想は見事に裏切られた。いわばパソコンの初心者が、これさえ読めば、なんとか使いこなせるようになる「ハウ・トゥー」ものの一種で、内容は素晴らしい。
年輩でコンピュータと無縁だった人間へ挑戦させて、その体験談からウィンドウズ98の使い方をわかりやすく解説してゆく企画(コンセプト)が、サトウサンペイというキャラクターを獲て見事に開花したのであろう。映画なら、さしずめユニークな企画へハマリ役のキャスティングで予想以上の結果を生んだというところか?・・・・・・こう言えば、予想したからこそ企画を進めたのだと、朝日のスタッフにはお叱りを受けるかもしれないが!
ともあれ、「パソコンの・・・」は初心者へ本当に役立つお薦めの1冊であると同時、マイクロソフト社の日本人スタッフをはじめ、コンピュータのソフトを開発する連中がぜひ読んでほしい。コンピュータの世界とて国境はあり、カタカナ化した英語を使おうが失くなるどころか、むしろ本質を見失うだけだ。その点、サトウサンペイの意見は痛快である。
「ハリウッド最前線」を開設以来5年近く、私自身が「-Windows- チューンアップ・テクニック」のコラムを書きながら文句の多いことは、ご存じの読者もおられるだろう。Windows95以来、半角になったり全角に戻ったりするカタカナ表示へ不満を抱き、昔から「ユティリティ」で通してきた人間として、最近コンピュータ業界で定着しつつある「ユーティリティ」の訳が気に入らない。
もっと単純な疑問で、「画面」や「背景」なら年齢は関係なく誰でもわかるものを、日本のマイクロソフト社が「デスクトップ」や「壁紙」という用語を採用したのはなぜ?・・・・・・もっとも、自分自身がコンピュータを使う上で、こうした諸々の疑問点は支障をきたさず、文句を言うだけ言って忘れてしまうのが常だった。しかし、「パソコンの・・・」を読んで再認識したのは、日本の高齢層へコンピュータが馴染みにくい問題は、このあたりに根元がありそうだ。
プリンターの仕様書を読んでチンプンカンプンのサトウサンペイは、各用語へ馴染みのある日本語を当てはめると理解できたそうだが、そこに挙げられた彼自身のイラスト例などプリンターの製造業者こそ見習えばいい。結果、業績は伸び、コンピュータの普及へ貢献できる確率が高いのに、現状は不思議と英語のカタカナ綴りがまかりとおる業界なのである。
マイクロソフト社のオフィスに至っては、メニューの表示がカタカナどころか英語そのままだ。ここまでくると私など性格上、英語の表示すべてを、せめてカタカナ綴りへ書き直す。それだけ文句は言いながら、オリジナルが巨額を投じて開発されただけの性能を秘めるソフトとなれば、捨ててはおけない。じっさい、10年以上、愛用し続けた一太郎でさえ、このところATOK(一太郎を支える日本語機能)が活躍する以外、影は薄くなってきた。
話を戻し、メーカーがどこであれ、なぜコンピュータ業界は「背景」でなく「壁紙(ウォールペーパー)」というのかを考えると、日本の配給会社がリメイク版を“華麗・・・”でなく“トーマス・・・”と題した疑問へ重なってゆく。そして、安易な英語のカタカナ綴りは国境を失くすようで、意味合いが曖昧になるだけ現実は逆なのだ。
かつて“サントロペ・ブルース”の邦題を“赤と青のブルース”と名づけた配給会社のセンスが時代遅れかどうかより、はっきり言えることは、それぐらいのセンスがあってこそ国境は失くせる一方、邦題が“サントロペ・・・”のままでは、まず期待できそうもない。自分自身が認識できてこそ、他人を認識できるのであり、ただ眺めているだけでは相手との距離が開くばかりだ。個人単位から国単位へ置き換えるなら、国境線は太くなるばかりである。
日本人の感性なら作れてもよさそうな“ザ・シックスス・センス”といった名画が、同じ東洋でもインド人の手によるのは、邦題が“シックス・センス”とくれば、さもあらん! なぜ、“第六感”とか、それを感じさせる邦題をつけなかったのだろう? まして、日本人得意の冠詞や定冠詞、あるいは三単現や複数形の「s」から場合によって「th」すら省くカタカナ綴りが、結果として「6番目の感覚」の意味合いを「6つの感覚」へ変えてしまった。その無神経さは、やはり納得できない。
しかし、いったん封切られた以上、どのようなタイトルであろうと、それが邦題なのだと割り切って、わが「ハリウッド最前線」の原稿を書くいっぽう、ふと思い浮かぶのはロカビリー全盛時代、多くの若者が口ずさんだ「ユエンナツバラハウンドッグ」・・・・・・その中で「お前は野良犬にすぎない(You ain't nothing but hound dog)」という意味を理解していた者がどれだけいたかは疑問だ。
戦後、日本の英語教育が進んだおかげで、フォーク・ブームからビートルズ以降の世代はもう少し歌詞の内容を理解しようとする姿勢があった。この世代から見れば、「ユエン・・・」と歌っていた前の世代は無邪気に映る。もはや「アイ・アンダスタンド・電気スタンド」が面白くも可笑しくもない時代へ移り変わり、海外旅行は日本人にとって当たり前、これが世界では当たり前でない認識がない。つまり、本質は現在も変わらず、知らず知らず国境を築いているわけだ。それ故、世界へソニーやホンダを送り出した日本も、個人レベルのハリウッド進出では香港やインドに遅れをとった。
ただ、個人レベルの話なら香港やインドと比較しても始まらず、私がハリウッドから映画情報を発信する1人の日本人映画ファンとして言いたいことは、いまの日本の若い世代へもっと自分を知り、もっと自信を持ってほしい。将来、ハリウッドで日本人のスター俳優やスター監督が生まれるとしたら、第1歩はそこからしか始まらないのである。
横 井 康 和