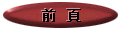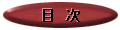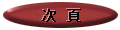映画と弁護士
弁護士と精神分析医は日本に少なくアメリカに多い職種の典型だと、以前「映画と国境」で書いた。つまり、それだけ裁判沙汰や精神分析療法が一般のアメリカ人の日常生活へ浸透していることを意味する。その結果はアメリカの映画、TV番組、小説などに反映されないほうが、むしろ不自然だ。
言い換えると、たとえばアメリカ人ほど裁判と馴染みのない一般の日本人は、裁判絡みのハリウッド映画を見ても、ある程度までの実感しか伴わない。いっぽう、陪審員への勧誘状を役所から定期的に受け取るアメリカ人は
日本人の私でさえ、ハリウッドで27年と数ケ月暮らすううち、何度勧誘状を受け取ったことか!たとえ自ら経験していなくとも、無意識のうち陪審制度がどのように機能するものなのか理解はあるだろう。今年(2002年度)のアカデミー賞で6部門を制覇(せいは)した「シカゴ」、そして間もなく公開を控えた映画「ニューオーリンズ・トライアル」や原作となったジョン・グリシャムのベストセラー小説「陪審評決」がいい例で、前者の場合はリチャード・ギア演じる辣腕(らつわん)弁護士(写真左)が印象的だった。殺人犯である女性被告(キャサリン・ゼタ・ジョーンズ)を尋問する彼は、記者たちを操り人形のごとく誘導して同情的な記事を書かせたり巧みな情報操作で陪審員の心を動かし、ついに無罪判決を勝ち取るのだが、脚色されたドラマの本質は現実の陪審制度そのものである。
後者の場合も同じく、原作の小説であれ裁判の内容が変更された映画であれ基本(コンセプト)は巨額が絡む企業裁判での陪審員の影響力だ。当然ながら、被告側の弁護士は自分たちへ有利な陪審員を選択すべく候補者の緻密な調査を進めてゆく。ところが、この物語では陪審員の中に潜りこんで判決を操作しようと企む上手が登場する。まず、冒頭ではジーン・ハックマン演じる悪徳弁護士(写真右)が公判に備え、持てる組織力を総動員して陪審員候補者全員を調べ上げ、それらの情報をパネルへ並べて作戦を練ってゆく。
シカゴ ニューオーリンズ・トライアル こうして検討に検討を重ね、自分たちへ有利な陪審員を揃えるといってもピンとこないかたのため、このプロセスをもう少し具体的に説明してみよう。たとえば白人原告の裁判で黒人被告を弁護する場合、一般論としては黒人の陪審員が多ければ多いほど有利だ。したがって、じっさいは陪審員の選択の前に、どの管轄区で裁判を開けるかという問題もある。ともあれ、この白人を関東人、黒人を関西人と置き換えて考えてほしい。
関西人の被告を弁護する以上、関西人の陪審員が多いほど同情票を集めやすく、弁護士としては関西で裁判を開きたいところだが、この点は選択の余地がないか、あってもかなり制約される。可能な範囲内で有利な場所を選択する努力はするだけしたとして、いよいよ裁判の開始だ。しかし、始まったからといって、すぐ陪審員が登場するわけではない。まず判事は原告と被告が提出した動議書(訴状)を検討しながら審議の論点を絞ってゆく。この段階では原告と被告から提出される動議書のやり取りが中心となる。
こうして裁判で審議する論点が定まれば、次はそれを裏付ける事実、つまり証拠集めだ。原告、被告それぞれが証人から宣誓証言を取ったりするのはこの段階であり、それらの証拠の中から判事が審議で使っていいものといけないものを振り分け、ようやく審議に入る。陪審員はここで初めて登場するわけだが、必ずしも彼らの参加は求められない。原告、被告がどちらも審議を判事へ委(ゆだ)ね、陪審員抜きの裁判を求めた場合に限って、判決を下すのは判事の裁量だ。
ただでさえ弁護士だけが得をする結果を招きかねない裁判好きのアメリカ人でも、陪審員の参加は裁判費用と時間の増加を意味し、それだけ原告と被告の負担が増すぐらいはわかっている。したがって、小規模な裁判なら陪審員を使わない裁判も多い。いっぽう、裁判の規模が大きくなればなるほど、弁護士は自分の腕一つで判決を左右する余地が残された陪審制度を好む。
陪審員の参加する裁判では先の「ニューオーリンズ・・・」を見るまでもなく、その選択からして重要だ。たとえば、先ほどの関西人についた弁護士が東京で裁判を始めたとする。論点は絞られ、証拠集めの段階が終わるのと平行し、彼は陪審員候補者全員をひととおり調べ上げておく。審議へ入る準備も整い、いざ陪審員の選択が始まるや、それらの調査結果は意味を持つ。陪審員候補者が関西人を嫌うかどうか前もってわかっていれば、嫌う候補者を排除できる。
順序として、原告と被告の弁護士は12人の陪審員が揃うまで候補者を1人づつ尋問してゆく。先入観や偏見を持った候補者を除外するためのプロセスだ。たとえば、事前の調査で関西人を嫌うとわかっている候補者なら弁護士は、
「この裁判の被告が関西人だと知っていましたか?」ここで判事や原告側の弁護士がどう出ようと別問題で、ひとまず私のポイントはおわかりいただけたと思う。じっさい私の知り合いで、関西の青いネギを見て関西人がケチだと思った関東人ばかりか、関東の白いネギを見て、関東人が貧しいと思った関西人もいる。ちょっとした習慣の違いでさえ、時には相手の食文化や経済状況を理解する上で障害となりかねない。そういった些細なことをどう活かせるかが弁護士として腕の見せ所なのだ。
「いいえ」
「関西人をどう思いますか? 関西人へ何か偏見をお持ちですか?」
「そんなことはありません」
「なるほど・・・・・・」
と、一瞬間をおいた弁護士が続けて、
「ところで、○○にある蕎麦屋××はご存じですね?」
「はい、うちの近くだからよく行きます」
「××の主人と話したことがありますか?」
「そりゃ、馴染みの店だし世間話はしょっちゅうします」
「その世間話で、あなたが『関西人はケチだから青いネギを食う』とおっしゃった記憶がありますか?」
「さあ・・・・・・はっきりした記憶はありませんが、もしかしたらそんなことを言ったかもしれません」
「では、それがあなたのお考えだと解釈して間違いありませんね?」
「そこまで大袈裟な気持ちはありませんよ」
「軽い気持ちにせよ、もしあなたがそうおっしゃったとしたら教えて下さい。あなたは関西で関東のようなネギへ土をかぶせて育てる習慣がないことは、ご存じでしたか?」
「いいえ」
「つまり、関西で白いネギを食べないのが当たり前だと知らず、青い部分まで食べるほど彼らはケチだと判断されたわけだ?」
「そんなつもりで言ったわけじゃ・・・・・・」
相手が言い終わるまで待たず、判事を振り返った弁護士は、
「裁判長、明らかな偏見が認められますので、この候補者を陪審員から外すようお願いいたします」極端な話、陪審員を外す理由付としてネギそのものの妥当性は重要でなく、ネギへどこまで説得性を持たせられるかという弁護士の力量が決め手となり、ネギを判事に認めさせた弁護士をアメリカでは有能という。12人の陪審員が揃っていざ審議へ入る段階で、この力量はさらに発揮される。たとえ判事なら疑問の余地なく原告の主張が正しいと判断するようなケースも、決めるのは陪審員だ。もし彼らが原告は間違っていると判断すれば、判事はそう判決を下すしかない。弁護士が陪審員候補の偏見を判事へ認めさせることと比べ、陪審員を説得するのはまだ楽だろう。
陪審員が全員関東人であったにせよ、彼らへ悪い関西人などいるはずはないと思いこませたら、その弁護士にとって勝訴が約束されたようなものだ。もちろん原告側の弁護士とて無能ではないから、被告側の弁護士が陪審員を誘導しようとするのを黙って見過ごすわけはない。陪審員を説得できるかどうかで勝負が決まるのは彼らの立場も同じで、両者がお互いの隙を窺いながら法廷という舞台で陪審員という観客を前にドラマを繰り広げる。
少しでも相手が隙を見せるや、そこを突いてゆく。じっさい「O・J・シンプソン裁判」で原告の検察側はあそこまで被告のシンプソンを追い詰めながら、たった1つのミスが致命傷となった事実を思い出してほしい。いったん悪い関西人などいるはずはないと思いかけた陪審員を原告側の弁護士が現実へ引き戻せても、何かミスを犯せば被告側の弁護士はそれを反撃のチャンスに利用する。「O・J・シンプソン裁判」の最後のドンデン返しを見れば、法廷物がハリウッドで映画のネタとして魅力的なのは無理もない。
良しも悪しきも法廷内外での弁護士の駆け引きが裁判の行方を大きく左右するアメリカの現状は、ふだん新聞やTVのニュースを見ていれば嫌でも目につく。去年、L・A(ロサンゼルス)市の南にあるイングルウッドで手錠をかけられた黒人少年を殴り、暴行罪に問われた白人警察官の裁判が先月行われた時は、陪審員の意見が分かれて評決は成立しなかった。その陪審員というのが12人のうち黒人はわずか1人であり、これまた弁護士の手柄というわけである。
横 井 康 和