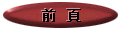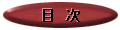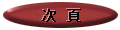映画と世界 (中)
L・A(ロサンゼルス)の知り合いで建築家の先生がいる。その日本人の先生は焼き鳥の軟骨が好物で、ふだんはホームシックと無縁でも軟骨に郷愁の念を覚えることがあるそうだ。同じく、私は世界のどこであろうと自分のいるところが日本だと思っているから、人や物へ想いをやっても、いわゆるホームシックにはかかりようがない。
「タイタニック」
もっとスケールを大きく考えると、我々のホームは世界であり、宇宙へ出ない限りホームシックが存在しない理屈となる。つまり、日本から出ない場合と結果的に変わらなくなってしまう。日本と世界は相対的な関係である以上、世界で活躍する日本人を「世界の××」と呼ぶ発想も、世界へ視野を広げると消滅し、代わって「日本の○○」が意味を持つ。
最近は日本の監督や俳優が海外に進出しても珍しくはなくなった。しかし、進出が世界的な成功へ直結するわけでもなく、「世界の××」と呼ばれるうちはまだまだだ。じっさい誰もが「世界の××」と認める人間なら、わざわざ呼称へ解説はいるまい。それが「日本の○○」と呼ばれるようになれば、いよいよ本物の仲間入りである。
今のところ世界の映画で一番稼いでいるのは「タイタニック(1997年)」だが、同じ日本のマスコミでもそのジェームズ・キャメロン監督やスティーブン・スピルバーグを「世界のキャメロン」とか「世界のスピルバーグ」と呼んだりはしない。国籍がどうあれ、そこまでの実績を築いた監督は実績があればあるほど曖昧な肩書は似合わなくなってゆく。
世界に憧れる限り、どれだけがんばろうが、そこへ到達できないのは当然だ。そして、到達した同胞を憧れの目で見たのが「世界の××」だとしたら、その表現に実体は伴なわない。日本のマスコミが、まさしくこのパターンである。ハリウッド映画の監督へ起用された中田秀夫は「世界のナカタ」、ハリウッドで監督作が引き続いてヒットを飛ばしたチャン・イーモウたるや「世界の巨匠」と呼ぶ。こんなメンタリティーでは、世界へ通用する日本の映画祭を目指すなら、ぜったい避けるべき「日本アカデミー賞」の発想に至ったのもしかたがなかろう。
「鉄道員(ぽっぽや)」
世界の真似から始めるのは常套手段の1つだが、憧れや真似の範疇を超えないと世界レベルへ届く第1歩も踏み出せず、芸術などオリジナリティーを問われる創作分野では、たとえば「日本アカデミー賞」と名付けた時点で中身がどれだけ立派な映画祭でも二流止まりの運命を決定付けられる。自動車レースの「日本グランプリ」とはわけが違うのだ。
もし同じ日本アカデミー賞協会主催の映画祭を「東京国際映画祭」や、いっそのこと「サンダンス」の向こうを張って「サンライズ映画祭」とでも名付けておけば、その選考ポリシー如何では世界へ影響を及ぼす映画祭に成長し、それだけの権威が伴なえば、「東京国際映画祭入選」や「サンライズ入選」は売り文句として立派な商業価値を持つ。いっぽう「日本アカデミー賞」の発想が映画祭の価値を高めるどころか、こういった将来の可能性を限定してしまうと、なぜわからないのであろうか?
ふとそんな疑問を持ったのは、日本からハリウッドへ引っ越して2年後の1978年春、第1回日本アカデミー賞が開かれると知った時である。以来、今年で第28回を迎え、これまでの作品賞を振り返って思うのは、意外と選択基準がしっかりしており、「さすが日本アカデミー賞に入選した作品」という印象を与えるだけ、いよいよ「日本アカデミー賞」の名が障害となってきたのは惜しい。
「ロード・オブ・
ザ・リング/
王の帰還」そもそも「東京国際映画祭」など二番煎じでない名称だったとしたら、たぶん他の映画祭同様、そこでどのような映画や俳優その他が選考されたか、私自身、最低限の興味は引かれていたと思うが、「日本アカデミー賞」の名前のおかげで、つい最近まではその存在すら忘れていた。それも、私がハリウッドで住むせいばかりといいきれないのだ。
日本のマスコミが意味もなく「世界の××」という逆で、アメリカのマスコミは何かといえば「オスカー××」といい、その一言が持つ意味合いは深い。「オスカー監督がオスカー俳優2人を起用した映画」と聞けば、映画ファンの期待は膨らみ、そこへアカデミー賞の長い歴史や背景が凝縮されている。こうした裏付けなくしてアカデミー賞は権威を持たず、フランチャイズが可能だとすればせいぜい名前までだろう。
たとえ伝統はフランチャイズが無理でも、「日本アカデミー賞」と名付けた以上、狙いはそこしか考えられない。仮にその狙いが当たった場合の兆候は、まず「日本アカデミー賞で・・・」という売り文句へ現われるはずが、現状は受賞を商売に利用するなど夢のまた夢・・・・・・たとえば、高倉健主演作「鉄道員(ぽっぽや)(1999年)」を見ればいい。
昔は劇場の興行収益へ頼っていた映画も、DVDやビデオを含む二次市場が多様化した現在では、それなりの戦略が要求される。ごく一般的なパターンとしては、DVDへ撮影中の裏話(エピソード)を加えたり、劇場公開後、有名な映画祭で受賞したとしたら、当然ながら二次市場へ出す時の宣伝文句に活かす。ハリウッド在住の私が見た「鉄道員(ぽっぽや)」しかりで、高倉健のモントリオール映画祭主演男優賞受賞作というコメントから始まる。
「たそがれ清兵衛」
「へ〜え!」と思いつつ忘れていたのを、前回のコラムでこの映画を取り上げる際、モントリオール映画祭の記憶に間違いはないか確かめようとして初めてキネマ旬報賞から日本アカデミー賞9部門へ至る受賞作でもあると知った。ふつうならDVDの発売元が受賞した各映画祭を列挙しそうなところを、モントリオール映画祭しか紹介しないとなれば、他の映画祭はどうでもいいどころか邪魔だと判断している以外に解釈のしようがない。
アメリカで上映された山田洋二監督作「Twilight Samurai」こと「たそがれ清兵衛(2002年)」を見てギネス・ブックの記録に残る「寅さんシリーズ」の監督だけのことはあると納得し、「忠臣蔵外伝 四谷怪談(1994年)」もやはり監督が深作欣二と聞いて見たくなった。見た時点では「鉄道員(ぽっぽや)」同様、これらが日本アカデミー賞受賞作であるなど考えすら及ばず、他の邦画へ受賞作という理由で目を向けるようになったのは、つい最近なのだ。
日本アカデミー賞受賞作を振り返って、まず気がつく本家との違いは、そこへ「千と千尋の神隠し(2001年)」や「もののけ姫(1997年)」といったアニメーション映画が同列に並んでいる。「千と千尋の神隠し」と「もののけ姫」はアメリカでも「Sprinted Away」と「Pricrss Mononoke」のタイトルでDVDがそこそこ売れているばかりか、後者は本家アカデミー賞のアニメ部門でオスカーさえ勝ち取った。今やアニメは輸出産業を担(にな)う日本の代表選手と考えれば自然の成り行きかもしれないが、アニメを作品賞部門へ含む結果、やはりマイナーな印象は拭えない。
「Mr.インクレディブル」
極端にいうと宮崎駿の「千と千尋の神隠し」や「もののけ姫」を実写で映像化したのが、去年の本家アカデミー作品賞受賞作「ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還(2003年)」ではないだろうか? そうすると、前者がそこまでの手間を省きアニメで誤魔化した映画のような気もしてくる。と同時、なおかつ作品賞へ相応しい内容ならアニメを同次元で捉える日本の選択基準はオリジナリティーという解釈が成り立つ。
そこでハリウッドのアニメはといえば、今年の本家アカデミー賞でアニメ部門を競った「Mr.インクレディブル(2004年)」や「シュレック2(2004年)」のようなアニメでしか表現できない(つまり実写で映像化すると持ち味が活かせない)内容であり、たとえオスカーを取ろうが全米の一部でしか公開されなかった「もののけ姫」とは興行成績が雲泥の差なのだ(オスカーこそ「Mr.インクレディブル」へ譲った「シュレック2」ながら興行成績たるや「タイタニック」、「スターウォーズ(1977年)」に次ぐ映画史上堂々第3位)。その点、同じ宮崎作でも「ハウルの動く城(2004年)」あたりはアニメならではの上手さが活かされており、先月ディズニーの配給で全米公開されて以来、なかなかの奮闘振りである。
最近はアメリカで日本のアニメが「コミック(Comic)」から独立して「漫画(Manga)」というジャンルへ区別されるまでになったのはいいが、その基本的なイメージは一連の宮崎作で代表される少女漫画の世界なのだ。日本の誇るアニメが実写へ活かされた「鉄人28号(2004年)」などは、実写でありながらアニメの「Mr.インクレディブル」や「シュレック2」より漫画に見えてしまう。何よりも(「ハウル・・・」や日本からの輸出映画で一番稼いだ「ポケモン・シリーズ」と違って)アメリカでのメジャー・ヒットを考えられない「千と千尋の神隠し」や「もののけ姫」が、日本だとあそこまで当たる落差は激しい。もちろん、国民性の違いといえば、それまでの話だ。
ただ、在米日本人の目から見ると、そういった落差が自覚できるのとできないのでは、世界へ通用する才能を伸ばすか殺すかの分かれ道のような気がする。あるいは、自覚できない結果がかつての貿易摩擦を生み、相も変わらぬ領土問題や教科書問題に現われているのではないだろうか? ロシヤが北方領土を手放そうとしないのは、冬の間、それが太平洋へのアクセスに欠かせないという軍事的な(つまり国家の死活問題だという)理由を考えれば当然だろう。
教科書で教えなくていけないのは、国と国とが所有権を巡って対立する領土の歴史的な背景から日本の正当性を説くのではなく、なぜ対立し、最後の決め手となるのが力関係だと理解させることだ。自分本位の勝手な解釈で主張した正当性など相手は聞く耳を持たない以上、生徒が腹を括らないと今ある領土だって将来は失くすかもしれず、そういう認識を持った上なら韓国や香港の映画が日本で流行る最近の傾向は素晴らしい。
「半落ち」
もっとも、日本人の認識がどうあれ、流行る韓国や香港映画は人間ドラマへそれだけのシビアーな国情が反映されており、その現実的なインパクトと日本映画を代表するアニメを比べた場合、いたって平和な「千と千尋の神隠し」や「もののけ姫」の感動は海外市場で大人の客層をつかめないわけだ。こうしたアニメが作品賞に選ばれる日本アカデミー賞でもう1つの特徴は、ノミネート作へ「後ろ向きのパワー(Negative Energy)」を持つ映画が混ざっている。芸術性を掘り下げれば当たり前のことかもしれない。しかし、本家アカデミー賞の場合、ノミネートされる以上、たとえテーマは冥(くら)い映画であろうと必ず「前向きのパワー(Positive Energy)」を持つ。
そもそも私がハリウッド映画を好きなのは、アメリカの国民性を反映してか、ハッピーエンドが基本パターンだからである。つまり、「前向きのパワー(Positive Energy)」だ。いっぽう、今年の日本アカデミー作品賞ノミネート作「血と骨(2004年)」などは「後ろ向きのパワー(Negative Energy)」しか伝わってこない。いわゆる「行間を読むコミニケーション」に馴染む日本の観客なら深さを感じるのだと思うが、同じ日本人でありながら私自身はこの映画がいったい何を言いたいのか理解に苦しむ。
「血と骨」と競って作品賞を受賞した「半落ち(2003年)」は、いくら冥(くら)くても「前向きのパワー(Positive Energy)」なので、こちらが受賞しなかったとしたら不思議な話である。その点、本家アカデミー賞のほうは今年の受賞作「ミリオン・ダラー・ベイビー(2004年)」であれ対抗馬の「アビエイター(2004年)」であれ、ノミネートされる以上、毎年「後ろ向きのパワー(Negative Energy)」を感じる映画がまずないといっていい。
日頃ハリウッドから日本を眺めながら思うことを書いてきたのも、そんな「前向きのパワー(Positive Energy)」を持ってほしいからこそだ。ハリウッドを目指すかたへ少しでも参考になればと、独断と偏見は承知の上で文句を連ねてきたが、要は業界がなんであれ世界へ出て活躍しながら焼き鳥を懐かしむのも一つの人生なら、日本で焼き鳥を味わいながら世界を夢見るのも1つの人生、どっちがどっちという問題ではなく、あなた自身の選択(チョイス)がすべてなのである。(続く)
横 井 康 和