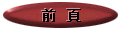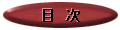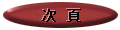映画と世界 (下)
先日、仕事絡みでの参考資料として日本の某TV番組ビデオを見る機会があった。そのTV番組というのは邦画の海外進出がテーマであり、たまたま前回のエッセイ「映画と世界 (中)」を書き終えたばかりの私は、相通じる内容へ参考資料としてよりも興味を引かれた。ナレーターの役所広司が番組中程で「タイタニック(1997年)」を切り口に語りだすあたりは、前回のエッセイで私も使った手なので、どうしてもその先の展開が気になる。
「七人の侍」
映画史上最高の収益を誇る「タイタニック」の次は「荒野の7人(1960年)」で、それが黒澤明監督作「七人の侍(1954年)」のハリウッド・リメイク版ときた。そこから「スターウォーズ(1977年)」へ続くと、そろそろ流れは見え始める。すると、思ったとおり同じく黒澤の「隠し砦の三悪人(1958年)」が出てくるまではいい。ジョージ・ルーカスが「隠し砦の三悪人」を参考に「スターウォーズ」を作ったのは周知の事実なら、「ジェダイ」の語源が「時代劇(ジェダイゲキ?)」しかりだ。問題はこの先で、おかしな方向へ傾きだす。
要するに、「タイタニック」が抜いたとはいえ未だ映画史上第2位の座を護る「スターウォーズ」がそれだけ稼ぎながら、アイデアの元となった「隠し砦の三悪人」へは1銭たりとも分配されていないのが不公平だと言いたいのだ。これは、たいへん危険な考え方である。まして、その自覚がないから、なお悪い。同じ番組の中で日本は映画文化があっても映画産業はないといいながら、この考え方がそんな状況を生み出しているにもかかわらず、それらの関連へは最後まで触れずじまいだ。
少しでも海外へ進出しようとする日本の映画人の助けになればと前回、前々回のエッセイで様々な問題を提起した後、私の杞憂で終わって欲しかったそれらの問題点がこの番組でくっきり浮かび上がり、がっくりさせられた。結局、日本人同士のコミニケーションは現実をちゃんと認識する姿勢より相手に対する気遣いで成り立ち、気遣いを言い換えれば甘えである。価値観の違う相手へ気遣いが伝わらないと、本来は伝えるため相手を理解しようと努めるのが当たり前だ。しかし、そういう相手とはほとんど遭遇しない環境に慣れてしまうと、つい相手の気遣いへ甘えてしまう。
気遣いは伝わっても、そのお返しがない相手を無神経なよそ者と決めつけ、失礼な相手だから気を遣うのはやめる。そして、気遣いが伝わらない相手はいわば外人で、住む世界が違うのだから見放す。これでは、いくら気遣っているつもりでも甘えに過ぎない。価値観の違いが認識できない限り、甘えも自覚できず、価値観の違う相手と遭遇するまで、その認識は無理だ。もちろん、相手を理解しようと努めなければ、たとえ遭遇したところで世界が広がるわけはない。
「スターウォーズ」
まして、先のTV番組がルーカスと黒澤へ触れながら、その企画者はいったい黒澤の「影武者(1980年)」や「夢(1990年)」が誰の金で製作されたか考えたことはないのだろうか? 前者の場合、製作総指揮がルーカスとフランシス・フォード・コッポラ、つまり黒澤は2人の金であの映画を作りカンヌ映画祭のパルム・ドール(いわゆる作品賞)を取った。また、後者の場合、ポスターを見れば「スチーブン・スピルバーグ提供、黒澤明監督作品」とあり、これを今風に言い直すと製作総指揮がスティーブン・スピルバーグ、つまり彼が金を出したという意味だ。加えて、クレジットにはマーティン・スコセッシや特撮(SFX)を受け持ったルーカスのILM(インダストリアル・ライト&マジック)も名を連ねている。
たとえ後年、黒澤へそういった見返りがなかったとしても、そもそもルーカスと「隠し砦の三悪人」の関係を例えていえば、アンディー・ウォーホールとマリリン・モンローや毛沢東のようなもので、素材としてウォーホールの使ったモンローや沢東のイメージはパブリック・ドメイン(公共物)の類だ。したがって、作品が売れただけ何がしらはモンローや沢東へ分配されるべきだと思うほうが非常識である。どこまでをパブリック・ドメイン(公共物)とするかは、まだまだ灰色の部分が多い。1つだけいえることは、作品の独創性(オリジナリティー)や奥の深さが大きな決め手となり、ウォーホールの才能だから許される部分は少なからずあるだろう。これをウォーホールの知名度だから・・・・・・と、うっかり解釈すればまったく意味が違ってくるにもかかわらず、あんがい日本人は無神経なのだ。
「スターウォーズ」が「隠し砦の三悪人」からヒントを獲ても完全なオリジナルだから、先のTV番組でさえ盗作とは言えない。そんな曖昧な取り上げ方をする日本のマスコミと比べ、アメリカのマスコミが「ライオン・キング」は手塚治の盗作だという場合、なぜ手塚がディズニーを訴えないのか疑問を投げかける。両者の発想の違いは日本人がアメリカで失敗する大きな原因であり、理論立てて考えずに発想の違う相手は理解できない。
もし「スターウォーズ」がヒントのみならず完全な「隠し砦の三悪人」のパクリで成功していようと、そちらへ収益を分配すべきか否かは、パクリ自体とまったく次元の異なる問題である。私自身、29年間ハリウッドで暮らすうち、ヒット曲がもともと自分の作品だと訴える盗作事件を随分見てきた。裁判での勝敗は関係なく、自分の曲が盗まれたか盗まれたと主張するニュージシャン(作家)は、私の知る限り必ずといっていいほど裁判が終わって間もなく消え去っている。盗作にせよヒットしたのは曲の良さよりヒットさせたアーティストの才能と努力であり、盗まれないで作家自身がいくらがんばったところで、たぶん日の目は見なかっただろう。
ウォーホールの「毛沢東」
自分の曲が盗まれて盗んだ相手を著作権侵害で訴えるのは正しい行為だし、裁判が好きなアメリカでもハリウッドだと日常茶飯事だ。それだけに、そのメリットとデメリットはよくわかる。もし、私の曲が盗まれてヒットしたとしよう。私の行動は考えるまでもない。曲が盗まれたことは間違いなく証明できて、堅物の弁護士がたとえ成功報酬でも請け負いたがるほど勝訴を確信したとして、なお訴訟だけはぜったい避ける。
たとえば、曲や本の出版が決まった後、契約内容を変更されて納得できない場合は、そもそも自分が交渉して決めた以上、裁判への躊躇はない。これと曲が盗まれた場合とでは事情が違う。盗まれた曲のヒットは自らの意思と関係なく、基本的に他人の力で生じた利益だ。そこへ自分の権利を主張していくら儲かろうが、しょせんあぶく銭は身に付かず、それ故、むしろ疫病神となりかねない。
いっぽう、本来こだわるべき曲そのものへ焦点を当ててみると、何が得策かはっきりする。盗作裁判で非生産的な時間とエネルギーを費やす代わりに、盗まれた曲よりもっと素晴らしい曲を書いてヒットさせる努力をすれば、結果は駄目でも同じ時間とエネルギーを活かせる上、努力が実った時の満足感たるや、盗作裁判であぶく銭をつかんだ満足感など足元にも及ばないのは確かだ。また、ヒットさせたのが盗んだ相手である以上、喧嘩は簡単だが、ある意味でせっかく自分の才能を見出してくれた相手なのだから、関係を断ち切るよりは相手が自分に利用価値を見出す方向へ仕向けるべきだろう。
もし、盗むよりは正面きって自分を利用するほうが話は早いばかりか、結果に違いが出ると相手を納得させれば、お互いの利益へ結びつく。しかし、喧嘩は生産的な解決方法が可能であったとしても、それを閉ざす上、憎しみ以外に残るものがない。本質を見極めない裁判は、勝訴で負けてしまう。「隠し砦の三悪人」を盗んだ「スターウォーズ」だけが儲けて・・・・・・という発想ではハリウッドとの断絶がますます広がるばかりだ。
先のTV番組を見ながら思い出したのは、久しく会っていないが一時は連日のごとく顔を合わせていた友人レオナルド(レン)・シュレイダーである。かつて京都の同志社大学で英語を教えていた頃、映画好きの彼はやくざ映画にはまっていた。書籍とやくざ映画のポスターが居間の壁を埋め尽くし、当時流行っていた鶴田浩二のレコードを訪れたアメリカ人の知り合いに聞かせるため、「古い奴だとお思いでしょうが・・・・・・」という曲中の台詞を英訳しておく徹底振りなのだ。しばらく経ってアメリカへ戻ったレンは、趣味が高じてハリウッドでやくざ映画を作ろうと決意する。
「やくざ」
帰国したレンは、当時UCLA(カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校)の映画科を卒業後、全米を放浪中だった弟ポールを探し出し、2人でやくざ映画を作ろうと説得する。こうして誕生したのが高倉健とロバート・ミッチャム主演のシドニー・ポラック監督作「やくざ(1975年)」だ。製作準備のため京都を訪れたレンと四条河原町の交差点でばったり出会い、延々と立話をしたこともあった。
続く「タクシー・ドライバー(1976)」の成功でシュレイダー兄弟は業界へ食い込み始め、私がロサンゼルスに引っ越すのは、ちょうどその頃だ。レドンド海岸(ビーチ)のレンのアパートへ遊びに行くと映画と音楽の話で盛り上がり、面白い映画を演ってるからと誘われたりしながら、初めて目の前へ邦画の世界が開いてゆく。溝口健二や小津安二郎の名前は知っていても、彼らが作った映画は日本だと馴染む機会はほとんどない。
その点、さすが「映画の都ハリウッド」だけあって、いわゆるクラシック映画を日替わりメニューで上映する名画座は何館かあり、こういった類の映画館で黒澤明ばかりか溝口や小津の映画が上映される頻度は、チャーリー・チャップリンのそれより多い時もある。ハリウッドへ移り音楽活動を続けながら邦画が再発見できたのはレンのおかげだ。そして、ハリウッドの懐の深さがその奥に潜む。
「ザ・リング2」
最初は(そういった巨匠たちの)映画のテクニックばかりか溝口の私生活まで教えてくれるレンが特殊な存在だと思っていたら、そうでもなく、黒澤、溝口、小津、そして山田洋二や深作欣司などの名監督は、いいものへ貪欲なハリウッドの映画屋にとって馴染みのある存在で、フランス、イタリアその他どこの国の名監督であれ、とにかくよく研究している。それも日本のマスコミが海外へ出た日本の映画屋を「世界の××」と呼ぶ発想とは正反対で、埋もれた名作であろうと監督が何をやったかで評価する彼らは、名作とヒット作の違いを混同しやしない。彼らが「日本の○○監督は素晴らしい」と言う場合、裏づけがあるからそう言うのだ。
たとえば、「世界のナカタ」と書いた日本のジャーナリストへなぜ「世界のナカタ」なのか問い返すと、たぶん答は中田秀夫の監督作「ザ・リング2」が全米トップ10でNo1になったから・・・・・・するとハリウッド・リメイク版「呪怨」の清水崇監督とて変わらない。しかし、日本のオリジナルであれハリウッド版であれ「リング・シリーズ」はヒットしただけの内容があるいっぽう、二番煎じの「呪怨シリーズ」はしょせんホラー・ジャンルでしか通用せず、映画としての格が違う。全米トップ10のNo1入りで判断するうちは上辺しか見えず、本質を見落とす。
日米の「リング・シリーズ」と「呪怨シリーズ」をひととおり見た上での私の評価が、図らずも先のTV番組ビデオでより鮮明となった。たまたま中田と清水は番組を通じてフィーチャーされていたため、見ているうちに映画だとわからない2人の個人像がくっきり浮かび上がってゆく。ハリウッドを狙う日本の映画人はあと何人か登場し、彼らを含めたほとんどが「スターウォーズ」と「隠し砦の三悪人」を比べ、気遣いが通じない相手は見放すレベルの発言で、筋が通っていたのは中田ぐらいなのだ。
それも仕事の関係者であと2人の日本人とこの番組を見たのだが、アメリカで生活している以外は年齢や外観から性格や考え方までまったくタイプが異なる我々3人が3人とも、中田を除いて彼らの発言はまずアメリカで通用しないという点で意見が一致した。同胞でありながらアメリカで暮らす日本人には見える問題がなぜ見えないのだろう? なぜ価値観の違う相手を理解しようと努めないのだろう? 日本で認められた自分の才能をアメリカでも認めさせればいいのに、なぜ?
「THE JUON/呪怨」
怖さで勝負するホラー・ジャンルだからこそ、重要なのはリメイク権を欲しがるハリウッドが「呪怨」のどこへビジネスになる怖さを嗅ぎ取ったののか把握し、そこで日本と同じインパクトを与えるにはどうすべきか工夫する。こんな当たり前のことが、続編を打ち合わせる日本チームは忘れている無神経さが、番組を見る3人には理解できない。怖さを通じて日米間の溝が浮かび上がると同時、そういえばアメリカで暮らしながら自分も同じような失敗をしてきたな・・・・・・と、思ったのは私だけかもしれないが?
もう1つ、この番組から2人の日本人監督の間で大きな違いを知った。ハリウッドへ起用された日本人監督といえば、私の頭には単身乗り込んで勝手の違う俳優やスタッフを自分のイメージ通り動かすべく奮闘するイメージが浮かぶ。番組で現場のシーンを見る限りイメージ通りの中田に対し、意外だったのは清水である。彼の場合、中田のような個人プレイでなくチーム・プレイと知り、ハリウッド版「THE JUON/呪怨(The Grudge)」での疑問がいくつか解けた。結局、日本でのヒットへ目をつけたハリウッドはリメイク権の交渉を始め、受けたほうが自らの参加を条件にした結果、双方の妥協点からこの映画は生まれている。
参加を条件けた日本人プロディーサーや清水が、もう少し気遣いの伝わらない相手を見放さず、何とか理解しようと努めるだけで、まだまだ稼げる映画は作れたはずだ。続編の製作が決まって日米スタッフの打ち合わるシーンを見ながら、私でさえアメリカの市場を狙うなら疑問だった1作目の問題は今度こそ・・・・・・そんな期待がどんどんすぼんでゆく。結局、日本チームは1作目の教訓を何も学んでいなかった。打ち合わせで日米間のギャップが広がるのを見ながら、日本チームの姿はヒット曲が盗作だと著作権侵害を主張する作家の姿と重なり出す。
映画を見ただけで評価していた「リング」と「呪怨」の違いは、こんな背景があったのかとTV番組は教えてくれた。そして、更に番組の行間を読むと、番組の取材班が単身ハリウッドへ乗り込んだ中田より気心の通じる日本人チームで動く清水をより多く取材したのはわかるだけ、ジャーナリストとして安易な姿勢も引っかかる。番組を作る側のスタッフ各々がプロの自覚を持ち、それなりの仕事をするのは当たり前だ。しかし、邦画の海外進出がテーマの番組を作る以上、番組を通じて1人でも多く世界へ通用する人間を育てるぐらいの気構えは欲しい。そうすると、たとえば中田をもっと突っ込む手もあったような気がする。
ふだんは観客を動員できる映画や視聴率を稼げる番組へ専念し、「芸術祭参加作品」だと気合を入れるのは日本の伝統だから、映画文化があって映画産業はない日本の現状を紹介する上記のTV番組が、結局観光案内の番組と変わらなくなってしまう。「芸術祭参加作品」ではないから、ただ客をノセればいい。結果、「日本の××」と意味もなく囃し立てる野次馬にすぎず、世界へ通用する人間を育てるどころか大きな障害なのだ。日本から世界を目指すなら、まずそれに目を惑わされるな!! (完)
横 井 康 和