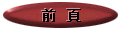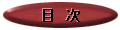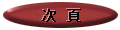映画とヒット
前回まで3回にわたって連載してきた「映画と世界」のテーマは、いわば邦画界と洋画界の間へ立ちはだかる大きな壁を浮かび上がらせることであった。世界に進出する日本の映画人と、それを「世界の××」と囃し立てる囲りのギャップへどれだけシビアーな問題が潜んでおり、日本に映画文化はあっても映画産業がないという、その映画文化すらこのまま行けば将来は怪しいものだ。
「ハウルの動く城」
これが、もしスポーツの世界なら白黒ははっきりするが、エンターテインメントの世界だとそうはいかない。結果、映画会社の大袈裟な宣伝文句へ何ら疑問を抱かず報道し、日本人がハリウッドのヒット映画を監督すれば、その監督を意味もなく「世界の××」と呼ぶマスコミや、世間は世間で報道されたとおり受け容れてしまう日本の風潮が、冷静な状況判断を阻害する。アメリカで活躍する日本人の野球選手だと、ちゃんと現状を把握している日本のマスコミやファンも、なぜかアメリカで活躍する日本人の映画監督や俳優の場合は、彼らの打率すら見ようとしない。
映画人にとって打率と該当するのが興行収益であり、当然ながら全米のボックスオフィス・トップ10へ入ったからと(つまり、ホームランを1本打ったからと)、それだけで評価の基準にはならないわけだ。ところが、日本のジャーナリストは清水崇監督のハリウッド・リメイク版「呪怨(2004年)」が全米トップ10入りすれば「世界のシミズ」、続いて今年の春シーズン中田秀夫の監督作「ザ・リング2(2005年)」が全米トップ10入りすれば「世界のナカタ」、全米1位というだけで両者の打率へは目もくれようとしないのである。
公開週末の興行成績が3,507万ドルの「ザ・リング2」に対して「呪怨」は3,913万ドルとやや上回るが、即トップ10から脱落した後者と比べ、前者は4週間もの間トップ10内へ留まったばかりか8週目でなお26位、それまでに合計7,589万ドル稼いでいるのだ。また、ディズニーが夏のブロックバスター・シーズンへ勝負をかけた宮崎駿作「ハウルの動く城」は公開週末の興行成績が全米14位とトップ10から外れたため、日本ではまったく話題にならなかった。しかし、「呪怨」のような二番煎じの駄作の1位より、こちらの14位のほうが重みがある上、じっさい「もののけ姫(1997年)」でオスカーを取った宮崎の知名度は、まだ日本でしか通用しない「世界のシミズ」と比較にならない。
ばかりか、もしかして日本以外でも通用するかもしれない映画が、こういった「世界」とか「巨匠」など映画会社の軽薄な宣伝文句で可能性を失くす。たとえば、鈴木清順監督のリメイク版「オペレッタ狸御殿(2004年)」は、ツィイー・チャンが出ているというので興味を引かれたものの、予告編を見ると・・・・・・「キル・ビル」のクエンティン・タランティーノ、「2046」のウォン・カーワァイ、「ミッション・インポッシブル2」のジョン・ウー、世界の巨匠鈴木清順・・・・・・この出だしでがっかりさせられて、それ以上は予告編さえ見る気がなくなった。
「ザ・リング2」
本来は映画を見たくさせるための予告篇が、これほど逆効果を生むケースは珍しい。まず、この出だしで映画会社が言おうとしたのは、鈴木がタランティーノ、カーワァイ、ウーと並ぶ世界の巨匠であり、そこから本編の紹介へ入ろうという作戦は読めるが、じっさいタランティーノ、カーワァイ、ウーと並ぶ世界の巨匠なら、そういった前置きは必要なく、ただたんに鈴木清順で事足りる。
加えて、なまじタランティーノ、カーワァイ、ウーのような世界的なヒット作がないだけ、よけいな前置きは鈴木がタランティーノ、カーワァイ、ウーへ傾倒する三流監督の印象を与えてしまう。そうすると、もしかして「オペレッタ狸御殿」は素晴らしい映画かもしれないけれど、もはや確かめる気にならず、未だ見ずじまいなのだ。なぜ、エンターテインメントの世界だと、こういう問題が起こるのであろうか?・・・・・・答は簡単である。オリジナリティーが決め手となる創作の世界では、勝敗が決め手となるスポーツの世界と違って、他者との比較が個性のなさを意味し、自らの否定へ結びつく。
話は変わるが、国際的に活躍する日本の建築家やファッションデザイナーは少なくない。ただ、ごく一部のトップクラスを除けば、日本でプロとして活躍する同業者の多くへ共通していえるのが、オリジナリティー(個性)とトレンド(流行り)の勘違いだ。両者は対極をなし、まったく次元が違う。そして、トレンドを追う限りオリジナリティーは生まれず、逆に物事へのこだわりがオリジナリティーとなり、そこからトレンドは生まれる。
「オペレッタ狸御殿」
プロの建築家やファッションデザイナーである以上、誰しも自分のスタイルを持つ。オリジナリティーを活かすことで、より顧客に満足感を与えることが可能となる。それは何も奇抜なアイデアを意味せず、むしろ快適な住居や衣服へのこだわりだ。そういったこだわりがあるデザイナーでも、当然ながらセンスの良し悪しは別問題となってくる。そして、一見センスが良さそうなデザイナーほど、先の勘違いは目立つ。
たとえば、自宅を新築か増築する際、設計を頼んだ建築家がこちらの希望に対し、
「今の流行(はやり)はそうじゃなくて・・・・・・」とか、
洋服をあつらえる際、仕立て屋がこちらの希望に対し、
「今の流行(はやり)はそうじゃなくて・・・・・・」と言うことが、日本の場合、少なからずあるのではないだろうか? 私自身もアメリカへ引っ越すまで、ずいぶん身に覚えがある。ただ、自分ではそういったプロへ頼むとしたら、どうしてほしいか決まっているので、それを通すか別の業者を捜すかどちらかだ。もちろん、反対された理由が流行(はやり)でなく、住み心地や着心地の問題であれば相手の意見を素直に聞く。アルマーニのスーツを買っても、結局は自分の好みで仕立て直し、裏地へ縫いつけられた(アルマーニの)ラベルさえ切り取ってしまう私を変態視する友人がいようと、そういう性格なのだからしかたない。と思いつつ、アメリカへ引っ越してわかったのは、建築家やファッションデザイナーの類(たぐい)のプロが今の流行(はやり)を教えてくれても、それはあくまで参考に過ぎず、顧客(クライアント)が求めるものを最優先する。つまり、アメリカで彼らから「今の流行(はやり)はそうじゃなくて・・・・・・」と反論されたり変態視されたことがないのだ。
アメリカの場合、むしろ常識とかけ離れていたり斬新なアイデアを提起すると、一般レベルのプロでも優秀なほど意欲を燃やす。これを国民性の違いといえばそれまでだろう。しかし、その違いは日米のメジャー・スタジオがヒットを狙う映画の歴然たる差となっている。最近の邦画へ、かつてのような拘(こだわ)りは感じられない。今でこそ日本を代表する監督の一人、小津安二郎が業界に入った当初、洋画ファンの当人はほとんど邦画と無縁であった。それが「世界の小津」としての実績を築くのは、ただならぬ彼の拘(こだわ)り故である。
洋画ファンであった小津は、たまたま社内の配置換えで監督となっても幸い何が邦画の流行(はやり)か知らず、ひたすらこだわるうちあの独自の構図をあみ出した。「秋刀魚の味(1962年)」など小津の映画では登場人物を平行して並べた構図が随所で見られる。実際は不自然な配置でありながら、その構図が不思議な世界を醸し出す。当時、それらの映画は日本でヒットしたばかりでなく、後年、小津の名を世界へ知らしめるわけだ。
「秋刀魚の味」
こだわりという点なら、黒澤明だって溝口健二だって山田洋二だって深作欣二だって変わらない。ところが、最近の邦画を見るとそういうこだわりはあまり感じられず、やたら物真似、つまり流行(はやり)が目立つ。そして、流行(はやり)を追う限り流行(はやり)を生み出すようなヒットを飛ばすのは難しいだろう。
一連の「あずみ(2003年、2004年)」とか「阿修羅城の瞳(2005年)」とか「SHINOBI(2005年)」などを見ると、きまってアン・リー監督作「グリーン・デスティニー/伏虎隠龍(2000年)」の空中を駆けるパターンやウォシャウスキー兄弟の「マトリックス三部作」で使われた様々な手法(テクニック)が応用されている。いかにも日本の中堅どころの建築家やファッションデザイナーが上手く流行(はやり)を取り入れるごとく、一見まとまっていそうで、そこへは徹底したこだわりもオリジナリティーも感じられない。
その点、「グリーン・・・」と同じくツィイー・チャンが主演するチャン・イーモウ監督作「LOVERS/十面埋伏(2004年)」などは、空中を駆けるのとよく似たパターンを使っても、こだわりが伝わってくるので気にならない上、最後のクライマックスたるや、類を見ないユニークさだ。決闘シーンの背景では山々が刻々と季節を変えてゆく。結果、手前で展開する決闘の激しさを強調こそすれ、決して漫画にはならない。先の流行(はやり)を取り入れた軽薄な邦画と雲泥の差であり、「LOVERS」がハリウッドでヒットしたのもうなずける。
「LOVERS」
こだわりとは、言い換えれば隙をなくすことでもある。流行(はやり)の手法を取り入れただけだと、一つ一つのシーンがどれだけ高い完成度でも隙だらけだ。たとえ屋根を飛び越すシーンは「グリーン・・・」を勝り、放たれた矢が飛んでゆくシーンは「ロビンフッド(1991年)」を勝り、天地が逆さまになりながら戦うシーンは「マトリックス」を勝ろうと、それだけでいい作品が誕生するわけではない。もし全体のバランスがとれていないと、反って作品としての質を落とすだけだ。
「あずみ」の戦闘シーンでは、主演の上戸彩自ら演じる部分とスタントマン(スタントウーマン?)の演じる部分が開きすぎで興ざめなのも、編集の時、上戸の部分だけほんの少しスピードを上げ、スタントマンの動く早さとマッチさせるだけで結果はまったく違っていたと思う。そこまで気を回さないと隙が生じてしまうのである。それは「ローレライ(2005年)」のSFX(特撮)とて変わらず、せっかく模型を使ったシーンが上手く出来ているのに、後半の連合艦隊を俯瞰で捉(とら)えた1シーンだけは風呂場へ玩具の船を浮かべた世界なのだ。この1シーンが全体をぶち壊しにするのだから隙とは恐ろしい。
そうした致命的な隙が目立つメジャー路線の最近の邦画でも、いっぽうでは「NIN×NIN 忍者ハットリくん THE MOVIE(2004年)」など、逆にマトリックス・テクニックや中華テクニックばかりか「恋愛準決勝戦(1951年)」や「2001年宇宙の旅(1968年)」の360度回転するセットを使う手法まで採り入れながら、しっかり自分のものにしている。そうすると、冒頭のCG(コンピュータ・グラフィック)で描いた風景の嘘臭さすら意識的なものと思え、すんなり受け入れてしまう。
「インストール」
また、先の上戸の主演作でも「インストール(2004年)」は、「あずみ」と違ってなかなかいい(「大ヒット上映中!」というポスターのうたい文句がちょっと残念だ)。物語はタイトルどおりコンピュータが中心となって展開するわりに、その関連シーンはやはり嘘臭いのだが、それを意図していると解釈できる。監督の片岡K(41歳)はこの映画でデビューしたばかりと聞けば、なおさら将来が楽しみだ。
「NIN×NIN・・・」や「インストール」と比べ、結局、「あずみ」、「阿修羅城の瞳」、「SHINOBI」といった映画はトレンドを追うだけの建築家やファッションデザイナーと変わらないような気がする。一見、カッコいいようで隙だらけ、「本物」と呼ぶには程遠い。ともかく、溝口の構図へのこだわりを見習い、隙をなくせば日本から世界的なヒットを出すことだって可能だろう。そして、ちょっとした突っ込み如何が、その映画の決め手となるのである。
横 井 康 和