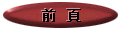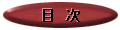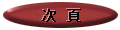映画と茶髪族
「ボーン・アイデンティティー(2002年)」やその続篇「ボーン・スプレマシー(2004年)」は、映画ファンならご存知のとおり記憶を失くした主人公ジェイソン・ボーンが自分自身(アイデンティティー)を捜し求める物語である。そして、自分を知ろうとするボーンの旅は、原作だとロバート・ラドラムのシリーズ第3作「最後の暗殺者(1990年)」およびラドラムを引き継いだエリック・ラストベーダーによるシリーズ第4作「ボーン・レガシー(2004年)」へと続いてゆく。
「ボーン・アイデンティティー」
さすがラドラムと思わせるユニークな目のつけどころだが、よくよく考えてみると「自分を知ろうとする旅」はボーンばかりが体現しているわけではない。つまり、我々の人生そのものが「自分を知ろうとする旅」なのだ。そもそも人はどこから来て、どこへ行こうとしているのか、誰も明確に答えられないだろう。それを捜し求めるのが人生であり、生き甲斐とは自分なりにどこまで納得できる答が見つけられるかである。
自分自身(アイデンティティー)を捜し求めながら、時としてシビアーな現実と直面し、克服してゆかなければならない。たとえば足の短さは、いくら悩もうが解決せず、上げ底の靴(ヒール)で誤魔化そうとしたら、よけい惨めな結果を招くだけだ。「憧れ」は自分を向上させるエネルギーとなるいっぽうで、うっかりすると自分を誤魔化す。上げ底の靴(ヒール)がカッコいい場合はあっても、足の長いのがカッコいいと憧れて上げ底の靴(ヒール)を履くと絶対カッコ悪い。
ただ、カッコいい悪いの判断は自分が下すべき問題であり、マイケル・ジャクソンだって彼なりの信念は持っているからこそ、あそこまで不自然な白人のような容姿に整形したのだろう。そのジャクソンを見るたび思うのが、他ならぬ日本の「茶髪族」で、最近は「あずみ(2002年)」や「阿修羅城の瞳(2005年)」といった時代劇へまでこのトレンドが及ぶようになった。
「あずみ」
いうまでもなく、髪を茶色く染めた当人たちは、自分を誤魔化している認識などなく、まして茶髪をジャクソンの整形と同レベルで考えていないはずだ。ところが、海外から見るとさほどレベルは変わらない。私がそう思う背景には、過去30数年の様々な出来事が影響している。
'70年前後まで遡(さかのぼ)り、「旅行記」に何度も登場する友人レスリーと京都で出会った当初、彼女の書いた詩が印象的で、その10数年後「Infatuation」という曲の2番の歌詞に使った。「Black hair shinning almost blue (艶やかな黒髪が輝く)・・・・・・」で始まる元の詩は、当時の彼女が好む(ちょうどツイィー・チャンのような)ストレートな黒髪の日本男児を反映しており、興味を引かれたのはその部分だ。
時が流れアメリカ生活に慣れて間もない頃、もともと癖毛で決して美しさとは縁のない私のロングヘアーへ、そっと手を差し伸べた白人のガールフレンドが、「Such a beautiful hair! (なんて美しい髪なんでしょう!)」と溜息交じりに言った時の瞳の輝きは、言った当人の印象がぼやけた今でも忘れられない。金髪(ブロンド)へ憧れる日本人同様、相手にとっては我々の黒髪が(レスリー好みのストレートと限らず)神秘的なのだと初めて実感させられた瞬間である。
それから30年以上を経た数ケ月前、アメリカで最先端をゆくホームシアターのショールームを何軒か訪れた時、たまたま1軒のオーナーが元タワー・オブ・パワーのベースとサックス奏者ジェイソン・ロードで、すっかり話は盛り上がる。ショールームが3つあるうちの1つはスピーカー・システムだけで2千万円を超え、その音で首筋の後ろが逆毛立った体験もさることながら、ポツリと漏らした彼の言葉も私の胸を突き刺した。
「阿修羅城の瞳」
まったく日本を知らなかったロードが、四半世紀以上前に初めてバンドのコンサート・ツアーで訪れて以来、つき合ってきたガールフレンドはすべて日本人なら、今や自宅へ日本庭園を作り、行きつけのレストランが日本食というばかりか、音響技師としてショップを立ち上げた結果、職業柄、日本のメーカーとは密接な関係を持つ。同時に日本の音響および映像機器の長所と欠点を冷静に分析する彼が、「最近は中国人の客が増えているけれど、アメリカ、ヨーロッパ、日本製は受け容れる彼らも、中国製や韓国製だと絶対買わないね」と、面白おかしく説明しながら的を外さない。
しばらく話すうち、話題が共通の知人であるギターリストの高中正義へ逸(そ)れたりしつつ、日本に対するロードの思い入れや並外れた理解度は犇々(ひしひし)と伝わってくる。本当に日本が好きなんだなと感心しているところへ、彼はポツリと漏らす。
「日本が素晴らしい国であることは間違いないよ。ただ、髪を染めた若者が目立つようになってからは・・・・・・」と、途中で言葉を濁した。まさか、こんなところで日本の茶髪族へ抵抗を示すアメリカ人がいようなどと予期せぬ私は、改めて自分自身が茶髪族を毛嫌いするわけを考えさせられたわけだ。そうすると、やはり「あずみ」の上戸彩や「阿修羅城の瞳」の市川染五郎が茶髪でなかったら、それだけで映画の質(クオリティー)は向上していそうな気がするし、反面、もし茶髪であったとしたらツイィー・チャンはハリウッドで今のような成功がおぼつかなかったと思う。いっぽう、「SAYURI」でチャンと共演するミシェール・ヨーも、いいところまでハリウッド進出を果たしながら、最近の茶髪を見ると先は見えた。極端すぎるかもしれないが、要はマイケル・ジャクソンの整形と変わらず、自分自身(アイデンティティー)を無視した場合、どうしても嘘臭さが付きまとう。
「阿修羅城の瞳」で市川染五郎の髪はいっそピンクとか紫だったら問題がはっきりする。本来、映画とは虚構の世界であり、ピンクの髪の嘘臭さへ観客が真実味を感じるかどうかの世界だ。ピンクとか紫の髪で黒髪を表現できれば、茶髪ならなおさら違和感はなくて済む。しかし、茶髪で違和感があるぐらいならピンクや紫など論外である。そういった意味で「あずみ」や「阿修羅城の瞳」の茶髪は中途半端なのだ。時代劇と限らず、「交渉人 真下正義(2005年)」など茶髪族が目立つ最近の邦画は同じことがいえる。
「インストール」
やはり上戸の主演作「インストール(2004年)」は、映画自体がよく出来ているだけ登場人物の茶髪はさほど気にならない。だが、出来のいい映画ほど登場人物の自分自身(アイデンティティー)へのこだわりは意味を持つ。「インストール」のような映画こそ、茶髪で価値を下げてほしくないものだ。
私個人がどう考えるかはさておき、ロードと会って2〜3ケ月も経っただろうか、ビバリーヒルズの美容院の前を通りかかると、ショーウィンドウに張ってあった1枚のポスターが目を引く。2メートル近い縦長のポスターは背景が黒髪のクローズアップ、キャッチフレーズは中央やや下寄りへ白文字で書かれている。曰(いわ)く、「あなたにも日本人のストレート・ヘアーを」・・・・・・これを見て思ったのが、ますます広がってゆく現実とのギャップだ。現実の日本人は自分自身(アイデンティティー)を掘り下げようとせず、たとえビバリーヒルズの美容院が宣伝文句に使おうと自らの武器はあっさり放棄する。
つまり、ロードが途中で言葉を濁した先は、極論を言うと「髪を染めた若者が目立つようになってからは、日本人が自分自身(アイデンティティー)を失くした」ということではないだろうか? ただ、失くそうが失くすまいが自分の勝手でしょ、と考えても日本国内なら損はない。海外へ出た茶髪族が黒髪族に変身したり、帰国して髪を染める日本人が少なくない現実は、この裏返しだ。しかし、たとえ自覚がなくとも損得で髪の毛を染めるのでは、ちょっと寂しい。
コロンビア、ドリームワークス、スパイグラスの共同企画としてアーサー・ゴードンのベストセラー小説「さゆり(1997年)」の映画化が決まったのは前世紀の終わりだが、遅れに遅れた大きな理由は、当初プロデュースばかりでなく自ら監督を務めるはずのスティーブン・スピルバーグのスケジュール調整がつかなかったことと、もう1つは芸者新田さゆり役のキャスティングで手間取ったことだ。
「SAYURI」
一時、スピルバーグが抜擢したニューヨーク在住の無名の日本人ダンサー岡本リカで決まりかけて、結局は駄目だった。紆余曲折を経て、先月末、ようやく全米公開された「SAYURI」の主演が中国人の女優ツィイー・チャンなのは、言い換えればハリウッドで通用するさゆり役をこなす日本人の女優がいなかったからである。やはり今の「茶髪族のメンタリティー」だと、その境遇ゆえ無意識ながら自分自身(アイデンティティー)を問わざるを得なかった新田さゆりの生涯を演じるなど、とてもおぼつかないのだろう。
私は個人的に茶髪族を嫌いだからと、なにもそれが悪いとかやめろと言っているのではない。私が言いたいのは、もし海外へ出て勝負をしたいのなら、せめて自分の持っている武器ぐらい使えということだ。まして、映画のような自分自身(アイデンティティー)を問われる芸術分野だと尚更である。とにかく、自分自身(日本と日本人)へもっと誇りを持て!
横 井 康 和