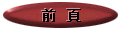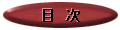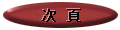映画と世界 (上)
今年のクリスマス・シーズンを狙って全米公開される「SAYURI」、主演は紆余曲折の末、ツィイー・チャン(Ziyi Zhang)で決まった。このチャンだが、どういうわけか(「ラッシュアワー2」など)ハリウッド映画に登場した当初は苗字と名前が逆のZhang Ziyiとして紹介され、その後、Ziyi Zhangへ修正されながら、日本のYahoo!ムービーなどを見ると未だチャン・ツィイーのままだ。
「SAYURI」
もっとも日本語の場合、本来は苗字が先だからチャン・ツィイーでも間違いではない。最近の邦画界だと(ジョー・オダギリならぬ)オダギリジョーという名の男優もいる。しかし、そうすると例えばジュディー・ウォンがウォン・ジュディーとなるべきである。日本はどうもそのあたりが曖昧かつ統一性に欠けるようだ。そして統一性に欠けるといえば、典型は歴史の認識であろう。整理上、世界史と日本史へ分類するのはいいが、その結果、うっかり両者を別物として認識しがちである。
たとえば、世界史は苦手だが日本史は得意という人がいないだろうか? しかし、日本史は世界史の一部である以上、これだと辻褄が合わない。もちろん、言った当人はそんなつもりがなく、同じ日本人同士なら言われた相手もちゃんと意味合いを理解する。つまり、言葉よりお互いの気配りで成り立つコミニケーションだ。価値観の違う外国人には時として誤解を招く。
結局、われわれ日本人が日本と世界を区別する場合の基準は、価値観が同じか同じでないかの違いかもしれない。この図式は歴史の認識同様、音楽なら邦楽と洋楽、映画なら邦画と洋画、その他いろいろなところでパターン化している。ところが、最近は価値観そのものが昔ほどはっきりと区別できなくなってきた。日本の映画監督や俳優がハリウッドへ進出するようになると、出来上がった映画を洋画とか邦画で分けるのは無意味だ。
今後、日本の映画人が世界で活躍すればするほど日本と世界の区別はなくなってゆくだろう。裏返せば、アメリカで「ザ・リング2」がヒットした結果、監督の中田秀夫を日本で「世界のナカタ」と騒ぐうちは、そこへ至る過渡期に過ぎない。この「世界」が何を意味するのか曖昧なあたりからして日本的発想なのである。同じことなら「水を描かせたら天下一品の中田」とか、なぜもっと具体的な表現が出来ないのであろうか?
「忠臣蔵外伝 四谷怪談」
かつて「世界の黒澤」と呼ばれた黒澤明監督なら「World famous Kurosawa」と訳せば済む。じっさい、彼は「世界的に有名な映画監督(World famous film producer)」とか「世界的に知られた映画監督(Internationally recognized film producer)」といえるだけの実績があり、そう訳して差しつかえはないはずだ。黒澤ばかりでなく「世界の小津」、「世界の山田」、「世界の溝口」、「世界の深作」しかりである。だが、世界の桧舞台へデビューしたばかりの中田の場合、彼らのようなベテランと違って「World famous Nakata」の訳は当てはまらない。
ハリウッドの企画へ起用されることが評価の対象でなく、肝心なのはそこで何を作るかだ。作る内容が肝心であれば、むしろ世界に通用するのは日本的な映画であり、深作欣二監督作「忠臣蔵外伝 四谷怪談(1994年)」など、次のような冒頭の文句だけで「世界」を感じさせる。
「仁義なき戦い」
元禄時代
江戸の総人口は百万に達し
パリの五十万
ロンドンの七十万をいて
世界最大こうして、まず当時の江戸を世界の中で位置づけて幕が開く。タイトルのごとく「忠臣蔵」と「四谷怪談」を混ぜたストーリーへ、「仁義なき戦い」と「アダムス・ファミリー」を混ぜた邦楽ミュージカルとでもいうべき脚色は、なんだか訳がわからないようで抵抗なく入り込む。その印象は妙にハリウッドっぽい。そして、深作の代表作である「仁義なき戦い」の流れを「忠臣蔵外伝 四谷怪談」より感じさせるのが「キル・ビル(2003年/2004年)」や「シン・シティー(2005年)」だ。
監督のクエンティン・タランティーノは「キル・ビル」を深作へ捧げているだけでも彼の傾倒振りがわかる。ばかりか、「キル・ビル」でシリーズ9作目「新・仁義なき戦い(2000年)」のテーマソングを使っている以上、彼は7作目で深作が降りた後の「仁義なき戦い」まで、しっかり見ているのだろう。また、「キル・ビル」の一部は監督仲間のタランティーノから頼まれたロバート・ロドリゲスが演出しており、ロドリゲスはロドリゲスで、その後、原作者のフランク・ミラーとの共同監督で「シン・シティー」を映画化する際、ゲスト監督としてタランティーノを迎えた。
「仁義なき戦い」の延長線上へ「キル・ビル」と「シン・シティー」が浮かんでも、背景を見れば偶然ではないことがわかる。そこに邦画と洋画の区別はない。「仁義なき戦い」から「シン・シティー」へ辿り着き、さらに「シン・シティー」から辿ると黒澤の「天国と地獄(1994年)」が浮かぶ。モノクロへ部分的な着色をした「シン・シティー」のテクニックは、もともと黒澤が「天国と地獄(1963年)」で考えたアイデアなのだ。
「キル・ビル」
黒澤があのアイデアを思いつくまでの経緯は、以前もこのコラムで触れたとおり、時代背景と密接な係わりがある。カラー映画の時代に突入してなお当時の黒澤はモノクロへ固執し、固執し続けたからこそカラーにどう移行するかが大きな問題だったのだろう。あっさりカラーを受け入れれば、天然色フィーバーで浮かれる他の監督同様、モノクロは過去へ置き去りになったと思うが、固執すればするほど、そうはいかない。
そんな状況で、煙の色が決め手となる「天国と地獄」のクライマックス・シーンは、カラーを試す絶好のチャンス到来であったはずだ。つまり、勘ぐれば世間の天然色フィーバーへの反発から意地を張った結果に過ぎないという見方もできるわけだが、後の映画へ多大な影響を及ぼした事実は反論の余地がない。たとえば「天国と地獄」から逆に辿ってゆくと、今度は「シン・シティー」と並んでスティーブン・スピルバーグのオスカー受賞作「シンドラーのリスト(1993年)」や高倉健がモントリオール映画祭その他で主演男優賞を取った「鉄道員(ぽっぽや)(1999年)」も登場する。
暴力で支配されたフィルム・ノアールの典型作「シン・シティー」と、「シンドラー・・・」や日本の鉄道員を描いた地味な芸術ドラマ「鉄道員(ぽっぽや)」は、まったく異質の存在でありながら、少女の服の色や回想シーンが部分的に着色したモノクロの映像で統一された「シンドラー・・・」や「鉄道員(ぽっぽや)」は「天国と地獄」の延長線上で「シン・シティー」と重なりだす。ますます邦画と洋画がクロスオーバーしてきたところで、ハリウッドよりもっと身近な外国へ目を向けるとどうだろう。
「シン・シティー」
最近は韓国や香港の映画が日本でブームとなっても決して珍しい現象ではない。それらの映画に日本人が価値観の違いを覚える限り、こうした現象は起こり得ず、それだけ一般的なレベルで日本人の視野が広がってきたと思えば嬉しい傾向だ。国と国とは竹島を巡って対立する国際情勢でも、人間ドラマへ共感する心に国境はない。
今や冒頭で触れたチャンが鈴木清順監督作「オペレッタ狸御殿(2004年)」へ主演するいっぽうでは、彼女の主演作「HERO(2002年)」や「LOVERS(2004年)」のチャン・イーモウ監督が現在製作中の新作「千里走単騎」で先の高倉を主演に抜擢し、香港の佐田啓二、トニー・レオンが第53回カンヌ映画際で主演男優賞を取ったウォン・カーウァイ監督作「花様年華(2000年)」の続編「2046(2004年)」でも、木村拓哉が日本語の台詞だけの日本人役でがんばっている。
あるいは、宮沢りえが第23回モスクワ国際映画祭で最優秀女優賞を取った「華の愛 遊園驚夢(2001年)」のような台湾、中国、日本の共同製作映画や、一連の「リング・シリーズ」で脚光を浴びた中谷美紀が韓国語の台詞へチャレンジした「ホテル・ビーナス(2004年)」のような日本資本の韓国映画まで現われると、いよいよ邦画と洋画(外国映画)の境界線をどこへ引いていいのか微妙なところだ。
映画を整理する上でのカテゴリーとしての邦画と洋画はいいが、発想の上で邦画と洋画を区別するうちは、いくら先の中田や「呪怨(2002年/2003年)」の清水崇がハリウッド資本でリメイク版を監督し、「ラスト・サムライ(2003年)」でオスカー・ノミネートされた渡辺健がこの夏のブロックバスター作「バットマン・リターンズ」に出ようと、その先を育(はぐく)む環境は整わない。インターネットが進歩したおかげで国境の壁はどんどん崩壊しつつある今日、せっかく手を伸ばせば世界へ届くのに、手をこまねいていては、いつまで経っても対岸の火事を眺める野次馬でしかない。
先日、たまたま「千里走単騎」の記事が目についた。出だしは「『HERO』『LOVERS』の国際的ヒットで世界の巨匠となったチャン・イーモウ監督が、日本映画界の重鎮、高倉健を・・・」と、初っ端から何を称して記者は「世界の巨匠」と書いたのか疑問が浮かぶ。イーモウ監督を世界の巨匠と呼ぶことに異存はない。しかし、イーモウが世界の巨匠となったのは「HERO」や「LOVERS」の内容が決め手であり、国際的ヒットは二次的な要素だ。
「鉄道員(ぽっぽや)」
これが、ただ「『HERO』『LOVERS』で世界の巨匠となった・・・」、あるいは、それこそ「国際的ヒットで『世界のイーモア』となった・・・」なら納得できるが、「国際的ヒットで世界の巨匠となった・・・」では対岸から眺める野次馬と同レベルの表現である。日本のマスコミが野次馬の体質を持つのは昔からの伝統かもしれないが、もう少し慎重な言葉使いをお願いしたい。
深く考えないで表現した結果、本質を見誤り、挙句の果ては日本しか見ないで世界を見たと思い込む。そうすると、篠田正浩のようなベテラン監督でさえ国際的なスケールのドラマを描くつもりが「スパイ・ゾルゲ(2003年)」では裏目と出てしまう。つまり、日本人の感性でしか理解できない世界を描いても、それが世界へ通用しないという大前提だけは忘れないことだ。そうすれば、おのずと自分の感性で捉えた世界をどのように世界へ伝えようかと考える癖がつく。
要は日本人の気配りで成り立つコミニケーションを大切にしながら、かつ相手の価値観が必ずしも自分と同じでないと認識するだけで世界は広がってゆく・・・・・・ここまで書いてきたのも、それが言いたかったからである。誰かを「世界の巨匠」と呼ぶ以上、なぜそう呼ぶのか本来なら自覚はあるのが当然だし、さらに価値観の違う他人へ誤解を招かないよう配慮すれば「国際的ヒット云々」と関連付ける安易な発想、あるいは意味合いが曖昧なまま「世界の云々」という表現は出来ないはずだ。とにかく、日本のマスコミが軽々しく「世界の云々」や「巨匠」を使うのも、そろそろ止める頃合ではなかろうか?! (続く)
横 井 康 和