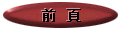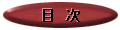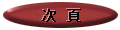映画と現実
今年の「MTV映画賞」で「最優秀映画賞」に輝いた「ウエディング・クラッシャーズ(2005年)」が、去年の夏に全米で封切られた時は、関係者ですらあすこまでヒットすると思っていなかった。私自身ほとんど期待せず、暇つぶしのつもりで見たら、数ある他のブロックバスター作よりよほど印象深かった次第である。ただ私の場合、この映画が印象に残ったのは、それなりの理由があってのことなのだ。
「ウェディング・クラッシャー」
かれこれ20年ほど遡(さかのぼ)るだろうか、いわば「結婚式場荒らし」を意味する「ウエディング・クラッシャーズ」に図らずも自らなってしまった。もちろん、最初はそんなつもりなど毛頭なく、風が吹いた結果、桶屋は儲かったという程度の話にすぎない。ちょうど日本から私の知り合いのN氏が訪れ、氏の友人のトロンボーン奏者を見に行こうというのがきっかけである。
そもそも、N氏とは私がかつて日本でプロデュースしたロック・バンドの若きギターリストを通じて知り合った。そのギターリストの父親であるN氏は、戦後間もなく死に場所を求める特攻隊崩れの若者であった頃、焼け野原の闇市を彷徨(さまよ)いながらデューク・エリントンの音楽を耳にして、再び生きる希望を持つ。その後、紆余曲折を経てエリントンと出会ったN氏が、エリントンから実の息子より可愛がられたことは、エリントンの自伝でN氏が登場する下りでも想像はつく。
したがって、かつてエリントン・バンドに在籍したミュージシャンの多くがN氏と昵懇(じっこん)の仲であり、「デュークス・メン」と呼ばれる彼らはアメリカのジャズ界でも一目置かれる存在だ。そんな「デュークス・メン」が南カリフォルニアに3人いて、先のトロンボーン奏者C氏はそのうちの1人である。みんな私より一回り年上のN氏と同じ世代か、更に上の世代であることは言うまでもない。
ただ、私が音楽活動と平行してプロダクション業務へ携わっていた頃、N氏を通じて知り合った彼らにTV取材を申し込んだりした関係上、私自身も彼らと家族ぐるみの付き合いはあった。その私が当のN氏と演奏を見に行きたいというので、C氏はわれわれ2人を大歓迎してくれたのである。ところが、たまたまその時の演奏場所はコンサート・ホールでなく結婚披露宴の式場だったのだ。
ビバリー・ウィルシャー・ホテル
結婚式場と聞いていたN氏と私がスーツ姿で式場へ付いてみると、そこはビバリー・ウィルシャー・ホテルでも一番大きなボールルームであった。ボールルームのドアは閉ざされ、招待客が表のラウンジでカクテル片手に盛り上がっている。われわれ2人を見つけたC氏は、人の結婚式で身内とその知り合いしか来ていないから、なるべく目立たないよう、ゆっくり楽しんでくれと言い残して楽屋へ去ってゆく。
われわれ2人とて、おめでたい席を台無しにしたくないからラウンジの隅で地味に飲み始めた。ただ、白人ばかりの中で20ほど歳の離れた日本人コンビがいれば、どうしても目立つ。招待客の中には、我々が新郎新婦とどのような関係なのか興味を引かれ、話しかけてくる者も少なくない。話しかけられると応えないわけにもいかず、もともとパーティー好きのN氏と私は、新郎新婦両方の友達の友達だということで、適当に話を合わす。そうこうするうち、広いラウンジでも、われわれのいるコーナーが、いつしかえらい盛り上がっていた。
問題は、しばらく経ってボールルームのドアが開いた後で、当然ながらわれわれ2人は遠慮して、他の客が全員席に着き終わるまで入ってすぐの壁際で立っていたところ、後ろのテーブルはどんどん埋まってしまう。C氏からテーブルの空いているところへ適当にすわれと言われていたが、まさか前のテーブルはまずい。と、先ほどラウンジで話していた気の良さそうな中年男が、「やあ、きみたちか! すわるところはまだ? じゃあ、ぼくたちのテーブルに来ないか? ちょうど2席空いてるし・・・・・・」と、問いかける。渡りに船と彼の後をついて行けば、そこはなんと主賓席、新婦の父親がその中年男だったのだ。
こうなれば、ジタバタしても始まらない。新郎新婦の親戚に囲まれながら盛り上がるしかない。次から次へと挨拶に来る招待客は、そのテーブルにいる以上、われわれ2人も親戚だと誤解し、しかたなく話を合わせるうち、いよいよ盛り上がってゆく。めでたく式が終わる頃、われわれは善行の後の清々しさに包まれていた。そして帰る間際、C氏から「なぜ、おまえたちが主賓席にすわっていたの?」と聞かれ、事情を説明したら彼は大笑い、未だ「デュークス・メン」の間で語り草となっている。
この日本人2人による「ウエディング・クラッシャーズ事件」があった少し前だろうか。とある用事で私はマイアミへ行った。当時のマイアミといえば、アル・パチーノ主演作「スカーフェイス(1983年)」がヒットして間もなく、私の頭には映画のイメージが一杯だ。ビーチだって今のような綺麗なものに再開発されておらず、建物はどれも戦前の古びたアパートや養老院で、「スカーフェイス」そのままだった。
「スカーフェイス」
「おっ、あれが(パチーノ演じる)トニー・モンターナの殺人現場だ!」と、映画そのままの景色へ見入ったり、当時はまだ2軒しかない日本レストランの1軒で箸さえ通らぬ岩のごとき冷奴を食べたのが懐かしい。また、懐かしいといえば「スカーフェイス事件」・・・・・・当時のアメリカといえば、コカイン入りの「コカコーラ」が売り出されて流行った頃に次ぐ第2次コカイン全盛期の後半であり、そんな時代背景へ身を投じたのがこの事件だ。
全盛期のピークは、ちょうど私がL・A(ロサンゼルス)に引っ越した'76年前後で、私のような音楽シーンで生活する者、あるいは映画関係者なら状況を好むと好まざると、また自分がコカインをやろうとやるまいとお馴染みの世界であり、ビジネスマンですら商談の席でコカインをやるのは珍しくない時代だった。したがって本場であるマイアミへ行った時、同伴者から「せっかくマイアミまで来たんだから、買ってみたいなぁ。ねえヨコチン、買いに行くの付き合ってよ?」と頼まれ、「うん、そいつは面白そうだ!」と好奇心をくすぐられてしまう。
頼まれた以上、責任がある。そこで、まず私はホテルのコンシアージ(案内)デスクでキューバ人街の中心がどの辺りか聞いてみた。どうせ、L・A(ロサンゼルス)ならメキシコ人街はイーストL・Aと相場が決まっているように、マイアミだって蛇の道はへびだ。行ってみると、思ったとおりイーストL・Aと同じような感触の寂れた住宅街で、南カリフォルニアならぬマイアミの陽光だけが燦々と降り注いでいる。
現在のマイアミ・ビーチ
タクシーを降りて辺りを見回した同伴者は、「ヨコチン、本当に大丈夫かい?」と、不安そうな目で私を見ながら聞く。その目を見ると、かつてイーストL・Aへ飲みに行く私を、アメリカ人の友人たちが変態視したのを思い出す。マイアミの場合、私自身、まったく先は見えないが、生まれつきの楽天的性格から、「大丈夫、大丈夫!」と言いながら、その実、弾ける寸前まで神経が張り詰めていた。
こうして半ブロックばかり歩き、四つ角の左手に1人の男が歩いてくるのを見た私は、「いた、あれだ!」と、押し殺した声で叫ぶ。髪がアフロで露骨なキューバ人顔を除き、胸元を目一杯はだけたオープンシャツ姿や、そこへぶらさがった思い切り重そうな金のペンダントなど、モンターナその人と言っても過言ではない。さっそく声をかけて、コカインが買えるかどうか交渉してみる。
結果、私と同伴者は近くのバーでしばらく待たされるのだが、そこへズカズカと入って行く「私のモンターナ」の態度は、まるで自宅に帰った主人のような横柄さで、改めて地元での力を痛感させられた。つまり、私の目のつけどころが正しかったわけだ。そして、30〜40分待たされた後、子分2人を従えて戻ってきた「私のモンターナ」は、われわれにトイレへ付いて来いと指で合図を送る。子分の1人がトイレの表を固め、もう1人はドアの内側で睨みをきかす。私が出る幕はここまでで、同伴者が交渉を引き継ぎ、すべてはスムーズに終わったばかりか、交渉結果は同伴者へ大満足なものだった。
以来、「マイアミ・ヴァイス」などのTVシリーズを含めて、この類(たぐい)の映画を見る私の捉(とら)え方が変わったことは言うまでもない。そういう意味で、アメリカへ来て映画を実感できた例が、もう1つある。ちょうど20歳(はたち)の私は「ファニー・カンパニー」というバンドでワーナー・パイオニアから最初のアルバムを出そうとしていた1971年、アメリカのニュー・シネマの一環で「バニッシング・ポイント」という映画が公開された。
物語の詳細はさておき、アメリカ大陸を横断する陸送屋がテーマであるこの映画は、「イージーライダー(1969年)」のピーター・フォンダやデニス・ホッパーが、なぜ旅に出て最後は殺されるのかが重要でないごとく、ほとんど感覚的な映画だ。そして、感覚的な映画である故、じっさい広大な北米大陸を走ってみないとわからない部分はある。
「バニシング・ポイント」
加えて、幸い(?)私の知り合いが引越屋であったため、常識では考えられらい条件付で陸送をする羽目となった。そもそも、その引越屋の社長と知り合ったのは、私が日本からL・A(ロサンゼルス)へ移って間もない頃、たまたま彼の引越屋でアルバイトをした時だ。仕事振りを気に入られたものの、私はミュージシャンとしての仕事があり、次回からは知り合いの日本人を紹介し、なんだか請負業者の真似事をする時期があった。
そんなある日、社長から電話でシカゴまで車を転がしてくれないかと言う。なぜ陸送屋を雇わないのか聞くと、それでは間に合わないらしい。じゃあ、若い者へやらせましょうかと聞くと、大事なお客様の車だからきみに頼みたい・・・・・・結局、引き受けたものの、初めての大陸横断が魅力であったことも然ることながら、無理な条件のぶんだけギャラは桁違い・・・・・・しごく単純な理由なのだ。もっとも、いざ東京=大阪間3往復半の距離を2日半で走るとなれば、その厳しさたるや想像を絶する。
まず、物理的に考えて、ひたすら走り続けないと間に合わず、途中モーテルで一休みするなど許されない。半日目ぐらいから睡魔との壮絶な闘いが始まる。もちろん、地図を読み間違えれば一貫の終わりだ。こうして着いたシカゴの届け先からタクシーでオヘア空港へ向かう私の頭は真っ白で、タクシーの窓から見たシカゴの冬景色だけが、なぜか今でもくっきりと残っている。そして、オヘア空港で帰りの便に乗り込んだ瞬間、私は熟睡し、次の瞬間スチュワーデスに起こされて目を覚ますと、早LAX(ロサンゼルス国際空港)で他の乗客がすべて降りた後だった。
その後、再び「バニシング・ポイント」を見た時の印象は1971年当時とあまりにも違っており、改めて現実の体験が映画を見る上で大きく影響することを知ったのである。「スカーフェイス事件」と「ウェディング・クラッシャー事件」は、それから起こったのだ!
横 井 康 和