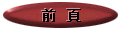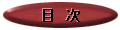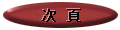映画とライフル
早いもので、この映画とまつわるエッセイを連載し始めて10年の歳月が過ぎた。第1回目の「映画と拳銃 (上)」から始まって、なるべく他にないユニークなテーマをと考え、様々な角度から書いてきたつもりではあるが、どうしても自分の得意の分野に偏ってしまうのはしかたがない。過去10年を振り返ってみると、主流はやはり銃器やコンピュータ絡みの映画論で、そこへ日米間の文化の違いといった日ごろ感じている私の主観が頭をもたげる。
レミントン・ローリング・ブラック時には「映画と糞(シット)」のような、わけのわからない英語教室もどきまで登場しながら、とりあえず11年目へ突入したところで、ここらでいったん原点に戻ってみたい。そこで、今回選んだテーマが「映画とライフル」というわけだ。アメリカは日本と違って一般個人が銃器を所有できる。そういった背景は当然ながらハリウッド映画へ反映され、結果として日本のような現実離れした銃器絡みのシーンがほとんどない。
加えて、自ら「ガンパーソン(銃器愛好家)」である関係上、戦争映画をはじめとするハリウッドのアクション映画を見ていると、そこで使われている銃器に感心させられることが多々あるのだ。古くはゾルタン・コルダ監督作「四枚の羽根(1939年)」で、劇中カルファの手先が持つ「レミントン・ローリング・ブラック(写真)」といい、あるいはイギリス軍が「ロング・リー・エンフィールド(写真)」を扱う様は、コルダの拘りが表われているのだろう。
小道具係は銃器へ拘っているのに役者の扱い方が悪かったり、その逆も多い中、「四枚の羽根」は上手く両者のバランスが取れており、アフリカを舞台に繰り広げられた「オムダーマンの戦い」をドラマチックに描きあげている。良く出来た銃撃戦映画というだけではなく、映画史上でも秀作の1本だ。
ロング・リー・エンフィールドそして、「四枚の羽根」の公開から四半世紀を経た1966年、「砲艦サンパブロ」が封切られる頃、ようやく私は映画館へ通い始めていた。したがって、こちらのほうが見た順序は「四枚の羽根」より早く、第二次大戦前の中国を舞台にスティーヴ・マックィーン演じる米軍水兵が演じる銀幕のドラマへ心を躍らせたものだ。同じマックィーンの主演作では、少し前にヒットした「大脱走(1963年)」よりこちらのほうが印象深かったのは、そこで登場する「ブローニング・オートマチック・ライフル(写真)」が少なからず影響している。
当時、それがブローニングだと知らなかった私も、この機関銃の持つ存在感から受けたインパクトは強烈で、後の「M-16」や「AK-47」が活躍する数多くのベトナム戦争映画の比ではなかった。いわば当時のアメリカと中国のあからさまな武力の差を象徴していたのがマックィーンの撃つブローニングであり、史実に裏付けられたリアリティーならではのインパクトを持つ。
銃器が係わる時代劇では、その選択や扱い方が時として結果を左右する。綿密な時代考証へ更にマニアックな選択で映画を盛り上げることも出来るいっぽう、些細なミスでさえ映画は台無しになってしまう。だからこそ、砲艦サンパブロの乗組員であるマックィーン演じる水兵へブローニング・オートマチック・ライフルを持たせた選択が心憎いのだ。さすが、「ウエスト・サイド物語(1961年)」や「サウンド・オブ・ミュージック(1964)」のロバート・ワイズ監督作だけのことはある。
ブローニング・オートマチック・ライフルハリウッドで銃器を代表する監督の一人といえばジョン・ミリアス、一連の「ダーティー・ハリー」を見るまでもないだろう。NRA(米ライフル協会)」のメンバーであり銃器のコレクターとして知られるミリアスの代表作「風とライオン(1975年)」もまた、銃器ファンなら見過ごせない作品だ。時の大統領ルーズベルトを巻き込んだ実話がベースとなった物語は、しょっぱなの回転銃(リボルバー)「ブルドッグ」からルーズベルトの「1895ウィンチェスター」や通称「ポテト・ディガー」と呼ばれる機関銃「コルトM1895」その他、いやはや堪えられない。
新しいところでは、「ハムナプトラ/失われた砂漠の都
(1999年)」が銃器へ相当拘っていた。まず、オープニング・シーンでは外人部隊が当時の一般的な「マンリヒャー・ベルチエ」でなく「モデル1996レベルズ(写真)」を撃っているから凄い。よくぞ撮影用の空砲を集めてきたばかりか、このボルト・アクション・ライフルは、ただでさえチューブ状の弾奏(マガジン)を備え、空砲を撃つのが難しいはずである。銃器担当の小道具係は、間違いなくマニアックな人間だ。
モデル1996レベルズ物語が展開するにつれ、その拘りはエスカレートしてゆくから嬉しくなる。主演のブレンダン・フレイザーが持つ拳銃はフランス製の回転銃(リボルバー)「モデル1873オードナンス」と、1920年代が舞台の映画では実際問題として古すぎる選択だが、銀幕上の効果は抜群であり、何よりも不自然な選択ではない。フレッシャー以外の敵や味方が持つ銃器は、当時のコルト、ウィンチェスター、モーゼルなどに加え、「レミントン・ダブル・アクション・デリンジャー」までが登場する。
「ハムナプトラ・失われた砂漠の都」の続編「ハムナプトラ2・黄金のピラミッド(2002年)」は、やはり嬉しいほど銃器へ拘る映画であったが、「スターリングラードの戦い」を描いた同年の作品「スターリングラード」も、負けず劣らず銃器には拘っていた。プロデューサーのジョン・D・スコフィールド(「ブラザーズ・グリム」)が銃器や軍関連のコレクターとして有名と聞けば、それも頷ける。したがって、映画で登場するすべての軍服から武器や備品までが、可能な限り忠実に再現されていたことは言うまでもない。
「スターリングラード」を見れば、ソビエト軍とドイツ軍の狙撃手(スナイパー)が、使う銃器はもとより軍事情報(インテリジェンス)の捉え方など、まったくスタイルが違うのがよくわかる。また、この映画でソビエト側の「モシン・ナガン(写真)」やドイツ側の「K98モーゼル」の扱い方は、たとえば「プライベート・ライアン(1999年)」で米軍の狙撃手(スナイパー)が「1903A4」の照準(スコープ)を取り扱っていたような非現実的なミスは犯さず、第2次世界大戦がテーマの映画でも秀作の1本といえるだろう。
モシン・ナガンちなみに、第2次世界大戦がテーマのハリウッド映画といえば、かつてはドイツ軍か日本軍が悪役と相場が決まっており、われわれ日本人から見ると首をかしげたくなるようなものも少なくなかった。しかし、そういった類の映画でさえ、摩訶不思議な日本軍の持つライフルだけは本物である点が羨ましい。「三十年式有坂歩兵銃」に始まって、その後、「サンパチ銃」として知られる「三十八年式」、「四十四年式」、「九七式」へと発展した6.5ミリ口径のライフル、および7.7ミリ口径にパワーアップされた「九九式」や、その落下傘兵バージョンともいうべき「二式」などは戦勝国のアメリカだと、いくらでもある。
私自身、「九九式」の他「南部十四年式」なども持っているが、終戦後、それだけアメリカへ流れてきた以上、「7.7×58ミリ・ジャパニーズ」や「8ミリ南部」と呼ばれる実包の入手は他より値段が張るだけで問題はない。時たま邦画で、いかにもモデルガンといった「南部十四年式」を見ると、可哀そうになってしまう。もっとも、さすがのハリウッドといえど「九九式」や「南部十四年式」が登場する映画で、わざわざ「7.7×58ミリ・ジャパニーズ」や「8ミリ南部」の空砲まで用意したりはしないはずだ。
その点、日本軍の銃器同様、戦後、大量にアメリカへ流れ込んだドイツ軍の銃器の場合、かなり事情が違っている。中でも「ワルサーP38」と「ルガーP08」については「映画と拳銃 (下)」でも書いた。同じことがライフルや機関銃に言える。「モーゼル」や「シュマイザー」の場合は特殊な口径の「有坂」と比べて撮影で使い易い。ただ、映画でライフルを使う様々な要素を考慮したとして、結局、作る側が何を描きたいかで最後は決まる。もし「7.7×58ミリ・ジャパニーズ」の空砲を用意しないと、いい場面が作れないなら、用意するだけの話・・・・・・残念ながら、日本の銃器を考えてみると、そういった場面は思い浮かばない。
横 井 康 和