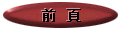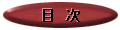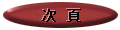映画と死
約2ケ月前の8月29日午前11時22分、それまで2年間、癌と戦ってきた私の姉が、とうとう他界した。その2年間の戦いは、たんに姉一人の戦いでなく家族全体の戦いでもあった。そして、戦いと表裏一体となって愛の形が浮かび上がってゆく。中でも母の愛の深さには、ただただ頭が下がる。9月の下旬、L・A(ロサンゼルス)へ戻った私は、ますますその想いを深めてゆくのだ。
「愛と死をみつめて」
私がまだ中学生時代、毎朝の礼拝で歌わされた賛美歌の歌詞は、40年を経た今、まったく憶えていない・・・・・・そう思っていたところが、母の日礼拝で、わずか3回歌っただけの讃美歌510番、「幻の影を追いて 浮世にさ迷い 移ろう花に誘われ行く 汝が身のはかなさ 春は軒の雨 秋は庭の露 母は涙 乾く間なく 祈ると知らずや・・・・・・」という歌詞が、L・A(ロサンゼルス)へ戻って以来、南カリフォルニアの陽光を浴びながら運転中、知らず知らず口ずさんでいたりする。
こうした自分自身の体験から、姉の死をきっかけに改めて映画や小説のテーマとしての「死」へ関心を持った。ある意味で死は人間ドラマの原点だ。当然ながら多くの映画や小説でテーマとなってきた。たとえば1964年度作「愛と死をみつめて」があれだけヒットしたのは、題名(タイトル)どおり「愛」と「死」がテーマのメロドラマ故であろう。
「ある愛の詩」
原作は当時話題となった実在の恋人同士の書簡集で、浪人生の誠(浜田光夫)が入院した病院で道子(吉永小百合)と出会い、大学へ入って2年目に再会した時も、彼女の病状は思わしくない。2人は文通を続けながら、やがて道子も大学へ入るが、軟骨肉腫という奇病で再び入院、誠の愛に支えられて彼女は手術を繰り返す。顔の左半分を切除までするものの、不治の病には勝てず、21歳の誕生日、手術の半ばでこの世を去った。
数年後、これと同じようなパターンで大ヒットを飛ばすハリウッド映画が「ある愛の詩(1970年)」である。オリバー(ライアン・オニール)とジェニー(アリ・マッグロー)は大学の図書館で出会い、育ちの違いを超えて結婚、貧しいが幸福な日々を送っていた。しかし、ジェニーは白血病で・・・・・・「血液の癌」と呼ばれる白血病や肉腫が癌と同類の病気であることは、今さら言うまでもない。それらが不治の病であるのかどうかは西洋医学と東洋医学で見解の相違があるにせよ、命を賭けた壮絶な戦いを意味することは確かだ。
それらの壮絶な人間ドラマを映画として描く場合、アプローチは特定されず、「愛と死を・・・」や「ある愛の詩」のような正攻法のアプローチもあれば、同じ状況を裏から捉えたアプローチもある。つまり、喜劇の主人公にとって、それが悲劇であるごとく、死を笑いのネタにすることだって簡単だ。要は仕上がった映画がいいか悪いか・・・・・・こればっかりは観客一人一人で判断の基準が違う。
「ラブ・アンド・デス」
たとえば、ウッディー・アレンの監督主演作「ラブ・アンド・デス(1975年)」は、題名(タイトル)だけなら「愛と死を・・・」とほとんど同じ響きである。しかも、たんなるメロドラマでなく、戦争というさらに壮大な背景で展開するドラマなのだ。ただ、アレン・ファンならご存知のとおり、彼のスタイルを平たく言うとパロディーであり、決して正攻法のアプローチではない。そこから「マンハッタン(1979年)」のような美しい映像が生まれるのである。
アレンのようなユニークなパターンは一先ずおいて、正攻法のアプローチでも、映画の中での死が必ずしも病気と限らないのは当たり前の話だ。映画史上、もっとも成功した(稼いだ)「タイタニック(1997年)」を思い出してほしい。あの映画が、やはり「愛」と「死」をテーマにしていることは明白だろう。
「タイタニック」
タイタニック号の惨事そのものが多くの命を奪った事実も然ることながら、その中で生き残ったローズ(ケイト・ウィンスレット/グロリア・スチュワート)と、彼女を助けようとして死んだジャック(レオナルド・ディカプリオ)、そして2人の愛でこの映画は成り立っている。また、主人公2人の「育ちの違い」たるや「ある愛の詩」どころではない。まさに身分を超えた「愛と死の人間ドラマ」なのだ。
「死」との対極で「生」もまた「愛」と並ぶ重要な要素である。「スターウォーズ・エピソード3/シスの復讐(1997年)」などがその好例で、師オビ=ワン・ケノービ(ユアン・マクレガー)と戦いの末、死にかけたスカイウォーカーが蘇ってゆくシーンと、ダークサイドへ走った良人に生きる気力を失くした女王パドメ・アミダラ(ナタリー・ポートマン)が死んでゆくシーンを交互に描きながら、ぐいぐい「エピソード4」へ焦点を定めてゆくクライマックスあたりは、さすがジョージ・ルーカスといえよう。
「スターウォーズ
エピソード3
シスの復讐」このストーリーの一部を日本のメロドラマに置き換え、癌で死にかけた欲深い亭主が、その欲の深さ故、癌を克服してゆく姿と、死にかけた亭主の欲深さへ絶望した故、生きる気力を失くした妻の姿を対比してみても面白い。さらに、その亭主が日本の首相だとしたら、ますます興味深い展開も考えられるし、そこへ北朝鮮との緊迫した情勢は一転・・・・・・ちょっと悪ノリか?
ともあれ、「死」と「生」の対比といえば、黒澤明監督の名作「「生きる(1952年)」がある。市役所の市民課長、渡辺勘治(志村喬)は30年間無欠勤という模範的な役人ながら、ある日、胃癌で余命がいくばくもないことを知った。死に別れた妻との間の息子からは冷たくされ、絶望と孤独の中で街へ出て飲み慣れない酒を飲む。
「生きる」
こうしてドラマが展開し、自分の人生とは何だったのかを考え始めた渡辺が、最初は無断で仕事を休み好き勝手なことをしてみた結果、突然、職場へ戻るばかりか、市民のため下水溜りを改善した小公園を作ることに情熱を注ぐ。死の直前、小公園が完成するまでの過程は、渡辺の葬式へ出席した同僚たちの会話から浮かび上がるのであるが、その会話から観客は「もし渡辺が胃癌にならなかったら公園のプロジェクトは実現しなかったのでは?」と疑問を抱くはずだ。
つまり、癌で死の宣告を受けたからこそ、それまで意味もなく生きてきた人生が意味を持った・・・・・・「生きる」とは何かを黒澤はこの映画で問いかけた。私の姉は2年間の癌との戦いを始めた当初、この問題を自分自身へ問いかけた。その姉を見て、私は自分の生き方が少なからず変わった。そして、2年間で数回、日本へ帰るうち、一つの出会いによって私の人生は大きな局面を迎えた。姉が他界した8月29日から数えて、ちょうど1週間後の9月5日、私は55歳にして初めて結婚するのである。
横 井 康 和