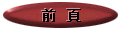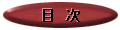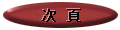映画と妊娠
生物学的見地から人生の目的が種族保存であるとすれば、前回のテーマ「結婚」は「妊娠」と言うメイン・イベントの序曲(プレリュード)といえよう。したがって、映画のジャンルとして考えた場合、「妊娠」映画にも様々な人間ドラマが集約されている。たとえば、今年のアカデミー賞で主演女優賞へノミネートされたエレン・ペイジ主演作「JUNO/ジュノ(2007年)」は、ティーンの妊娠がテーマとなり、物語はティーンの妊婦やその家族と生まれてくる子供を養子に貰う若い夫婦が核となって展開してゆく。
「JUNO/ジュノ」
ペイジの主演女優賞は逃した「JUNO/ジュノ」ながら、しっかりと脚本賞を獲得しているとおり、そこで展開する物語がいかにもアカデミー賞好みの渋さなのだ・・・・・・こう言うと、「それって褒(ほ)め言葉、それとも貶(けな)し言葉?」と、疑問を投げかけられるシニカルな映画ファンはおられることと思う。じっさい、最近のアカデミー賞ノミネート作がますます芸術的といおうか冥(くら)くなってきた傾向は否めない。「JUNO/ジュノ」の場合、そういうネガティヴな意味合いでなく、従来のポジティヴな意味合いでの「アカデミー賞好み」なのである。
「ウェイトレス 〜
おいしい人生のつくりかた」
次にアカデミー賞と関係ないが、「妊娠」のジャンルで去年は話題作がもう2作あった。1作は「ウェイトレス 〜おいしい人生のつくりかた(2007年)」、この映画が興味深いのは、だらしのない男たちと力強く生きる女性たちを描いた図式が、溝口健二(「祇園囃子」)の描く世界を彷彿とさせる点だ。主人公のウェイトレスは良人を毛嫌いしながら妊娠してしまう。そして、まったく繊細さ(デリカシー)のない良人と比べ、いっけん理想的な産婦人科医と関係を持つものの、相手は妻帯者で妻と別れそうもない。祇園の鉄則を破り自ら芸者と駆け落ちまでした溝口が描く世界へ登場する男たちは、芸者になった娘に物乞いをする情けない父親や、金や権力で女を意のままにしようとする実業家や役人など、観客へ拒否反応を抱かせる者ばかりである。そういう男たちを相手にしてきた女たちの生き様が、彼の作品からは脈々と感じ取れるはずだ。同じく「ウェイトレス・・・」も、すぐ暴力を振るう最低の良人ばかりか、いっけん理想的な産婦人科医でさえ優柔不断で信用できない。つまり、現実の世界そのままといえよう。
「ノックド・アップ」
もう1作の話題作「ノックド・アップ(2007年)」の場合、状況が逆で、妊娠の相手は行きずりの他人である。「ウェイトレス・・・」が出産をきっかけとして良人や愛人と決別し、新たな人生を歩み出すいっぽう、「ノックド・アップ」では出産が新たな人間関係を生み出す。どちらも、現実の世界でお馴染みのパターンだ。日本では未公開の「ノックド・アップ」だが、この映画で一躍脚光を浴びたキャサリン・ハイグルの次作「幸せになるための27のドレス」は今月(5月)末、日本でも公開される。ちなみに、「結婚」映画と並んで予想外のヒット作が多いのもこのジャンルの特徴だろう。「JUNO/ジュノ」のオスカー・ノミネートは大方の予想と反したばかりでなく、「ウェイトレス・・・」や「ノックド・アップ」の予想外のヒットが、それまではほとんど無名だった主演のケリー・ラッセルやハイグルを突如として「いま話題の女優たち」へ仲間入りさせた。
これら去年(2007年)のヒット作3本が最近の「妊娠」映画の傾向だとしたら、パターンはその他いろいろあり、同じ「妊娠」というジャンルの映画でも、従来のジャンル分けだとコメディーと限らず千差万別の内容がある。いちおう「コメディー」へジャンル分けされる先の3作も、基本的には我々の日常生活を描いた真面目な人間ドラマだ。そして、日常性を脱したレベルのコミカルな「妊娠」映画が、それはそれで少なくない
「ジュニア」
日常性を脱したレベルでコミカルな「妊娠」映画といえば、ここしばらくカリフォルニア州知事の仕事で忙しく映画界とは遠去かっているアーノルド・シュワルツェネッガー主演作「ジュニア(1994年)」あたりがまず思い浮かぶ。男の妊娠という発想からして可笑しい上、シュワルツェネッガーとダニー・デヴィートのユニークな顔合わせも効を奏し、内容は今一ながら米国内だけで3、672万ドル(約37億円)の興行成績を収めた。そして、この翌年に倍近い6,788万ドル(約69億円)を稼ぐヒュー・グラント主演作「9か月(1995年)」もまた「妊娠」がテーマのコメディーなのだ。妊娠が人生のメイン・イベントゆえコメディーへうってつけのテーマであるなら、見方を変えれば非常にシリアスな側面を持つ。「喜劇を演じる当人へは悲劇である」というとおり、上記の映画でさえ主人公にとってシリアスなドラマだが、そのシリアスなドラマを客観的な視点から茶化すのではなく、そのまま描いた映画も多く、それを突き詰めてゆくと、ホラーへもうってつけのテーマだとわかる。
「ローズマリーの
赤ちゃん」
ミア・ファーロウ主演作「ローズマリーの赤ちゃん(1968年)」などがその典型で、発想の原点は現実の世界で五体満足な子供が生まれるよう祈りながら、そこへ伴う不安であろう。加えて、世の権力者たちは世継ぎとして男児を求めてきた。つまり、たとえ五体満足な子供が生まれようと満足できるとは限らない。「ローズマリー・・・」の場合、ファーロウが身ごもるのは権力者どころか悪魔の世継ぎだ。しかし、これまた考えようで、悪魔の世継ぎを身ごもった時点で身の保障をされたも同然といえるかもしれない。時代を反映してか、約30年後のシャーリーズ・セロン主演作「ノイズ(1999年)」だと、彼女が身ごもるのはジョニー・デップ演じる宇宙飛行士の良人が宇宙から持ち帰ったエイリアンの種だ。精神分析医でない私は、悪魔やエイリアンが何の象徴なのか追求する気はない。ただ、それらが現実の夫婦生活を脅かす何らかの存在の象徴であることは容易に想像がつく。
55歳で初めて結婚し、まだ1年8ケ月という私の場合、幸いそういった夫婦生活を脅かす存在の心配はないものの、この歳でいざ子供を作ろうとすれば若い時ほど簡単でないことを痛感させられる。コメディーでもシリアスな人間ドラマでもホラーでもなく、仄々(ほのぼの)としたごくありきたりのファミリー・ドラマを求めるのが、あんがい難しい年齢へ差しかかった現状を認識しつつ、とりあえずこのジャンルでもがんばってゆきたいと思う。
横 井 康 和