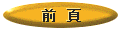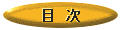風の街 (上)
シカゴといえば、このコラムでは「シカゴで翔んだ日」と「ルート66(その1)」に続く3度目の登場である。今回も、やはり日本からの撮影絡みのエピソードだが、この時は滞在期間が随分長かった。家庭の主婦を対象とした某TV番組では、毎朝、世界各地を紹介するコーナーがあり、それをシカゴでまとめて撮ろうというのだ。
大型船舶の通行時に開く2階建の
可動橋は道路の下を環状線が走るいくら1回分の放映時間は短くても、回数が多ければ多いほど、その数だけのネタを集めなくてはならない。また、ロケの期間が長いからと、けっして余裕はないのが日本の業界である。厳しいスケジュールを可能とすべく、前もってディレクターの送ってきた資料は、まとめるとかなりの量だ。よくこれだけ見つけてきたと感心するぐらいのネタが揃って、なお日本側はそれ以上を要求する。いろいろ捜し続けても、目ぼしいネタのほとんどが日本から送られた資料でカバーされており、それなら現地へ先乗りして捜せばいいということになった。
単身シカゴへ乗り込んだ私は、ひとまず宿泊先のオヘア・ヒルトンで落着く。さっそくレンタカーを借りて、すでにあるネタを確認がてら新しいネタを捜し始める。数日後、これといった新ネタが見つからないまま、なんとかなりそうな気もしてきた。そして、スタッフより一足早く着いたディレクターへ現状を報告すると、私の判断は甘かったことを思い知らされる。
この時が初めてであり、どういうタイプのディレクターなのかは、いざ仕事を始めるまでわからない。もっともっとネタがほしいと言われ、血眼で捜すうちレポーターやスタッフも到着し、いよいよ撮影開始だ。と同時、ネタ捜しに追われ、連日2〜3時間しか寝る時間はないままロケが続く。ネタ捜しも範囲を広げ、隣のウィスコンシン州マディソンで「人形の館(ロック・オン・ザ・ハウス)」を見つけると、それをシカゴの撮影と前後して撮りにゆき、ちょうど「インディー500」の開催中ならインディアナポリスを目指す。隣の州まで行くとなれば出発は午前4時などざらである・・・・・・前日の解散が深夜を回っていようとも!
もう少し具体的な例をあげて説明しよう。まず東京で早朝ロケを行った後、そのまま車で次のロケ地、新潟へ向かったとする。着いてみると、現場は思ったほど良くない。そこでスタッフの1人が大阪でのロケを提案し、ディレクターも同意、今度は南を目指して走り出す。大阪のロケが終わり、深夜の東名を帰路につく頃、車内は運転手を除いた全員の寝息で満たされていた。博多ロケが待ち受ける翌日のため、運転手は東名をひた走る。
この冗談みたいな話が現実となるのは、アメリカの州を都道府県の感覚で捉えてしまうからだろう。京都市内のロケ中、若狭湾まで足を伸ばす感覚が、アメリカの地図を見る限りロサンゼルスからサンフランシスコへ行くのと変わらない。しかし、距離的には若狭湾どころか京都から東京までの違いがある。ばかりか、予算枠は限られており、運転手も他ならぬ私が兼任するシビアーな現状だ。
もっとも、長いロケを通じて遠出をしたのは数回で、もっぱらシカゴ市内および近郊を撮りまくった。その間、「ハリウッドの故郷(ハートランド)」がキャッチフレーズというだけあって、市の広報係は映画やTV撮影へ積極的に協力しようとする姿勢なのが、ありがたい。「高架(エレベイテッド)電車」を略して「エル・トレイン」
日本流に略せば「コウデン」と、あまり縁起は良くない響きだが!?地元では「ループ(環状線)」の愛称で親しまれる線路下の道路を走りながら撮影中、目前の情景が脳裏へ浮かぶさまざまな映画のシーンと重なってゆく。慌(あわただ)しく予定を消化した後は、たとえわずかな時間の余裕があってもこの撮影クルーに休もうという発想はない。ある日、シカゴ近郊のロケが思いのほか早く終わり、次の予定は何も決まっていなかった。そこで、昼休みのための店を捜し始めて間もなく、スタッフの1人が、
「そういえば、日本を出る前に新聞で読んだ記事は、たしかこのあたりだったような気がするな」と言う。曰(いわ)く、その記事は地元の子供が作った本格的な「ハウス・オン・ザ・トゥリー」を紹介したものらしい。名前のとおり「木の上の家」とはアメリカでごくありふれた子供の遊び場所だが、ふつうは裏庭の木に小さな子供がせいぜい2人か3人入れる程度の小さな箱を乗せたお粗末な代物(しろもの)だ。しかし、記事で紹介された家たるや、最初はたんなる箱から増築を重ね、とうとう水道と下水まで引くに至っているのである。興味を示したディレクターから、
「よし、それでいこう。ヨコチン、地元の新聞社へ問い合わせてみてくれ!」
さっそく道端の公衆電話でバンを停めた私が2〜3の新聞社を当たってみると、たまたま日曜日のせいか誰も答えられない。週明けにかけなおせば、たぶんわかるそうだが、こっちはそれだけ待つ時間の余裕がない。しかたなく「ハウス・・・」の取材は諦めたわれわれが近くで昼食を取り始め、ハンバーガーを食べる間、どうせ「ダメモト」と私は囲りの客全員へ聞くだけ聞いてみようと思い立つ。そこで、まず声をかけた隣のテーブルの男性が、
「ああ、その家ね。知ってるよ」
さりげない相手の言葉に自分の耳を疑いつつも詳しく聞くと、なんでも記事の家を建てた子供の両親は彼の親友なのだそうだ。ばかりか、道順を尋ねれば自ら現場までわれわれを先導し、家族を紹介しようと申しでる。着いてみると幸い在宅中の家族は取材に協力的で、満足のゆく映像が撮れた。ただ、感心はしたが木の上の家そのものは、しょせん子供が作ったものである。それより、いまだ信じられないのは、いったん諦めたネタが向こうからやってきたことだ。同じような出来事は他の取材でも起こり、ここらが「ものごと、必死で捜せば何とかなる」と楽観視する私の気楽な性格を形成してゆく原体験の一部なのだろう。
私の両親は、とくべつ占いに凝っていなかったが、幼い頃、私は何度か運勢を見てもらい、いつも幸運に恵まれた人生を送る相だと言われた記憶がある。見方を変えれば、この記憶は先入観となり、「ものごと、必死で捜せば何とかなる」と楽観視すればこそ、がんばれたのかもしれない。そう考えると「風の街」シカゴ近郊で木の上の家を捜した体験は、後の人生に大きな収穫をもたらしてくれる旅となった。 (続く)
横 井 康 和